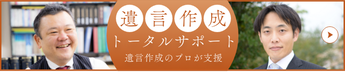- トラブル解決総論
- 相続・遺産分割トラブル解決
- 夫婦子供のトラブル解決
- その他親族トラブル解決
- 企業・事業者のトラブル解決
- 不動産・借地借家・隣近所のトラブル解決
- 不動産の取得時効と登記の関係
- 不動産賃貸借における関西方式・関東方式
- 敷金・保証金・建設協力金の違い
- 賃貸借契約の当事者が変更した場合、誰が誰に敷金を返せば良いか?
- 敷引特約の有効性
- 賃貸借契約で「中途解約を禁止する条項」は有効か?
- 賃貸借契約における更新料条項の有効性、更新料不払いの効果、法定更新との関係ほか後日もめないための具体的な対策
- 賃貸借契約で遅延損害金を年14.6%とする条項は有効か?
- 明渡しが遅れたときに賃料倍額の使用損害金を請求する条項は有効か?
- 借主の軽微な契約違反だけでは解除できない賃貸借契約「信頼関係破壊の法理」
- 家賃滞納による建物明渡請求
- 滞納賃料(家賃・地代)の請求を受けた連帯保証人の対応
- 賃借人が連帯保証人を立てない場合、賃貸人は賃貸借契約を解除できるか?!
- 借地に関する契約
- 借地権登記できない場合の「借地上の建物登記」民法177条の例外
- 建物賃貸借の契約期間を設定するときの注意点
- 借地上の建物を賃貸借するときの注意点
- DIY型賃貸借契約のメリットと注意点
- 原状回復・敷金返還に関するトラブル解決
- マンションの滞納管理費・修繕費・積立金の回収
- マンション義務違反者への対応
- 連棟建物(長屋、二戸一、三戸一)の切り離しトラブル
- マンション上階や二戸一の隣家からの水漏れトラブル解決
- 隣近所とのトラブル解決
- 隣地の建築計画はどこで確認するか?!宅地開発から建物建築までの流れ
- 建物建築に際しての周辺住民への説明義務
- 隣地が境界ギリギリに建築するのを止められませんか?!
- 崖地の擁壁・石垣の補修に関するトラブル【図解】
- 境界トラブル(筆界と所有権界)
- 私道の通行権をめぐるトラブル
- (ケガの後遺症や精神疾患などが原因で)騒音、大声、奇行などの問題行動をおこし周囲に迷惑をかけている方への対応(グループ会員限定記事)
- 交通事故解決
- 消費者トラブルの解決
- 借金が返済できないときの個人の債務整理(任意整理・民事再生・自己破産)
- 判決が出ても従わない相手方への強制執行による債権回収(差押え)
- 刑事事件(被害者・加害者)
- 少年事件(被害者・加害者)
マンションの滞納管理費・修繕費・積立金の回収

皆さん全員が真面目に支払っている管理費を滞納する方がいると、腹が立ちますよね。マンション管理組合としても放置できません。
滞納されたマンション管理費等については、区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)が、特別な回収方法を定めています。当グループが、あなたの管理組合に最適な方法をご提案します。
また、所有者がお亡くなりになって相続人が分からないときは、毎月滞納管理費が溜まっていきますので、急いでご相談ください。司法書士が相続人を特定のうえ代理して請求します。
当グループは、滞納マンション管理費の回収に力を入れています。是非ご相談ください。
| もくじ | |
|
原告・申立人
マンションの管理者
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任することができる(区分所有25I)。管理者は、規約又は集会決議により、その職務に関し、区分所有者のために、訴訟当事者になることができる(区分所有26IV)。
マンションの管理組合(管理組合法人)
区分所有者に対して訴訟を提起する場合には、個別に集会決議が必要とされるのが実務です。
被告・相手方
区分所有者
区分所有者の承継人
滞納後に区分所有建物の特定承継があった場合には、特定承継人を被告とすることができる(区分所有法8)。
相続などで承継した一般承継人にも請求できることは当然です。
請求できる金額
管理費・修繕積立金
裁判所手続を使うときには、管理費などについて定めた「規約」又は「集会決議の議事録」が必要です。
任意に支払いを交渉する場合であっても、足下を見られないために、まず用意しましょう。
規約にあれば請求できるもの
- 約定遅延損害金(定めがなければ法定利率)
- 弁護士報酬、司法書士報酬
規約にない場合には、予め規約の改正手続を行なってから手続を進めるべきです。
将来にわたる管理費等
滞納状況等から、将来の管理費等の支払請求が認容された事例(東京地裁H10.4.14判決)
管理費等の消滅時効期間は5年(最高裁H16.4.23判決)
任意に支払われないときの回収方法は4種類
| 通常訴訟から強制執行 | 7条先取特権 | 8条特定承継人への請求 | 59条競売 |
|
|
|
|
以下、詳しく見ていきます。
7条先取特権
| 区分所有法第7条(先取特権) | |
|
|
7条先取特権の担保物件
|
管理費等を滞納された管理組合は、
の上に、先取特権を有しています(区分所有法7条)。 |
【1-1】「建物に備え付けた動産」について、2説がある。
- 建物内の動産全て(金銭、有価証券、衣服、宝石とか)を含むとする説(大審院T3.7.4判決は、民法312Ⅱ「その建物に備え付けた動産」につきこちらの説。)
- 建物内の動産全てではなく畳、建具、家具調度、機械器具に限定するとする説(稲本洋之助、鎌野邦樹著/コンメンタールマンション区分所有法[第2版]/日本評論社/2004/59p)
がある。
【1-2】専有部分に備え付けられたものに限らず、建物の共用部分である廊下や屋上に備え付けられたものでもよい(稲本洋之助、鎌野邦樹著/コンメンタールマンション区分所有法[第2版]/日本評論社/2004/59p)。
【2】滞納者が「それは、他人の物から差押できない」と主張してきた場合には?
7条先取特権は、民法319条(即時取得の規定の準用【3】)を準用していますので、「他人の物」と言われたとしても、その物に先取特権を行使できます。
【3】民法319条
第192条から第195条までの規定は、第312条から前条までの規定による先取特権について準用する。
- 第192条(即時取得)
- 第193条(盗品又は遺失物の回復)
- 第194条(同上)
- 第195条(動物の占有による権利の取得)

- これら以外の財産(滞納マンション以外の不動産、動産や債権など)への差押・配当要求である場合には、7条先取特権を主張できないことに注意が必要です。この場合には、民法上の一般の先取特権(民法303)を主張します(参照:滞納管理費を管理組合が回収する方法/新銀座法律事務所/最終閲覧210925)。
- 滞納者が、マンションを第三者へ賃貸し賃料収入を得ている場合には、その賃料を差押することができます。これは先取特権の物上代位(民法304)によるものです。
7条先取特権の順位
登記された抵当権に負ける(民336)
滞納した税金に負ける(国税徴収法8、地方税法14)
7条先取特権の実効性
- 競売しても先順位者に先に支払われて、管理組合にお金が戻らない可能性が高いときは、裁判所によって競売手続自体が「無剰余取消し」がなされてしまいます(民事執行法188、63)。
- 無剰余取消しがなされず、競売手続が進んだ場合には、滞納管理費等の回収が可能となります。
- 全額回収できなかったとしても、競落人は特定承継人(区分所有法8)に該当するので、競落人に対して残りを請求できます。
- 滞納者について破産手続開始決定がなされた場合でも、先取特権は別除権(破産法65Ⅰ)であるため、実行することができます。
- 管理組合が先取特権実行による競売申立をする前に、他の債権者が競売申立をしている場合には、配当要求することができます。
「通常訴訟から強制執行」か「7条先取特権」かの選択
事案に応じて、具体的な費用を算出し、検討なさるべきです。
<例>
所有者が死亡したためマンション管理費等に滞納が生じ、所有者の相続人にマンション管理費を請求する必要がある場合
| 通常訴訟から強制執行 | 7条先取特権による実行 |
|
訴訟コスト |
債権者代位による法定相続登記:数十万円 ▼ 先取特権による競売申立:100万円(予納金) |
|
※訴訟中に滞納所有者と示談できる可能性があり、その場合、競売費用がかからない。 |
※競売申立の予納金が確定する。 |
| 時間がかかる可能性あり |
早い |
|
判決で強制執行できるのは・・・ ○マンション ○マンション内の動産 ○相続人(固有)の全財産 |
先取特権で強制執行できるのは・・・ ○マンション ○マンション内の動産 ×相続人の全財産 |
|
マンションが売却不許可でも相続人固有の財産に強制執行が可能である。 |
「売却不許可」の可能性もある。 |
7条先取特権の実行による回収の流れ
(管理組合総会の決議)
申立に必要な次の書類が準備できない場合には、総会を招集しその承認を求めます。
- 代表者・管理者を選任した総会議事録
- 毎月の管理費等についての定めがある管理規約or管理費等について決議した総会議事録【1】
ご要望により、司法書士が総会に同席し、今後の流れについてご説明することも可能です。

滞納者所有マンション内の動産に対する動産執行の申立
- 原則として、動産執行を先に行なう必要があります。その理由は次のとおりです。すなわち、7条先取特権は、共益費用の先取特権とみなされます(区分所有法7条2項、民法306➀)。「共益費用の先取特権」は「一般の先取特権」ですので、民法335(一般の先取特権の効力)が適用されます。したがって、その実行に当たっては、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができません(民335Ⅰ)。
- 滞納者がその所有マンションを第三者へ賃貸している場合には、建物内に滞納者の所有動産がないことは明らかですので、その旨を証明することで動産執行を省略できることもあります。具体的には陳述書(「賃貸にしているため債務者財産はない」など)を提出します。
| 民法335条(一般の先取特権の効力) | |
|
|

先取特権の実行による競売申立(配当要求)
| 場合 | とるべき手続 |
| 先行する競売がないとき | 先取特権の実行による競売開始申立て |
| 先行する競売があるとき | 先取特権による配当要求 |
当事者の証明
- 法人登記された管理組合の場合:管理組合の登記事項証明書
- 法人登記のない管理組合の場合:代表者に関する事項についての管理規約+代表者・管理者を選任した総会議事録
先取特権を有することを証明
先取特権の存在を証する文書(民事執行法181Ⅳ)として次の書面を提出します。
- 毎月の管理費等についての定めがある管理規約or管理費等について決議した総会議事録【1】
- 滞納管理費等の明細書等
【1】管理費等の額が規約や集会決議で決まっていない場合には、申立に先立ち、具体的な金額を確認する決議をする必要があります。
建物に備付けた動産に対する担保権の実行では請求額に足りないことの証明
- 動産執行を先にしなければならないのは、前述のとおりです。
- 滞納者がその所有マンションを第三者へ賃貸している場合には、建物内に滞納者の所有動産がないことは明らかですので、その旨を証明することで動産執行を省略できることもあります。具体的には陳述書(「賃貸にしているため債務者財産はない」など)を提出します。
予納金
- 競売開始申立ての場合:不動産競売同様高額の予納金を要します。予納金は、売却代金の中から優先的に返還されますが、管理組合が一時的に立替える必要があります。
- 配当要求の場合:予納金不要。少額の印紙、切手のみ。
8条に基づく特定承継人への請求
| 区分所有法第8条(特定承継人の責任) | |
|
|
| 区分所有法第7条(先取特権) | |
|
|
「特定承継人」とは、前の所有者から購入した人(買主)という意味です。区分建物以外の物の売買で買主が売主の債務を引き継ぐということはありません。ところが、区分建物の場合の滞納管理費等については、特定承継人に対しても請求することができます(区分所有法8)。
そして、強制競売による買受人も、この特定承継人に含まれます(稲本洋之助、鎌野邦樹著/コンメンタールマンション区分所有法[第2版]/日本評論社/2004/62p)。
なお、相続人などの「一般承継人」に対して請求できるのは、当然です。
59条競売
|
区分所有法第59条(区分所有権の競売の請求) |
|
|
|
いきなり競売申立ができる訳ではなく、競売請求訴訟で勝訴する必要があります。
59条競売の特徴は、次のとおりです。
競売請求訴訟のハードルが高い
下記二つの要件を主張・立証する必要があります。
- 共同生活に著しい障害【1】
- 他の方法では他の区分所有者の共同生活の維持が困難【2】
【1】相当長期の滞納、督促無視・・・などです。
【2】他の強制執行が不奏功、今後の支払い可能性がない・・・などですが、裁判例では競売請求までの経緯などによって判断が分かれています。
- 認めなかった裁判例(東京地裁H18.6.27判決、東京高裁H18.11.1判決)。
- 認めた裁判例(東京地裁H17.5.13判決、東京地裁H24.9.5判決)。
無剰余取消しがなされることがありません。
競売請求訴訟で勝訴さえすれば、無剰余取消しされることがないとされていますので、(特定承継人への請求を含めて)回収可能性は高くなります。
59条競売による回収の流れ
滞納者への「弁明の機会」を設ける

管理組合総会の特別決議による承認
区分所有者と議決権総数の3/4以上の賛成

競売請求訴訟

競売請求訴訟で勝訴

競売開始申立て
司法書士の報酬・費用
滞納管理費の請求は、
- 滞納者のマンションに抵当権は設定されているか?
- 規約が整備されているか?
- 総会はキッチリと運営され、議事録が残されているか?
- 滞納者は入居中か?行方不明か?賃貸しているか?
- 滞納者は存命か死去しているか?
などによって、必要な手続が全く異なります。
まずは、30分ごと5,500円の司法書士法律相談をお受けください。
通常1時間程度で、事情を聞き取り、方針をご提示できると思います。
事情を良くお伺いしたうえ、見積書を提示いたします。
事案によっては、マンション管理に強い弁護士を紹介することもございます。
お客様の声

マンションの区分所有者がお亡くなりになり、近しい相続人もいなかったために、相続人が膨大な数に上りましたが、訴訟提起後、相手方相続人と協議のうえ、解決できた事例です。
訴訟前に円満解決できれば良かったのですが、単に滞納額の支払いを命じる判決をとっただけでは、将来も滞納が発生し続けることが確実でした。そこで、何としても相続人には、相続登記をしたうえで専有部分を売却してもらう必要がありました。
最終的には、滞納管理費、滞納修繕積立金、訴訟費用を含めて満額回収できました。
皆様にお喜びいただけて良かったです。
人気の関連ページ
- 不動産賃貸借トラブル
-
- 家賃滞納による建物明渡請求
- 借地に関する契約
- 借地上の建物を賃貸借するときに注意すべき事項
- 短期賃貸借保護制度から明渡猶予制度へ
- 借家に関する契約
- 不動産賃貸借における関西方式・関東方式
- 居抜き物件を借りたときのトラブル
- 原状回復に関するトラブル
- 敷引特約の有効性
- 賃貸借契約における更新料条項の有効性、更新料不払いの効果、法定更新との関係ほか後日もめないための具体策
- 賃貸借契約における遅延損害金14.6%の定め、使用損害金を賃料倍額とする定めは有効か
- 不動産売買トラブル
-
- 地中埋設物に関するトラブル
- 不動産建築トラブル
- マンションのトラブル
-
- 区分建物(マンション)とは何か?!知らないと分からない区分所有法の特殊な規定ほか
- マンション管理規約の設定、変更または廃止の方法
- マンション共用部分に関する訴訟
- マンションの滞納管理費・修繕費・積立金の回収
- マンション義務違反者への対応
- マンション復旧、立替に関する訴訟
- マンション管理組合総会決議無効・不存在確認の訴え
- マンション管理者の解任請求
- マンション会計帳簿等閲覧謄写請求
- マンション改修工事への協力請求
- 連棟建物(長屋、二戸一、三戸一)の切り離しトラブル
- マンションや二戸一建物における水漏れトラブル
- 隣近所のトラブル
-
- 隣近所とのトラブル解決
- 隣近所とのトラブルの種類
- 雨水など通水トラブル
- 崖地の擁壁・石垣の補修に関するトラブル【図解】
- 騒音トラブル
- 境界トラブル(筆界と所有権界)
- 境界トラブル(筆界特定制度)
- 境界トラブル(境界確定訴訟)
- 境界トラブル(所有権確認訴訟)
- 私道の通行権をめぐるトラブル
- 共有私道の工事をめぐるトラブル
- 私橋の通行権をめぐるトラブル
- 猫への餌付け被害の回復
- ハト・スズメなど鳥への餌付けによる被害の回復
- 敷地への放置車両の撤去