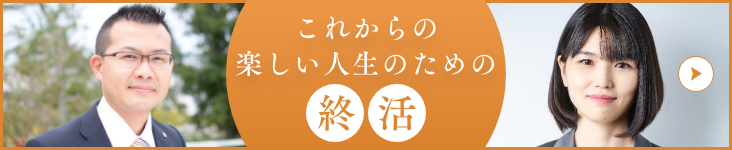特別受益(の持戻し)

特別受益は、相続人間の不公平を是正するための制度です。
「特別受益」とは、被相続人から生前贈与や遺言による贈与を受けている場合をいいます(民903.904)。そのまま法定相続分で分割すると不平等になるので、計算上、相続財産に戻す処理をすることがあり、これを「特別受益の持戻し」といいます。
特別受益の主張は、次のようなときに行ないます。
- 遺産分割調停
- 遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)
- 相手方の寄与分主張に対抗して
| もくじ | |
|
特別受益者の範囲
| 事例 | 結果 |
| 被代襲者が贈与を受けた場合 | 代襲者の特別受益となるか否か争いあり |
|
被代襲者が受けた利益が、一身専属的な場合 例)養育費 |
代襲者の特別受益とならない。 |
|
代襲者が推定相続人となった後(代襲原因発生後)、贈与を受けた場合 |
特別受益となる。 |
|
代襲者が推定相続人となる前(代襲原因発生前)、贈与を受けた場合 |
特別受益とならない(通説)。 |
|
受贈後に推定相続人となった場合 例)養子縁組前に養子となる者に贈与 例)婚姻前に配偶者となる者に贈与 |
特別受益となる。 |
|
包括受遺者が贈与も受けていた場合 |
特別受益とならない。 |
|
相続人の配偶者が贈与を受けていた場合 |
原則:特別受益とならない。 例外:相続人に対する贈与と同視しうる場合は特別受益となる。 |
特別受益の種類
| 種類 | 結果 |
| 婚姻、養子縁組のための贈与 | 特別受益に該当する場合もあるが、各相続人がほぼ平等に贈与されていた場合、持戻しをしない。 |
| 学資 | 特別受益に該当する場合もあるが、各相続人がほぼ平等に贈与されていた場合、持戻しをしない。 |
| 使用借権【1】 |
➊被相続人が同居していなかった場合 相続人は、独立の占有者として、借地権相当額を特別受益として扱う。 |
|
❷被相続人が同居していた場合 相続人は、占有補助者として、借地権相当額を特別受益として扱わない。 |
|
| 生命保険金 |
原則:特別受益ではない。 例外:保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる。(最判H16.10.29) |
| 死亡退職金 |
➊支給根拠が法律・条例・労働協約・就業規則などにあり、特定の遺族に対する生活保障が明確になっている場合、 特別受益といえない。 |
|
❷功労報酬的な色彩が強い場合 特別受益となる可能性がある。 |
|
| 遺族給付 |
原則:特別受益ではない。 ∵特定の遺族に対する生活保障 |
| 財産分与として受領した財産 |
争いあり |
| 相続人たる夫の債務を肩代わりして、求償しなかった |
特別受益になりうる(高松家裁丸亀支部H3.11.19) |
| 1回当たりの金額は高額ではないものの、長期に渡ってなされた結果、その合計額が多額になった贈与 |
東京家裁平成21年1月30日審判(家月62巻9号62頁)【2】 |
【1】相続人が被相続人の土地の上に、自己名義の建物を建築して無償で使用している場合
【2】東京家裁平成21年1月30日審判(家月62巻9号62頁)事件名:遺産分割申立事件、寄与分を定める処分申立事件。
この事件では、申立人は、下記➊~➌が相手方の特別受益に該当すると主張したが、審判では次の理由について、大幅に特別受益該当額を大幅に減額又は否定した。
なお、抗告審である東京高裁平成21年4月28日決定も、東京家裁の考え方を支持している。
| ➊ | 申立人主張 |
H8-H11までに727万余の送金を受けた。 H11-H16までに国民年金保険料、国民健康保険料99万余の支払いを受けた。 H14簡易保険満期金200万円をだまし取った。 S53-S60までに借入をし残は477万円余。 H4-H6までに227万円余の送金を受けた。 合計1762万円余の贈与を受けた。 |
| 審判 |
◆遺産総額や被相続人の収入状況からすると,相続人である相手方が被相続人から2年余にわたり送金を受けていた毎月2万円から25万円のうち,一月10万円に満たない送金は親族間の扶養的金銭援助にとどまり,これを超える送金のみが生計の資本としての贈与と認められる。(審判の要約は、WestlawJapan) 相手方の特別受益と認められたのは628万円余。 |
|
| ➋ | 申立人主張 | 相手方は被相続人に相手方の長男を3歳から高校卒業まで養育させてきたが、この間、少なくとも生活保護基準額及び教育費の合計702万円余を負担させた。 |
| 審判 | ◆被相続人が,相続人である相手方の子を3歳のころから高校卒業までの約15年間現実に養育し,その費用を負担したことは,被相続人から相手方に対する生計の資本としての贈与とは認められない。(審判の要約は、WestlawJapan) | |
| ➌ | 申立人主張 | 被相続人が一人株主かつ代表取締役の会社から、相手方は勤務していないのに2617万円余の給与を受けた。 |
| 審判 | 仮に相手方が稼働実態なくしてa株式会社から上記給与が支払われているとしても,同社から相手方に対する贈与であって,被相続人からの贈与とはいえない。このことは,同社が被相続人の一人会社であったとしても,会社経理との誤認混同など経済的に極めて密着した関係があったとは認めるに足りる証拠はないので,一人会社というだけで被相続人からの贈与と認めることはできない。 |
特別受益の計算方法
特別受益を受けた人の相続分の計算
(相続財産額+特別受益額)×法定相続分ー特別受益額=相続分
特別受益を受けていない人の相続分の計算
(相続財産額+特別受益額)×法定相続分=相続分
「相続財産額」は、遺産分割協議を行う時点の金額で計算します。
「特別受益額」は、相続開始の時点の金額で計算します。
あまり変わらないように思われるでしょうが、相続開始から相当期間が経過してから遺産分割協議を行うこともありますので、その際にはご注意ください。
相手方の特別受益を認定してもらうためには、遺産分割調停中に、別途申立てが必要か?!
最高裁H7.3.7判決
特定財産が特別受益財産であることの確認を求める訴えを、不適法として却下しました。
▼
特別受益は、いわゆる「遺産分割の前提問題」ではないので、遺産分割調停中に、別途申立ては不要です。
以下、同最判を少し長めに抜粋します。
|
民法903条1項は・・・被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に特別受益財産の価額を加えたものを具体的な相続分を算定する上で相続財産とみなすこととしたものであって、これにより、特別受益財産の遺贈又は贈与を受けた共同相続人に特別受益財産を相続財産に持ち戻すべき義務が生ずるものでもなく、また、特別受益財産が相続財産に含まれることになるものでもない。そうすると、ある財産が特別受益財産に当たることの確認を求める訴えは、現在の権利又は法律関係の確認を求めるものということはできない。
過去の法律関係であっても、それを確定することが現在の法律上の紛争の直接かつ抜本的な解決のために最も適切かつ必要と認められる場合には、その存否の確認を求める訴えは確認の利益があるものとして許容される(最高裁昭和四四年(オ)- 1 -第七一九号同四七年一一月九日第一小法廷判決・民集二六巻九号一五一三頁参照)が、ある財産が特別受益財産に当たるかどうかの確定は、具体的な相続分又は遺留分を算定する過程において必要とされる事項にすぎず、しかも、ある財産が特別受益財産に当たることが確定しても、その価額、被相続人が相続開始の時において有した財産の全範囲及びその価額等が定まらなければ、具体的な相続分又は遺留分が定まることはないから、右の点を確認することが、相続分又は遺留分をめぐる紛争を直接かつ抜本的に解決することにはならない。また、ある財産が特別受益財産に当たるかどうかは、遺産分割申立事件、遺留分減殺請求に関する訴訟など具体的な相続分又は遺留分の確定を必要とする審判事件又は訴訟事件における前提問題として審理判断されるのであり、右のような事件を離れて、その点のみを別個独立に判決によって確認する必要もない。 以上によれば、特定の財産が特別受益財産であることの確認を求める訴えは、確認の利益を欠くものとして不適法である。本件訴えを却下すべきものとした原審の判断は、結論において是認することができる。 |