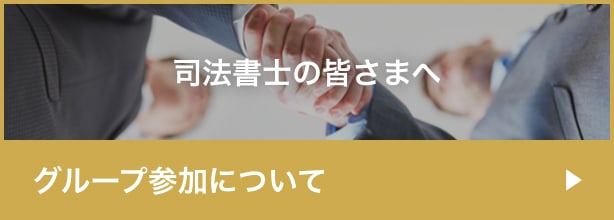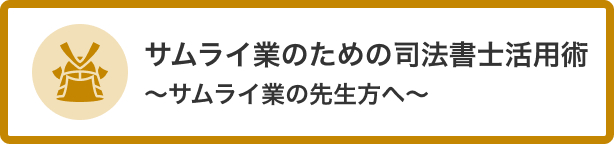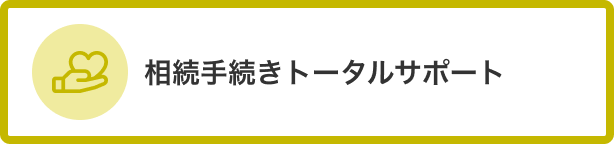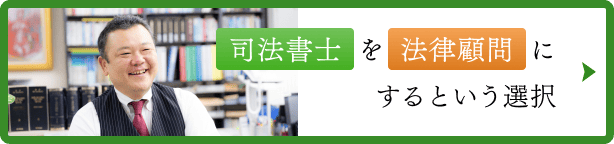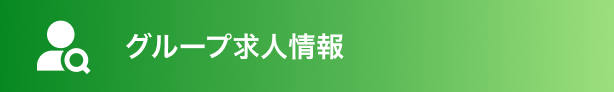相続権を侵害されたときには、相続回復請求を行うことができますが、実務上は、次のようになっています。
- △ 請求原因としては、あまり使われていません(つまり、普通は「相続権を侵害しているから、相続回復請求権に基づいて、金○円を支払え」や「相続権を侵害しているから、相続回復請求権に基づいて、○○不動産を引き渡せ」などとは使いません。)
- 〇 消滅時効の抗弁として、使われているケースが多いです(つまり「他の相続人によるこの請求は、相続回復請求権だから消滅時効にかかっている」というように使います。)。
| もくじ | |
|
相続回復請求権(民法第884条)
条文から分かること/分からないこと。
| 民法884条(相続回復請求権) | |
| 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。 | |
民法上、相続回復請求権について規定した条文はこの一条だけです。
相続回復請求権の行使期限を定めただけの条文、そして、たった一条しかない条文からは、
- 相続回復請求権の存在意義や内容、
- 行使するための要件、
- 物権的請求権との関係
は分かりません。
物権的請求権の存在から導かれる仮説
相続が開始すると、遺産は「相続人全員による準共有」となります。
ですから・・・
「他人」が遺産を占有している場合は、「共有持分権に基づき」妨害排除請求をすれば足ります。
「他の相続人」が遺産を占有している場合は、「共有持分権に基づき」遺産分割協議を求めれば良いのです。
これら妨害排除請求権や、遺産分割を求める権利は、所有権に基づく権利ですので「物権的請求権」といいます。
そして本来、物権的請求権は、消滅時効にかかりません。
本来、消滅時効にかからない権利を消滅時効により消滅させようというのが、民法884条の意義なのだと思われます。
現実にも、真正な相続人と表見相続人との争いではなく、共同相続人という真正な相続人同士の遺産分割の争いの中で、法定相続分の一部を侵害されている共同相続人が他の共同相続人に対して共有持分に基づく抹消登記請求や移転登記手続を求めた場合に、自己の法定相続分を超えて遺産を占有する者から相続回復請求権の時効消滅が主張するケースが多いのです。
相続回復請求権の制度趣旨(判例より)
- 「民法884条の相続回復請求の制度は、いわゆる表見相続人が真正相続人の相続権を否定し相続の目的たる権利を侵害している場合に、真正相続人が自己の相続権を主張して表見相続人に対し侵害の排除を請求することにより、真正相続人に相続権を回復させようとするものである。」(最大判昭和53年12月20日民集32巻9号1674頁)
- 「相続回復請求権について消滅時効を定めたのは、表見相続人の外見上相続により相続財産を取得したような事実状態が生じたのち相当年月を経てからこの事実状態を覆滅して真正相続人に権利を回復させることにより当事者又は第三者の権利義務関係に混乱を生じさせることのないよう相続権の帰属及びこれに伴う法律関係を早期にかつ終局的に確定させるという趣旨に出たものである。」(最大判昭和53年12月20日民集32巻9号1674頁)
相続回復請求権の適用範囲(判例より)
- 「真正な相続人」が、相続する資格がないのに相続した「表見相続人」に対して、行使できる。
- 共同相続人間でも適用される。すなわち「共同相続人のうちの一人又は数人が、相続財産のうち自己の本来の相続持分をこえる部分について、当該部分の表見相続人として当該部分の真正共同相続人の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分であると主張してこれを占有管理し、真正共同相続人の相続権を侵害している場合につき、民法884条の規定の適用」される(最大判昭和53年12月20日民集32巻9号1674頁)
相続回復請求権の行使要件
訴訟物:個々の財産の「所有権に基づく妨害排除請求」「所有権に基づく返還請求」などとなる。
要件事実(所有権に基づく妨害排除請求などと同じ)
- 相続人が当該財産の所有
- 被相続人の死亡
- 真正相続人が相続人であるための被相続人との身分関係及び同時存在
- 表見相続人が1の財産を占有していること又は1の財産につき表見相続人名義の所有権登記の存在
(参照:岡口基一(著)『要件事実マニュアル 第5版 第2巻 民法2』ぎょうせい/2016/639頁)
相続回復請求権の消滅時効の要件(判例より)
表見相続人が、真正相続人に対して、相続回復請求権の消滅時効を主張するには、次の要件を全て充たす必要があります。
抗弁(相続回復請求権の短期消滅時効)の要件事実
- 真正相続人が、表見相続人による占有又は登記を知ったこと及びその時期
- 1から5年経過(民法884)
- 表見相続人【1】が、占有開始又は登記の時に、自分が相続人でないことを知らなかったこと「善意」かつ、知らなかったことに「合理的理由」があったこと【2】
- 時効の援用
抗弁(相続回復請求権の長期消滅時効)の要件事実
- 相続開始から20年経過(民法884)【3】
- 表見相続人【1】が、占有開始又は登記の時に、自分が相続人でないことを知らなかった「善意」、知らなかったことに合理的理由があった「合理的事由の存在」【2】
- 時効の援用
【1】表見相続人からの転得者
表見相続人が「善意かつ合理的事由の存在」がないために、真正相続人に相続回復請求権を主張できないときは、表見相続人から不動産を譲り受けた第三者も真正相続人に対して、相続回復請求権の消滅時効を援用できない(最判平成7年12月5日裁判集民177号341頁)。
【2】最大判昭和53年12月20日、最判昭和54年7月10日、最判平成7年12月5日など
表見相続人が立証責任を負うことにつき最判平成11年7月19日
【3】数次相続が行われたときの相続回復請求権の20年長期消滅時効の起算点は、当初の被相続人死亡の時である(最判昭和39年2月27日民集18巻2号383頁、最判昭和40年5月28日裁判集民79号213頁、最判昭和41年4月26日裁判集民83号407頁)。
取得時効との関係(判例より)
表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前でも、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができる(最判令和6年3月19日)。
| 最判令和6年3月19日民集78巻1号63頁 | |
|
登場人物
事案の概要
|
|
|
抜粋 「民法884条所定の相続回復請求権の消滅時効と同法162条所定の所有権の取得時効とは要件及び効果を異にする別個の制度であって、特別法と一般法の関係にあるとは解されない。また、民法その他の法令において、相続回復請求の相手方である表見相続人が、上記消滅時効が完成する前に、相続回復請求権を有する真正相続人の相続した財産の所有権を時効により取得することが妨げられる旨を定めた規定は存しない。 そして、民法884条が相続回復請求権について消滅時効を定めた趣旨は、相続権の帰属及びこれに伴う法律関係を早期かつ終局的に確定させることにあるところ、上記表見相続人が同法162条所定の時効取得の要件を満たしたにもかかわらず、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成していないことにより、当該真正相続人の相続した財産の所有権を時効により取得することが妨げられると解することは、上記の趣旨に整合しないものというべきである。 以上によれば、上記表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるものと解するのが相当である。このことは、包括受遺者が相続回復請求権を有する場合であっても異なるものではない。」 したがって、養子は、本件不動産に係る甥Y1及びAの各共有持分権を時効により取得することができる。 |
|
判例のご紹介
相続回復請求権の時効を援用できる者に関する判例をご紹介します。
|
事 例 |
乙の相続権を侵害し、乙に訴えられた 【甲の属性】 |
甲が、乙の請求を相続回復請求権であるとして その消滅時効を援用できるか否か |
| 1 | 悪意or有過失の「他の共同相続人」 | 援用不可(最大判昭和53年12月20日) |
|
2 |
悪意or有過失の「他の共同相続人」から 譲渡を受けた転得者 |
援用不可(最判平成7年12月5日) |
| 3 | 善意&無過失の「他の共同相続人」 | 援用可能(最判昭和54年7月10日) |
<事例1、事例3は下図のとおり>
| 相続人乙 |
→➊甲が乙の相続権を侵害→ |
他の相続人甲 |
|
→➋乙が甲に返せ→ |
||
|
←➌相続回復請求権だから時効だと主張できるか?← |
<事例2は下図のとおり>
| 相続人乙 |
→➊甲が乙の相続権を侵害→ |
他の相続人甲 |
→➋譲渡→ |
甲からの 転得者 |
|
→➌乙が甲に返せ→ |
||||
|
←➍相続回復請求権だから時効だと主張できるか?← |
||||
最大判昭和53年12月20日
| 最大判昭和53年12月20日民集32巻9号1674頁 | |
|
要旨 ◆共同相続人の一人甲が、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分につき他の共同相続人乙の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分に属すると称してこれを占有管理し、乙の相続権を侵害しているため、乙が右侵害の排除を求める場合には、民法884条の適用があるが、甲においてその部分が乙の持分に属することを知つているとき、又はその部分につき甲に相続による持分があると信ぜられるべき合理的な事由がないときには、同条の適用が排除される。 (要旨は、Westlaw Japanによる。) |
|
|
抜粋 「民法八八四条の相続回復請求の制度は、いわゆる表見相続人が真正相続人の相続権を否定し相続の目的たる権利を侵害している場合に、真正相続人が自己の相続権を主張して表見相続人に対し侵害の排除を請求することにより、真正相続人に相続権を回復させようとするものである。そして、同条が相続回復請求権について消滅時効を定めたのは、表見相続人の外見上相続により相続財産を取得したような事実状態が生じたのち相当年月を経てからこの事実状態を覆滅して真正相続人に権利を回復させることにより当事者又は第三者の権利義務関係に混乱を生じさせることのないよう相続権の帰属及びこれに伴う法律関係を早期にかつ終局的に確定させるという趣旨に出たものである。」 「右法条が共同相続人相互間における相続権の帰属に関する争いの場合についても適用されるべきかどうかについて、検討する。(中略)共同相続人のうちの一人又は数人が、相続財産のうち自己の本来の相続持分をこえる部分について、当該部分の表見相続人として当該部分の真正共同相続人の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分であると主張してこれを占有管理し、真正共同相続人の相続権を侵害している場合につき、民法八八四条の規定の適用をとくに否定すべき理由はない」 「自ら相続人でないことを知りながら相続人であると称し、又にその者に相続権があると信ぜられるべき合理的な事由があるわけではないにもかかわらず自ら相続人でみると称し、相続財産を占有管理することによりこれを侵害している者は、本来、相続回復請求制度が対象として考えている者にはあたらない。」 「共同相続人のうちの一人若しくは数人が、他に共同相続人がいること、ひいて相続財産のうちその一人若しくは数人の本来の持分をこえる部分が他の共同相続人の持分に属するものであることを知りながらその部分もまた自己の持分に属するものであると称し、又はその部分についてその者に相続による持分があるものと信ぜられるべき合理的な事由(たとえば、戸籍上はその者が唯一の相続人であり、かつ、他人の戸籍に記載された共同相続人のいることが分明でないことなど)があるわけではないにもかかわらずその部分もまた自己の持分に属するものであると称し、これを占有管理している場合は、もともと相続回復請求制度の適用が予定されている場合にはあたらず、したがつて、その一人又は数人は右のように相続権を侵害されている他の共同相続人からの侵害の排除の請求に対し相続回復請求権の時効を援用してこれを拒むことができるものではない。」 |
|
実際に時効援用を認めた判例
| 最判昭和54年7月10日 | |
|
一 旧民法下の遺産相続による共同相続人の一人甲が、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分について他の共同相続人乙の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分に属すると称してこれを占有管理し、乙の相続権を侵害しているため、乙が右侵害の排除を求める場合には、相続回復請求権の規定の適用があるが、甲においてその部分が乙の持分に属することを知つているとき、又はその部分につき甲に相続による持分があると信ぜられるべき合理的な事由がないときは、同規定の適用が排除される。
二 旧民法下の遺産相続による共同相続人の一人乙女が遺産分割前に他の共同相続人甲男を家督相続人に指定して隠居したが、右隠居時に乙に胎児がいたことにより右指定が無効であり、乙が遺産相続権を失わないため、甲において相続財産のうち乙の相続部分もまた右指定により自己に帰属したとして同部分に対し占有管理を続けたことが乙の遺産相続権に対する侵害となる場合においても、胎児が生後まもなく死亡したため、甲において右指定の無効を知りえず、かつ、その無効を知りえなかつたことが客観的にも無理からぬものであるときは、乙の甲に対する右侵害排除を求める請求について、相続回復請求権の規定の適用がある。 (要旨は、Westlaw Japanによる。) |
|
悪意有過失の相続人からの転得者(第三者)は、相続回復請求権の消滅時効を援用できない。
| 最判平成7年12月5日 | |
|
共同相続の場合において相続回復請求制度の問題として扱うかどうかを決する右のような悪意又は合理的事由の存否は、甲から相続財産を譲り受けた第三者がいるときであつても、甲について判断すべきであるから、相続財産である不動産について単独名義で相続の登記を経由した共同相続人の一人甲が、甲の本来の相続持分を超える部分が他の相続人に属することを知っていたか、又は右部分を含めて甲が単独相続をしたと信ずるにつき合理的な事由がないために、他の共同相続人に対して相続回復請求権の消滅時効を援用することができない場合には、甲から右不動産を譲り受けた第三者も右時効を援用することはできないというべきである。
(要旨は、Westlaw Japanによる。) |
|
人気の関連ページ
 企業・事業者向けサービス
企業・事業者向けサービス
 トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)
トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)





















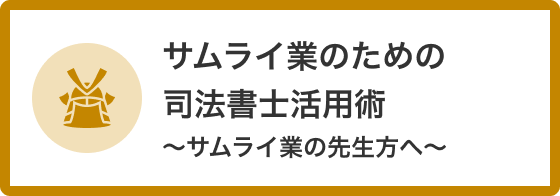
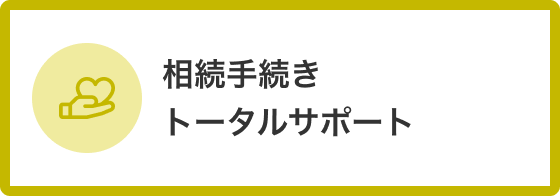
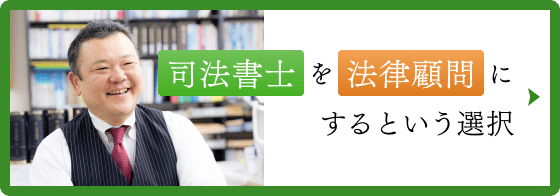

 個人向けサービス
個人向けサービス