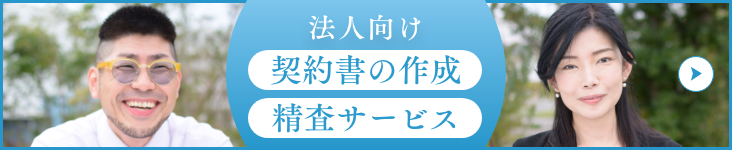- 起業支援(会社団体設立運営支援)
- 司法書士による顧問契約のご紹介
- 従業員支援プログラム(EAP)
- スタートアップ(ベンチャー)支援/株式上場(IPO)支援
- 法務部門支援
- 企業法務の種類と担当専門家
- コンプライアンス経営を支援
- ビジネス(事業目的)の適法性の調査方法(グレーゾーン解消制度、ノーアクションレター制度、新技術等実証制度、新事業特例制度)
- 【図解】不正競争防止法
- 【図解】景表法(不当景品類及び不当表示防止法)➊不当表示禁止
- ステルス・マーケティング規制(ステマ規制、景表法関連)
- 【図解】独禁法・下請法
- 【図解】フリーランス保護法
- 【インサイダー取引規制】上場株式を売買する場合のほか、上場企業から受注する場合にも要注意
- 【図解】資金決済に関する法律(資金決済法)➊前払式支払手段(前払式証票)
- 【図解】資金決済に関する法律(資金決済法)➋資金移動業
- 【図解】資金決済に関する法律(資金決済法)➌電子決済手段等取引業、暗号資産交換業、為替取引分析業、資金清算業
- 【図解】個人情報保護法➊個人情報の種類
- 【図解】個人情報保護法➋個人情報種類ごとの規制
- 【図解】個人情報保護法➌第三者提供・委託・共同利用の区別
- 内部通報者を保護する公益通報者保護法
- セミナー参加者の募集をウェブ上で行なうときの注意点
- DMするときに気をつけるべきオプトイン(特定電子メール法)
- 会社役員間の利益相反取引「見分け方」と「具体的な対応方法」
- 手形の基礎知識
- 与信調査、与信判断、与信管理
- 取引先等の信用チェック(決算書編)
- 取引先等の信用チェック(登記簿編)
- 契約書作成・精査
- 契約締結方法ごとのリスクと改善策
- 電子契約によるリスクと改善策
- 公正証書や書面など様式が決まっている契約の類型
- 確定日付の効力と要件(契約書には確定日付があった方が良いのか?)
- 法務部員が知っておくべき「二段の推定」とは?!
- 契約の成立時期【申込と承諾】民法の原則と商法・電子消費者契約法による例外
- 印紙税法の基本と間違いやすいポイント
- 契約不適合責任【図解民法改正】
- 約款(規約)と契約の違い/ 約款と定型約款の違い【図解民法改正】
- 契約書における「損害賠償」の定め方
- 業務委託契約とは何か?事業者が理解すべき業務委託2つの形態(請負型と委任型)
- 販売提携契約:提携の中身は売買・仲介・代理・取次のどれでしょうか?また、販売店・特約店・代理店・取次店・協力店の違いは何でしょうか?
- 事業者が理解しておくべき「リース契約」
- 根保証契約【図解民法改正】2020.3.31以前締結契約
- 根保証契約【図解民法改正】2020.4.1以降締結契約
- 債務承認弁済契約書に収入印紙は必要か?!
- 領収書(受取証書)の交付を求められたときの対応
- 消滅時効・時効管理【図解民法改正】
- 消滅時効が完成していると思っていた債務が実は時効完成していないケース~民間同士の貸借で「期限の利益喪失約款がない場合」や「約款があっても一括請求を受けていない場合」にご注意
- 企業秘密(営業秘密)の保護
- 秘密保持契約書NDA
- 個人情報の保護Ⅰプライバシーポリシー・個人情報保護方針
- 会社が書類の提出を求められたときの対応(はじめに)
- 定款提出を求められたときの対応◎当社の定款はどこにあるのか?
- 定款提出を求められたときの対応➊定款見直し、紛失定款再現サービス
- 定款提出を求められたときの対応➋定款再入力&WORDデータ化サービス
- 定款提出を求められたときの対応➌定款データ保管サービス
- 司法書士に定款変更を依頼したのに、手元の定款原本が変更されていないときの対応
- 帳簿や決算書の閲覧を求められたときの対応
- 株主名簿管理の重要性
- 株主名簿の提出を求められたときの対応
- 特殊事情(株主総会欠席、議案への反対、相続、株主権行使代表者、自己株など)があるときの株主リストの記載方法
- 株式譲渡承認請求への対応
- 自己株式取得(総株主から買取)の手続と注意点
- 自己株式取得(特定株主から買取)の手続と注意点
- 自己株式取得の財源規制(会社が株主から自社株を買い取るときの規制)
- 株式への質権設定を請求された会社の対応
- 株式を質入れする株主(会社)側のリスク
- 実質的支配者リスト(BOリスト)
- 株券の善意取得、株券の喪失登録
- 株式の相続・株主権行使代表者
- 単独株主権・少数株主権まとめ一覧
- 分散株主整理
- 株式持ち合い(相互保有株式)により制限されること/株式持ち合い解消のルール
- 上場会社の株式事務(株式等振替制度)
- 剰余金の配当に関する規制
- 労働に関する法律一覧【図解】
- 労働時間の原則と例外(時間外労働協定〔36協定〕、変形労働時間制、フレックスタイム制、事業場外みなし労働時間制、裁量労働制)
- 退職金・退職慰労金・弔慰金
- 役員退職慰労金の決定方法
- 知的財産権(著作権・実用新案権・特許権・意匠権・商標権など)
- 内部統制システム(コーポレートガバナンス)構築支援
- 株主総会・取締役会など運営支援
- 組織再編(会社分割・合併・組織変更・株式移転など)
- 会社・法人の事業承継
- M&A・ジョイントベンチャー(合弁事業)
- 会社や法人の登記
- 医療法人その他医療機関の登記
- 企業・事業者の資産管理・運用
- 会社の再生・倒産(負債が大きい会社)
- 会社の通常解散(負債が少ない会社の休業・廃業・解散)
- セミナー講師
約款(規約)と契約の違い/約款と定型約款の違い【図解・民法改正】

「約款」という言葉を聞いたことのある方も多いと思います。
JRの運送約款、銀行の預金約款など、小さな文字でビッシリと記載されたアレです。
意外なことに民法には「約款」が何であるのか定義がされていませんでしたが、2020(令和2)年4月1日施行された改正民法(民法548条の2~548条の4)に「定型約款」として規定されました。
約款を準備する側は、約款について正確に理解し、約款が顧客との契約の一部となるように工夫しなければなりません。
|
1.「約款」と「契約」の違い 2.「約款」を作成しておくメリット 3.「定型約款」と「それ以外の約款」の違い 4.「定型約款」のメリット 5.定型約款と認められるための要件 6.相手方の同意なき定型約款の変更が認められる(効力発生する)ための要件 7.相手方の同意をとる定型約款の変更 8.所要時間 |
「約款」と「契約」の違い
「約款」と似た言葉に「規約」というのもありますよね。
「規約」と「約款」は、ほぼ同じ意味と考えていただいて結構です。
| 約款(規約) | 契約 | |
| 当事者 |
|
|
| 内容 |
|
|
| 締結前の個別交渉 |
|
|
| 締結後の変更 |
|
|
「約款」を作成しておくメリット
1.クレームが発生したときの話し合いの土俵になる。
| 約款がないとき |
どう解決していいの?! 当社・お客様どっちが悪いの?! とアタフタしてしまう。 |
| 約款があるとき |
「約款第〇条の禁止事項をご覧ください」でOK |
2.法律の任意規定が不利に働かないようにしておく。
対消費者の約款の場合には、消費者の利益を一方的に害する全面的免責条項は無効になります(消費者契約法)ので、注意が必要です。
3.約款の定めが法律上有効か無効かは裁判次第です。それまで一応有効なルールとなり得るし、消費者は提訴しないかもしれない。
消費者やお客様にとって余りに不利な約款を定めてしまうと、ネット上での炎上や集団訴訟のリスクが生じます。合理的でユーザーに共感してもらえる内容を定める必要があります。
「定型約款」と「それ以外の約款」の違い
改正民法で「定型約款」が規定されるまでは、「約款」に関する規制・解釈は、学説・裁判例・民法の一般条項(公序良俗違反は無効など)によって行なわれてきました。
ただし、世の中にある多数の「約款」と「民法の定型約款」は同じではありません。
民法は「約款」が「定型約款」となるための要件と効果を規定しているのです。
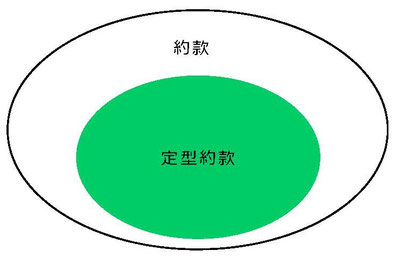
| 約款の類型 | |||
| 定型約款 | その他の約款 | ||
| 約款の内容に対する相手方の認識 | 不要 | 不要との見解が有力 | |
|
定型約款が契約 内容となるため の要件
|
みなし合意 | 適用 | 不適用 |
| 不当条項 |
適用
|
不適用(ただし、信義則一般の適用あり) | |
| 表示義務 | 適用 | 不適用 | |
| 表示義務違反によるみなし合意の否定 | 適用 | 不適用 | |
| 定型約款の変更が認められるための要件 | 適用 | 不適用 | |
(表は、「Q&A民法改正の要点・企業契約の新法対応50のツボ/長島・大野・常松法律事務所・松尾博憲編著/日本経済新聞出版社」55pより引用)
定型約款のメリット
貴社の約款が、定型約款に該当すれば、次のようなメリットがあります。
1.顧客ごとに契約内容の交渉をする手間が省ける。
2.(顧客が定型約款の内容を読んでいなくても)定型約款が契約の内容となりえる。
3.(顧客が定型約款の変更に同意していないくても)定型約款の変更が認められる。
定型約款による契約は、長期にわたることが多く、長期の間には契約相手が所在不明になることもありえます。定型約款を変更をするたびに、(場合によっては相手方を探し出して)相手方から同意を得なくてはならないとすると、相当のコストを要することとなってしまいます。
また同意を得られてた相手と、得られなかった相手を格別に扱うのも、相当面倒ですし、定型取引の画一性が失われてしまいます。
定型約款と認められるための要件
以下、7つの要件をすべて充す必要があります。
要件を充していれば、「事業者間契約における約款」も「定型約款」に該当する可能性はあります。
要件❶「定型取引」において用いられるもの
|
定型取引 とは
|
ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行なう取引 |
例 |
相手方の個性に着目せず行なわれる取引。 〇生命保険約款 〇オートローン約款 ×労働契約の雛形 ×就業規則 |
|
| かつ | ||||
| 内容が画一的であることが当事者「双方」にとって合理的 |
例 |
内容が画一的であることの理由が交渉力格差にあってはならない。 【事業者間取引に用いる約款の場合】 ×銀行取引約定書 ×コンビニのフランチャイズ契約 〇預金約款 【対消費者に用いる約款の場合】 〇住宅ローン約款 |
要件❷契約の内容とすることを目的として準備した条項
|
契約の内容とすることを目的として |
×事業者の内部ルールに過ぎないマニュアルや業務方法書 |
|
要件❸当該定型取引を行なうその特定の者が準備した条項
要件❹定型取引を行なうことの合意
要件❺定型約款を契約内容とする旨の合意又は定型約款を準備した者が「あらかじめ」その定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していた場合
アプリなどを久しぶりに起動したときに、約款が表示され「同意」ボタンをクリックしないと、アプリが使えないことがあると思います。あれが、定型約款を契約内容とする旨の合意です。
「利用規約をスクロールさせないと同意ボタンが表示されない」程度が理想です。
| 定型約款を契約内容とする合意をしたとき | |
| 又は | |
| 定型約款を準備した者が「あらかじめ」その定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していた場合 |
|
要件❻不当条項でないこと
顧客が定型約款の内容を認識していない場合があり得るので、不当条項を定めた定型約款の条項は、合意しなかった(契約内容にならなかった)ものとみなされます(民548の2Ⅱ)。
|
不当条項 とは
|
相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重するものであり | ||
| かつ | |||
| 定型約款の態様・実情、取引上の社会通念に照らして信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められる場合 | 物品の購入契約には、通常、その物品の定期的有料メンテナンスは含まれないが、約款には記載があった場合☛その条項は無効 |
要件❼相手方から定型約款を見せてと言われたとき遅滞なく表示すること
民548の3
会社HPに常時掲載させておき、表示請求に対してはURLを案内するのが一般的です。もっとも、約款を表示すること自体がノウハウの遺漏に繋がるため掲載できない場合には、開示請求に対して素早く開示することが必要です。
単に、会社HPに掲載しておくだけでは、表示請求に対応したことになりませんので、ご注意ください。
| 表示請求の時点 | ||||
| 定型取引合意前 | 定型取引合意後 | |||
| 相当期間内 | 相当期間経過後 | |||
| 表示義務 | あり | なし | ||
| 違反時の効果 | 契約の内容となるか否か | 定型約款が契約内容とならない | 定型約款が契約内容となる | |
| 強制履行(民414) | 可能 | 不可 | ||
| 損害賠償請求(415) | 可能な場合もある | |||
(表は、「Q&A民法改正の要点・企業契約の新法対応50のツボ/長島・大野・常松法律事務所・松尾博憲編著/日本経済新聞出版社」67pより引用)
相手方の同意なき定型約款の変更が認められる(効力発生する)ための要件
次のいずれかの要件をみたす必要があります(民548の4Ⅰ)。
| 方法A | 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき | + |
周知を怠っても効力発生に影響せず (民548の4Ⅲ反対解釈) |
|
| 又は | ||||
|
方法B |
定型約款の変更が契約をした目的に反せず、かつ合理的【1】であるとき |
+ |
効力発生前に適切な方法で周知【2】【3】 (民548の4ⅡⅢ) |
|
【1】合理的であるかは、次の基準によって判断されます。
①変更の必要性
②変更後の内容の相当性
③民法548条の2の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容
④その他変更にかかる事情
【2】周知すべき事項は次の3点です。
①定型約款を変更すること
②変更後の定型約款の内容
③効力発生時期
【3】適切な周知方法は、定型取引の態様等によって異なります。
| 取引の態様 | 周知方法の例 |
| ECサイトでの物販に適用される定型約款の場合 | ECサイト上で告知 |
| お店で取引する態様で、ポイントカードに適用される定型約款の場合 | 店頭に貼り紙 |
| 毎月請求書を送る態様の場合 | 請求書に同封 |
相手方の同意をとる定型約款の変更
相手方全員から個別に同意をとりつけた場合、民548の4は適用されません。
定型約款における各条文での工夫
具体的な約款にどのような工夫を凝らすかは、司法書士の腕次第ですが、次のような工夫をしています。
契約文言の平易化配慮義務
| 消費者契約法第3条(事業者及び消費者の努力) | |
|
利用者のサービス利用を制限する規定
事業者は、利用者の不正行為に対しては、サービス提供を中止(いわゆる「アカバン」)することによって対抗する必要があります。そして利用者の不正行為は予測不能なものもありえます。そこで、予測不能な不正行為が行われた場合であっても、サービス提供を中止するために下記のような包括的な条項を置くことがあります。
当社は、以下のいずれかに該当する場合、予告なく利用者の利用を一時的に停止しまたは登録情報を抹消することができます。
|
この定め方では、「当社が判断」という基準は、著しく明確性を欠き問題になりえます。
この場合には、次のように表現して少しでも明確にします。
当社は、以下のいずれかに該当する場合、予告なく利用者の利用を一時的に停止しまたは登録情報を抹消することができます。
|
免責規定・損害賠償額の制限に関する規定
定型約款における「免責規定と損害賠償の制限」については、こちらの外部サイト「利用規約における免責規定は会社を救う」(STORIA法律事務所)最終閲覧211020が秀逸ですので、ご参照ください。
標準的な所要時間
約款の作成・チェックの標準所要時間は、約1か月間です。
| 業務内容 | 所要時間 |
| ヒアリング(約款に反映する内容の聴取) | 7日 |
| ドラフト(案)作成・送付 | 14日 |
| ヒアリング(ドラフトの修正など) | 7日 |
| 合計 | 1か月ほど |
司法書士の報酬・費用
作成・精査とも、次のような基準でお願いしております。
| 業務の種類 | 司法書士の手数料 | 実費 |
| 定型約款の作成 |
220,000円(税込)~ |
|
| 法律・判例の調査を伴うもの | +55,000円(税込) |
- 弁護士のように契約金額(契約書に記載する金額)によって、司法書士報酬・手数料が増減することはありません。
- 顧問契約を締結いただいた場合、割引きがございます。
- 標準所要時間を大幅に短縮する納期でのご依頼の場合、割増料金(特急料金)5割増しを頂戴いたします。