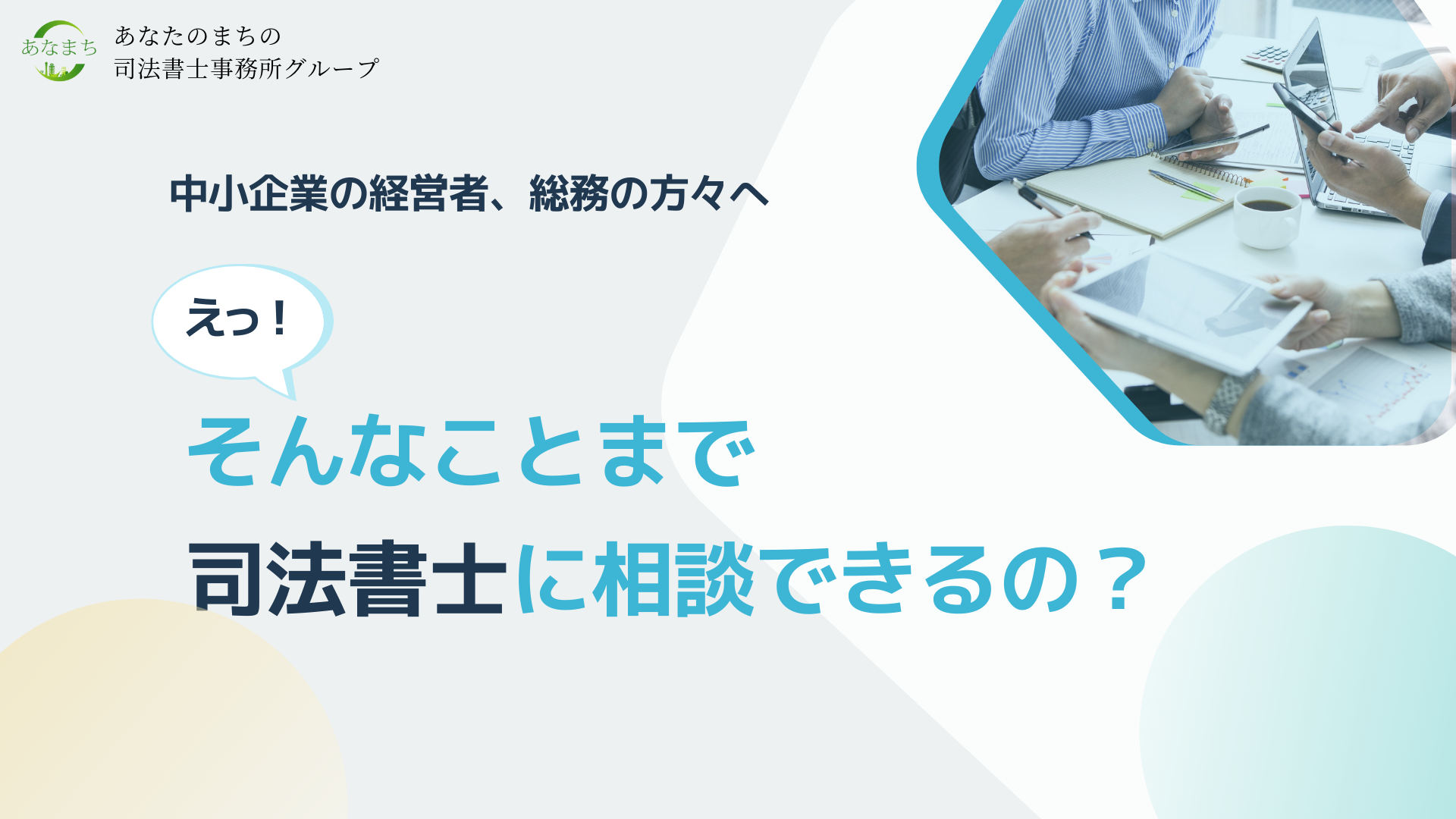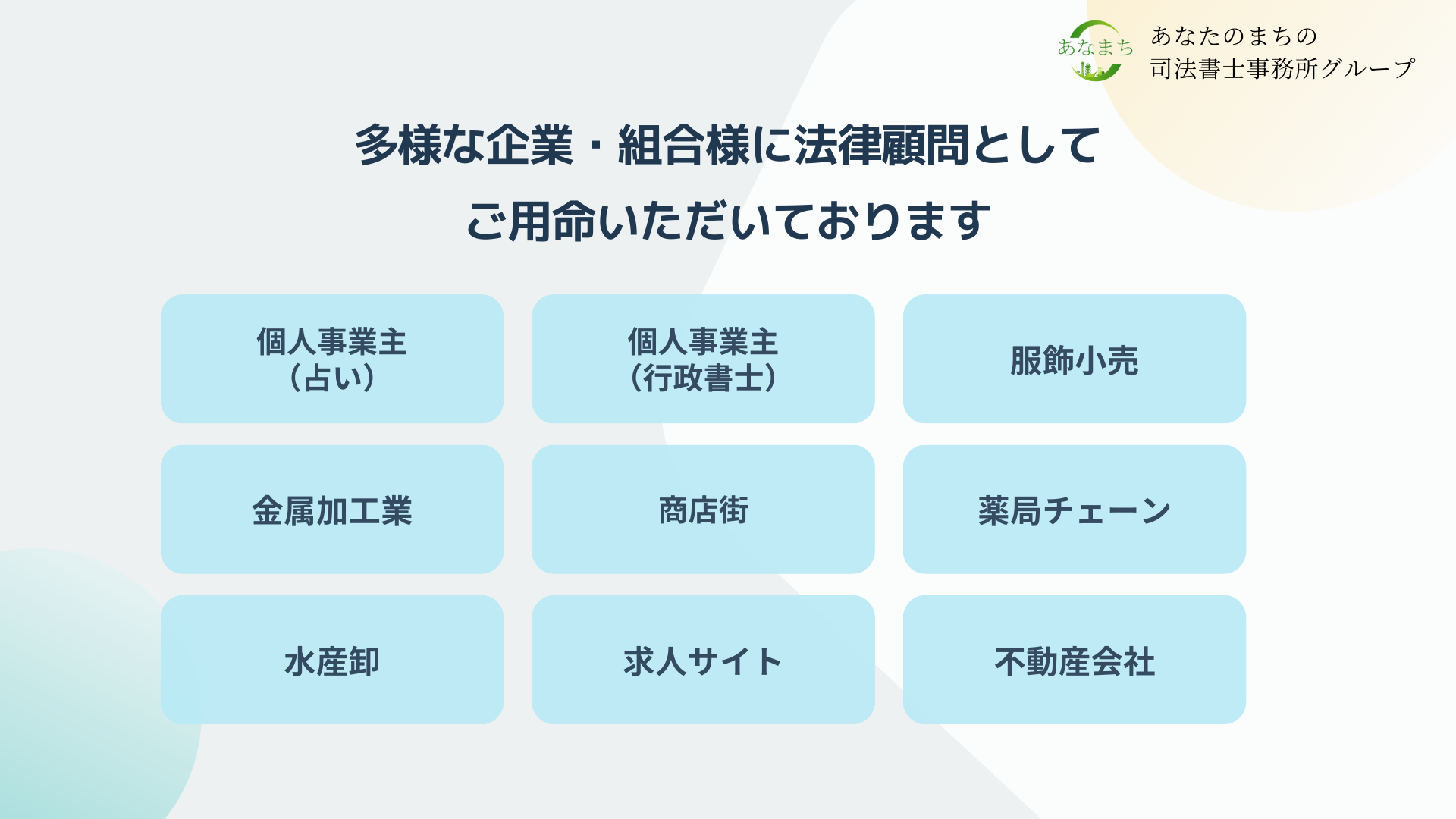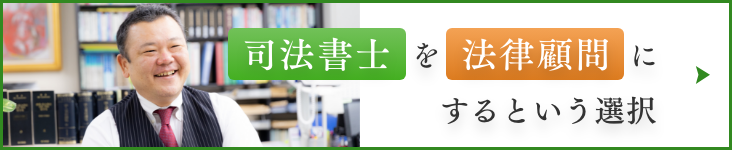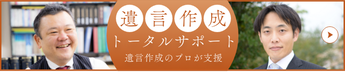- 不動産名義変更・不動産登記
- 売買・不動産取引・決済
- 不動産を売却予定の皆さまへ『司法書士による不動産売却サポート』のご紹介
- 建売住宅と建築条件付土地とは何が違うのですか?!
- 取引相手から「自分で登記する」と言われた不動産売買の当事者の方へ
- 不動産売買(取引)での関西方式・関東方式【まとめ】
- 不動産取引当日(決済当日)欠席するデメリット~業界通の司法書士が解説します。
- 不動産会社(仲介会社)なしで行う不動産取引
- 購入不動産は「新住所か旧住所」どちらで登記すべきか?!
- 同じマンションなのに敷地権付区分建物と敷地権の登記されていない区分建物があるのですが?!
- 認知症の方の不動産売却(行為能力・意思能力)
- 不動産売買契約締結前に、売主の判断能力確認(意思確認)を司法書士にご依頼くださる不動産会社様へ
- 隣地購入前に調べるべき助成金・補助金
- 住宅用家屋証明書:不動産購入時の登録免許税などの軽減
- 評価額0円の土地の登録免許税
- 生前贈与の手続と登記
- 財産分与の登記:離婚のときに簡単に「財産分与」を登記原因として登記してはいけない理由と代替案
- 差押・仮差押の取下書のチェックポイント(司法書士向け)
- 第三者のためにする契約(いわゆる三為契約、新中間省略)の契約実務・取引実務・登記実務
- 共有不動産の処分(贈与・売却・放棄)
- 外国人住民票と外国人登録原票記載事項証明書
- DV被害者の特例
- 判決による登記(不動産登記請求訴訟)
- 判決による登記(登記引取請求訴訟)
- 抵当権抹消の登記
- 根抵当権抹消の登記
- 解散や破産した抵当権者の抹消登記
- とても古い抵当権の抹消
- 土地区画整理事業(換地)と登記
- 拘置所・刑務所など刑事施設への被収容者(被告人・受刑者など)を登記当事者とする場合の注意点
- 終活TOP●これからの楽しい人生のため…元気なうちに始める終活
- 終活❶財産管理対策【成年後見】
- 終活❷財産管理対策【家族信託】
- 終活❸揉めさせない対策【遺産分割対策】
- 終活❹相続税対策
- 終活❺個人事業の承継対策
- 終活➏エンディングノート【無料】楽しく作る分冊型
- 終活❼楽しい家系図作成サービス
- 相続手続き・遺産整理など
- 契約書作成・精査
- 外国人の帰化
判決による登記(不動産登記請求訴訟)

登記に協力する義務があるのに、協力しようとしない登記関係者がいる場合、その者に対する判決を添付して、単独で登記をすることができます。
弁護士さんから多くのご質問を受けますので、論点をとりまとめました。
| もくじ | |
|
1.判決によってできる登記
すべての登記が判決によってできるわけではありません。
権利の登記
不動産登記法63条に規定があります。
| 登記の種類 | 可否 | |
| 権利者義務者が共同して行なうとされている権利の登記(不動産登記法60) | 可(不動産登記法63) | |
|
通常は合同申請でなされる次の登記 |
||
|
|
全共有者が共同して行なうとされている共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記(不65) |
|
| 順位を変更する抵当権者が共同して行なうとされている抵当権の順位変更登記(不89Ⅰ) | ||
| 根抵当権準共有者が弁済を受けるときの割合を債権額に応じないときの定め(不89Ⅱ) | ||
|
競売による所有権移転登記の抹消 和解調書に「競落による所有権移転登記の抹消登記手続をする」旨の記載がある場合 |
可(昭和37.10.26民事甲3099号) 競売による所有権移転は、私人間の合意解除等によっては抹消できないが、裁判や裁判上の和解により抹消することは可能である。 |
|
|
所有権保存登記 被告乙は、原告甲のために被告名義の建物所有権保存登記を抹消すべき。右建物は原告の所有であることを確認する。 |
可 登記申請書には「所有者の表示」として乙を、「申請人」として甲を記載する(昭和28.10.14民事甲1869)。 |
|
|
所有権保存登記 表示登記のない不動産につき「被告は原告に対し所有権移転登記手続をせよ」との判決がある場合 |
可 | |
|
中間省略登記 判決主文が甲から乙への移転登記を命じているが、判決理由で所有権が甲→A→乙に移転していることが明らかである場合 |
可。 中間省略登記は、原則不可。 判決主文で命じていれば可(昭和35.7.12民事甲1580、昭和39.8.27民事甲2885)。 |
|
|
所有権更正登記 「甲は乙に対し、甲名義でなされた相続登記を乙名義に更正せよ」との判決がある場合 |
更正登記不可(昭和53.3.15民事三1524) ∵更正登記の要件である主体の同一性がない |
|
|
真正な登記名義の回復登記 「甲は乙に対し、所有権移転登記をせよ」との判決の理由中において乙が相続により取得したのを誤って甲名義で登記されたものが明らかであるとき |
可(昭和53.3.15民事三1524) |
|
|
抵当権抹消 甲→乙への所有権移転登記の抹消を明示する判決に基づき、乙が丙のために設定した抵当権 |
丙の承諾書がない限り、丙の抵当権を抹消できない。 | |
|
相続登記の抹消 甲から乙へ売買、乙から丙へ相続を原因として登記されている場合に、甲から乙への所有権移転登記を抹消する旨の判決 |
前提として、乙から丙への相続登記をも、甲は単独で抹消できる(昭和38.12.28民事甲3380)。 | |
| 法定相続分による相続登記 |
必要ない。 ∵判決を得るまでもなく相続人が単独で(共有物に関する保存行為として)全相続人分を相続登記できる。 自己の持分のみを相続登記できない。 ∵あたかも被相続人と準共有しているような登記簿を作出してしまう。 |
|
|
被告からの判決に基づく単独登記申請 「被告は原告に対し、所有権移転登記手続をせよ」との判決 |
被告からの単独登記申請は認められない。 ∵意思表示を擬制されたのは被告であって原告ではない。 |
|
| 登記権利者が協力しない(登記引取請求) |
可(最高裁昭和36.11.24判決、昭和55.3.4民三1196)詳しくはコチラ |
|
表示登記
| 登記の種類 | 可否 | |
|
表示登記全般に関する原則 |
不可 ∵表示登記は単独申請で、権利登記の共同申請主義の原則を規定する不登法60は適用されず、その特則同法63(判決登記)も適用されない。 |
|
|
表題登記 甲は、表題登記がない乙所有建物を買ったが、乙が表題登記を申請しないため、自己の権利取得の登記が出来ない場合 |
必要ない。 ∵建物表題登記は、原始取得者だけでなく、売買等の特定承継者も、直接自己を所有者とする表題登記を申請できる。 乙が協力しないときは、乙を被告として所有権確認又は所有権移転登記請求訴訟を提起する。 |
|
|
地積更正登記 |
不可(昭和58.10.6民三5919) |
|
|
分筆登記 土地の一部を購入した者が、売主が分筆登記手続をとらず、所有権移転登記に協力しない。 所有権移転登記請求訴訟に先んじて分筆登記請求訴訟を要するか |
必要ない。 ∵以下の請求をまとめてすれば足りる。 「被告は原告に対して、別紙物件目録記載の土地のうち別紙分筆図面のイロハの各点を順次直線で結び囲まれた土地〇平米につき、年月日売買を原因として所有権移転登記手続せよ」 |
|
|
表題登記の抹消登記、滅失登記 自己所有地に、既に取り壊された第三者名義の建物登記が残っているとき |
可。 もっとも登記官の職権発動を促す申出をすれば足る場合もある(最判S45.7.16)ので、提訴前に登記官との調整は必須です。 |
|
|
滅失登記の抹消登記 根抵当権者が担保物件が誤って滅失登記された場合に、滅失登記の抹消登記を求める |
可(最判H6.5.12) | |

判決による表示登記まとめ
| 原則 | 不可 |
|
例外
|
実体を正確に表現していない表示登記の存在によって、自己の権利を侵害されている者は、表示登記請求権を行使できる。 登記官が職権ですることが出来ないのか、判決を取得すれば法63(判決登記)を類推適用して登記申請を受付してくれるのか、登記官と事前に調整することが必須である。 |
2.どんな判決を取得すれば良いのか?
「どんな判決文を取得すれば登記できるのか」という論点です。
| 要件 | 注釈 |
| ⑴ 判決主文中で | 主文中に登記原因が明示されていなくてもよい(昭和39.8.27民事甲2885) |
|
⑵ 登記申請を命じる
|
×売買せよ ×被告は原告に不動産を売り戻せ(明治33.9.24民刑1390) ×所有権を移転せよ ×登記に必要な書類を交付することを命ずる判決(昭和56.9.8民事三第5483号) ×原告又は原告の指定する者に対し、所有権移転登記登記手続をせよ(昭和33.2.13民事甲206) |
| ⑶ 給付判決で |
×所有権の存在を確認する確認判決では足りない。 例外①所有権保存登記は、所有権を有することが確定判決によって確認された者であれば申請できる(不動産登記法74Ⅰ②) 例外②相続登記で遺産分割協議が成立しているのに、一部相続人が協議書への押印、印鑑証明書の提出などを拒んでいる場合、所有権確認判決でも登記申請できる(平成4年11月4日民事局第三課長回答第6284号)【1】 |
| ⑷ 判決正本 | |
| ⑸ 確定証明書 | 判決主文に記載された不動産の表示について更正決定がなされているときは、その決定が確定したことを証する書面をも要する(昭和53.6.21法曹会決議)。 |
【1】詳細は「進まない相続登記(協力しない相続人がいる、相続人が何十人もいる)場合の対応方法」の「2.遺産分割協議は完了だが登記できない場合」の「⑵所有権確認請求訴訟プラン」をご参照ください。
3.判決に準ずるもの・準じないもの
判決に準ずるもの=登記で使えるもの
| 文書名 | 文書名の意味 | 注意点 |
| 和解調書 |
和解が裁判上でなされた場合に作成される文書 起訴前和解(即決和解)を含む (民訴267) |
|
| 認諾調書 |
被告が原告の請求を認めた場合に作成される文書 (民訴267) |
|
| 調停調書 |
民事調停法に基づく調停が成立した場合に作成される文書 (民事調停法16) |
|
|
家裁作成の 審判書 調停調書 |
家庭裁判所で行なわれた調停・審判で作成された文書 (家事事件手続法75、268) |
|
| 仲裁判断 |
当事者が紛争についての判断を、中立の第三者である仲裁人に委ね、仲裁人が判断したときはそれに従うことを予め合意(仲裁合意)した上で進める紛争解決手段。 仲裁合意を経ず紛争解決を試みる調停とは異なる。 (仲裁法45、46、民事執行法22Ⅰ⑥の2) |
執行力がないので、執行判決が必要 |
| 外国判決 |
外国の裁判所で出された判決 (民事執行法24、民事執行法22Ⅰ⑥) |
執行力がないので、執行判決が必要 |
判決に準じないもの=登記で使えないもの
| 文書名 | 文書名の意味 | 注意点 |
| 公正証書 | 公証人が作成した文書のこと。 |
登記では使えない。 |
| 転付命令 | 他人の財産を他人の財産のまま押えてしまう差押えと異なり、他人の財産を自分のものにしてしまう強制執行の方法。 | |
|
仮執行宣言
|
判決確定前であっても、仮に強制執行することができる旨の宣言。 判決文に付記される。 本来、意思表示を命ずる判決(登記手続を命ずるなど)には仮執行宣言は付けられないと解釈されている。 |
|
|
仮処分決定 仮処分判決 仮処分命令 |
判決が出るまでに時間を要するため、訴訟手続とは別に前もってする保全手続で裁判所が下した判断。 | |
|
家裁の保全処分 |
4.執行文の要否
原則:執行文は不要
∵確定または成立の時に意思表示をしたものとみなす(民事執行法174Ⅰ)
例外:次の場合は、執行文を要する。
∵執行文付与の時に意思表示をしたものとみなす(民執174Ⅰ但書)
| ①債務者の意思表示が債権者の証すべき事実の到来にかかるときは(条件成就)執行文を要する。 | |
|
|
例)農地法所定の許可を条件として所有権移転登記を命ずる旨の判決があった場合 ☛登記権利者は、農地法の許可書を裁判所に提出し、判決正本に執行文の付与を得る(民事執行法27Ⅰ)。 ☛登記申請書には、農地法の許可書の添付を要さない。 |
|
②債務者の意思表示が反対給付との引換えにかかるときは(条件成就)執行文を要する。 |
|
|
例)BがAに対して金〇円を支払うのと引換えに、AはBに対して所有権移転登記手続をせよとの判決があった場合 ☛登記権利者は、代金の給付をしたことを証する書面を裁判所に提出し、執行文の付与を得る(民事執行法174Ⅱ) ☛登記申請書には、代金給付を証する書面を添付しない。 |
|
|
③債務者の意思表示が債務の履行等債務者の証すべき事実のないことにかかるときは(条件成就)執行文を要する。 |
|
|
☛登記権利者は、ただ執行文付与の申立をする。 ☛裁判所書記官は、登記義務者に対して一定の期間を定めてその事実を証する文書を提出すべき旨催告し、登記義務者が期間内にその文書を提出しないときに、執行文を付与される(民事執行法174Ⅲ) |
|
|
④口頭弁論終結後、登記義務者に包括承継又は特定承継が生じたときは(承継)執行文を要する。 |
|
|
CF.口頭弁論終結前の承継は、訴訟承継、訴訟引受の問題。 CF.登記権利者に包括承継が生じたときは、承継執行文を要しない。 ∵登記権利者の包括承継人が不動産登記法62条により登記申請できる。 CF.登記権利者に特定承継が生じたときは、承継執行文を要しない。 ∵登記権利者の特定承継人は債権者代位により登記申請できる。 CF.移転登記を命じる判決後、登記義務者に特定承継が生じ、その特定承継人が登記を備えたときは、登記権利者は民法177条の対抗関係で負けてしまう。 CF.抹消登記を命じる判決後、登記義務者に特定承継が生じた場合は、次の二通り。
|
|
5.判決による登記の実行
「被告は、原告に対して、別紙物件目録記載の不動産につき、年月日売買を原因として所有権移転登記手続をせよ」との判決を得た場合、原告は、その判決に基づき、単独で登記申請できます。
判決主文を登記申請書に当てはめると次のようになります。
| 判決主文 | 登記申請書 |
| 所有権移転登記手続をせよ | 登記の目的 所有権移転 |
| 年月日売買を原因として【1】 | 登記原因 年月日売買 |
| 原告に対して | 登記権利者(申請人)原告の住所・氏名【2】 |
| 被告は | 登記義務者 被告の住所・氏名 |
|
添付書類 判決正本 原告・登記権利者の住民票 課税価格 登録免許税 |
|
|
別紙物件目録記載の不動産につき |
不動産の表示 |
【1】次の要領で登記する。
| 判決主文 | 登記原因(登記申請書) |
| 令和5年10月5日頃売買 | 令和5年10月日不詳売買 |
| 令和5年10月頃売買 | 令和5年月日不詳売買 |
| 令和5年頃売買 | 令和年月日不詳売買 |
| 登記原因もその日付も記載がない | 令和○年○月○日判決(日付は判決確定日を記載する。) |
【2】(申請人)と記載するのは、単独申請であることを表現するためです。