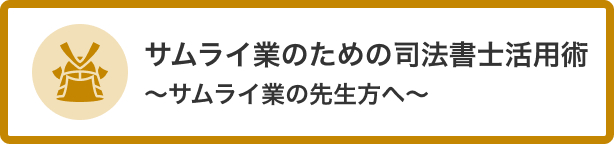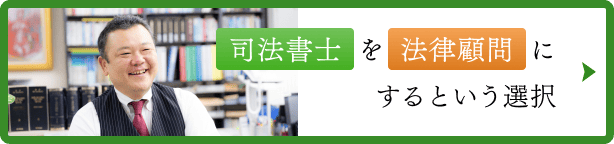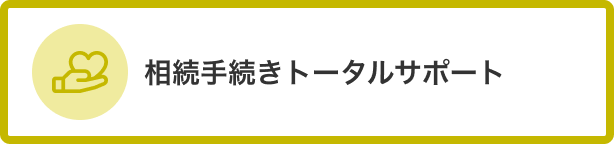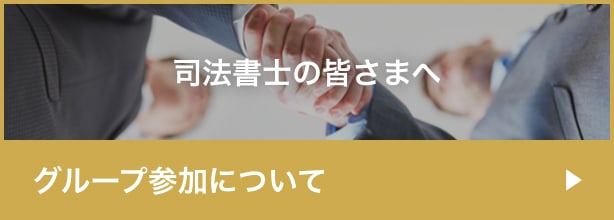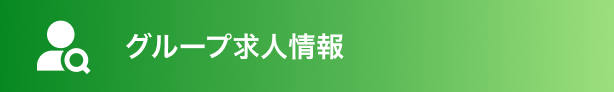- トラブル解決総論
- 相続・遺産分割トラブル解決
- 夫婦子供のトラブル解決
- その他親族トラブル解決
- 企業・事業者のトラブル解決
- 不動産・借地借家・隣近所のトラブル解決
- 不動産の取得時効と登記の関係
- 不動産賃貸借における関西方式・関東方式
- 敷金・保証金・建設協力金の違い
- 賃貸借契約の当事者が変更した場合、誰が誰に敷金を返せば良いか?
- 敷引特約の有効性
- 賃貸借契約で「中途解約を禁止する条項」は有効か?
- 賃貸借契約における更新料条項の有効性、更新料不払いの効果、法定更新との関係ほか後日もめないための具体的な対策
- 賃貸借契約で遅延損害金を年14.6%とする条項は有効か?
- 明渡しが遅れたときに賃料倍額の使用損害金を請求する条項は有効か?
- 滞納賃料(家賃・地代)の請求を受けた連帯保証人の対応
- 借主の軽微な契約違反だけでは解除できない賃貸借契約「信頼関係破壊の法理」
- 家賃滞納による建物明渡請求
- 賃借人が連帯保証人を立てない場合、賃貸人は賃貸借契約を解除できるか?!
- 賃料(地代・家賃)増減額請求
- 借地に関する契約
- 借地権登記できない場合の「借地上の建物登記」民法177条の例外
- 建物賃貸借の契約期間を設定するときの注意点
- 借地上の建物を賃貸借するときの注意点
- DIY型賃貸借契約のメリットと注意点
- 原状回復・敷金返還に関するトラブル解決
- 建物賃貸借で「通常損耗をも借家人負担とする」特約の有効性
- 原状回復義務と明渡義務の関係|原状回復が終わらないと、建物明渡し完了にならない?!
- マンションの滞納管理費・修繕費・積立金の回収
- マンション義務違反者への対応
- 連棟建物(長屋、二戸一、三戸一)の切り離しトラブル
- マンション上階や二戸一の隣家からの水漏れトラブル解決
- 隣近所とのトラブル解決
- 隣地の建築計画はどこで確認するか?!宅地開発から建物建築までの流れ
- 建物建築に際しての周辺住民への説明義務
- 隣地が境界ギリギリに建築するのを止められませんか?!
- 崖地の擁壁・石垣の補修に関するトラブル【図解】
- 隣地に対する目隠し設置請求権
- 境界トラブル(筆界と所有権界)
- 私道の通行権をめぐるトラブル
- (ケガの後遺症や精神疾患などが原因で)騒音、大声、奇行などの問題行動をおこし周囲に迷惑をかけている方への対応(グループ会員限定記事)
- 交通事故解決
- 消費者トラブルの解決
- 借金が返済できないときの個人の債務整理(任意整理・民事再生・自己破産)
- 判決が出ても従わない相手方への強制執行による債権回収(差押え)
- 仮差押・仮処分など保全処分
- 刑事事件(被害者・加害者)
- 少年事件(被害者・加害者)
原状回復義務と明渡義務の関係|原状回復が終わらないと、建物明渡し完了にならない?!

賃借人が不動産を返還(明渡し)しようとすると、賃貸人から次のように言われることがあります。
- 「原状回復が終わっていないから、返還は受け付けられない(明渡しは受けられない)」
- 「返還は受けたけれども、原状回復が終わっていないから、原状回復が終わるまで賃料(相当損害金)を請求する」
これら賃貸人の言い分は、正しいのでしょうか?
この記事では、①賃貸借契約が終了したときの賃借人の義務、②目的物の返還(明渡し)の定義、③原状回復と明渡しの関係を順に解説しています。
| もくじ | |
|
賃貸借終了時の賃借人の義務
賃貸借が終了したときは、賃借人は目的物を原状に回復して、返還しなければなりません。
これを分解しますと、賃貸借終了時の賃借人義務は、二つあることが分かります。
- 目的物を原状に回復する義務(民法621)
- 目的物を賃貸人に返還する義務(民法601)
そして
- 原状回復が不足していれば、賃借人は賃貸人に対して、原状回復費の支払い義務を負います。
- 賃貸借終了後も目的物を返還しなければ、不法占拠として、返還するまでの遅延損害金の支払い義務を負います。
まとめると次のとおりです。
| 賃貸借終了時の賃借人の義務 | 義務違反の効果 |
|
|
|
|
目的物の返還(=明渡し)とは何か?
「目的物を賃貸人に返還する」とは、明渡しという方法によって行うのが通常です。
「明渡し」とは、賃借人が占有を解いて、賃貸人に占有を渡す方法です。
より具体的には、次の裁判例による説明が、実務家である私たちの感覚とも一致しているためご紹介します。
| 東京地判平成18年12月28日(平18(ワ)8980号建物明渡等請求事件(本訴)、平18(ワ)17940号敷金返還請求事件(反訴)、ウエストロー・ジャパン) | |
|
一般に,賃貸借契約における賃借人の目的物返還義務としての不動産の明渡しとは,当該不動産の占有者が立ち退くとともに,不動産内にあった動産を取り除いて賃貸人に直接的な支配を移すことである |
|
| 東京地判令和3年9月29日(平29(ワ)5555号損害賠償請求事件(一部本訴)、平29(ワ)21983号不当利得返還等反訴請求事件、ウエストロー・ジャパン) | |
|
残置物がある場合,所有権放棄をすることで当然に占有者としての明渡義務を免れるものではない(無主物が残置されるに至る原因は放棄者が作出しているのであるから,占有の継続を認めるのが相当である。)。 |
|
| 東京地判平成27年9月10日(平27(ワ)2025号建物明渡等請求事件、ウエストロー・ジャパン) | |
|
被告会社(=賃借人。※筆者注)の所有物が本件建物を占有しているといえるほどに本件建物内に放置されていると認めるに足りる証拠はない。そして,被告会社が本件建物の鍵を返却しているという事情に鑑みれば,被告会社が本件建物について占有の意思があるともいえない。 したがって,被告会社が本件建物を占有しているとは認められない。 |
|
これらの裁判例を整理しますと、次のとおりです。
|
【目的物返還(=明渡し)の定義】 下記をすべて実行すれば、目的物の返還(=明渡し)が完了したことになります。
|
次にご紹介する裁判例でも、賃貸借物件内に残置された動産ごとに所有者を特定したうえ、賃借人の所有物は明渡しを阻害し、賃貸人の所有物は明渡しを阻害しないと、判断しています。
| 東京地判平成26年4月23日(平24(ワ)34477号敷金返還請求事件、ウエストロー・ジャパン) | |
|
ア 建物の賃借人は,賃貸借契約終了時に賃借建物の返還義務を負う(民法616条,597条)ところ,賃借人は,当該返還義務の一環として,建物の通常の使用収益を妨げる物を収去して原状に回復する義務も負うと解される。そうすると,原状回復までの当事者間のやりとり,原状回復が未了であることにより賃貸人に与える不利益の程度などを考慮して,原状回復の一部が完了していなくても,建物の明渡しが完了したと認められる特段の事情がある場合を除き,原状回復義務を履行して賃借建物を引き渡した時点で明渡しが完了するというべきである。 イ これを本件についてみると,上記(1)のエのとおり,原告が被告に対し,本件建物の鍵を引き渡した時点(筆者注:平成23年12月31日)では,原状回復が完了していないから,本件建物の明渡しがあったとはいえない。 ウ もっとも,上記(1)のオのとおり,平成24年1月6日にトレーニング機器が搬出されたことで,通常の使用を妨げる動産が本件建物内から搬出されたといえる。 そして,上記(1)のカのとおり,本件エアコンは,被告が契約した本件リース契約のリース物件であり,その所有権も被告にあることが確認されていたことからすれば,本件エアコンの搬出を行うべきであったのは被告であったということができ,現に被告の手配で撤去がされているから,本件エアコンの撤去は,原告が行うべき原状回復とはいえない。したがって,本件エアコンの搬出の遅延(筆者注:平成24年1月16日)は,明渡し時期の認定に影響を及ぼさない。 さらに,原告と被告は,平成23年11月頃から,年末の本件建物明渡しに向けて協力して準備を進めていたが,その間,看板の撤去は話題に上っていなかったこと,被告から申し入れ後,原告は速やかに看板の撤去を行ったこと,被告も看板撤去までの期間の賃料発生を主張していなかったことという経緯(上記(1)のア,イ,キ)及び看板の撤去が遅延したことにより被告が損害を被ったことを認めるに足りる証拠がないことに照らせば,原状回復の一部が完了していなくても,建物の明渡しが完了したと認められる特段の事情があるといえる。 以上によると,平成24年1月6日のトレーニング機器の搬出をもって,本件建物の明渡しが完了したといえる。 エ 原告は,本件賃貸借契約上の賃貸人の同意があったこと,残置動産の所有権を放棄する旨の特約の適用があることを主張する。 しかし,被告がトレーニング機器の搬出を平成24年1月6日に変更することを認めたとしても,その間の賃料相当額の支払いを免除したことにはならない。 また,残置動産の所有権を放棄する旨の特約は,賃借人が原状回復義務を履行しなかった場合に備えて,賃貸人が原状回復を代行できるようにするための特約であると解される。したがって,当該特約があるからといって,賃借人の原状回復義務が免除されるとはいえない。 |
|
次にご紹介する裁判例は、賃貸人が鍵の受け取りを拒否していたケースです。
| 東京地判平成22年3月16日(平21(ワ)9134号損害賠償請求事件(本訴)、平21(ワ)30979号損害賠償請求等反訴事件(反訴)、ウエストロー・ジャパン) | |
|
建物賃貸借契約が終了した場合においても,賃借人は,原則として,賃貸人による建物の明渡確認を受け,かつ建物の鍵を賃貸人に返還しなければ建物の返還義務を尽くしたことにならず,賃料相当損害金の支払義務を免れないというべきである。しかしながら,かかる建物返還債務の履行は賃貸人の協力がなければなし得ないところであるから,賃貸人が正当な理由なくこれに協力しないときは,賃借人においてこれに代替すべき社会的に相当な手段を採ることが許され,同手段を採ることにより賃借人は建物返還義務を尽くしたことになり,以後,賃料相当損害金の支払義務を免れると解するのが相当である。 本件の場合,賃借人が賃貸人による建物の明渡確認を受け,また,鍵を返還するためには,明渡確認の日の決定等について賃貸人と賃借人間で協議することが不可欠であるところ,被告は,前記1のとおり,原告会社からの郵便物の受領を拒絶してかかる協議の道を自ら閉ざしているのであり,賃借人の建物返還債務につき正当な理由なくこれに協力しないものと認めることができる(なお,賃借人が賃料等の支払を遅滞していたとしても,賃借人からの郵便物の受領を拒絶する正当な理由とならないことは言うまでもない。)。そして,証拠(甲1,7,8,27,原告X2の供述)によれば,原告は,本件賃貸借契約締結の際の仲介業者であった訴外不動産会社に対して建物明渡しの立会いを求め,平成20年9月30日,本件建物の鍵を同社に預けたものと認めることができ,原告会社がかかる措置を採ったこともやむを得ない社会的に相当な行為と評価できる。 |
|
原状回復とは何か?
先にご説明した「目的物の返還(=明渡し)の定義」には「原状回復したこと」は含まれていません。
「原状回復」とは、借りた物を、借りた当時の状態に戻すことです。
もっとも、新築建物を借りたら、新築建物を返す義務を負うかというと、そうではありません。時間の経過によって、自然と損耗した分は、賃借人は元に戻す義務を負わない(賃貸人が負担すべき)というのが、確定した判例の考え方です。
詳しくは、記事「原状回復・敷金返還に関するトラブル解決」をご参照ください。
原状回復完了まで、返還(明渡し)未了なのか?
多くの裁判例が、次の理由から「原状回復と明渡しは別物」すなわち「原状回復が未了であっても、明渡しは完了しうる」としています。
- 民法でも目的物返還(明渡し)義務(民法601)と原状回復義務(民法621、同622→599Ⅰ)とが別々に規定されていること。
- 目的物返還は、原状回復義務の履行の有無にかかわらず可能であり、後者が履行されなければ前者が履行できないという関係にはないこと。(後掲・東京地判平成18年12月28日、後掲・東京地判平成28年2月19日、後掲・東京地判令和元年7月16日)
- 原状回復義務は、目的物返還後に履行することも可能であること。(後掲・東京地判平成28年2月19日)
- 原状回復義務の範囲は、必ずしも一義的ではなく、原状回復の範囲について賃貸人賃借人が合意できるまで使用損害金を支払わせるのは不合理であること(後掲・東京高判昭和60年7月25日、後掲・東京地判平成22年12月20日)
裁判例の紹介
いずれの裁判例も、少し長めに引用しています。
事実関係を詳しく知りたい方のためです。
概要だけ分かれば良い方は、オレンジ色にハイライトされた部分だけをお読みください。
| 東京地判昭和53年10月26日(昭52(ワ)2669号、判時939号65頁、ウエストロー・ジャパン) | |
|
事業者間の賃貸借の事例です。 要旨 ◆貸室賃貸借契約において賃借人が契約に基づく一切の債務を担保するため保証金を預託した後、賃借人が契約終了後原状回復義務を履行しないまま退去した場合、賃貸人は、保証金から補修費用のほか、補修必要期間中の明渡遅滞損害金を控除した残額を返還する義務があるとした事例 (要旨は、ウエストロー・ジャパン) |
|
|
抜粋 「賃借人が賃貸借終了後原状回復義務を履行しないまま賃借部分を空室にして退去した場合の保証金返還義務の範囲について検討する。 本件保証金が賃借人たる原告の契約上の一切の債務を担保するため差入れられたものであること、本件賃貸借契約において、抗弁1に記載したような保証金からの原告の負担すべき債務額の優先控除及び明渡遅滞の際の損害金(以下「明渡遅延損害金」という)に関する合意がなされたことは、当事者間に争いがない。そして、本件賃貸借契約において賃借人が原状回復義務を負うものと解すべきことは前記二のとおりであるから、賃借人がその義務の履行として賃借物件の原状回復を行なっていたため約定の明渡期限を遅滞すれば、右遅滞期間につき明渡遅滞損害金が保証金より控除されることとなり、賃借人は原状回復のための補修費用と明渡遅滞損害金を負担することになる。 そこで、右の争いのない事実と想定事例との対比において考察すると、本件の如き場合には、賃借物件の原状回復のための補修が代替性を有し、かつ第三者において右補修着手可能時(多くの場合賃借物件から退去の時である)までにおける賃借人の負担する債務を保証金から控除した額によって、補修費用及び補修に必要な期間中の明渡遅滞損害金をまかない得るのであれば、賃貸人は賃借人退去後補修に必要な期間を経過した時点において、右残存保証金から、更に、補修費用のほか、補修必要期間を明渡遅延期間とみなし同期間中の明渡遅滞損害金を控除した残額を賃借人に返還すべき義務を負うものと解するのが相当である(なお、中途解約の場合であって右算定時点において当初の契約期間が満了していなければ、請求原因2の約定により右満了時まで右返還義務は猶予される。)。 もし、被告が主張するように、賃借人が原状回復義務を履行しない限り賃借物件の明渡が行なわれないと解すると、賃借人が自らその補修をなさない限り又は本件における如く賃貸人が補修を行なって明渡したとみなさない限り、明渡遅滞損害金が保証金から控除され続けることになる。そうだとすると、たとい補修をしないことにつき賃借人に責のある場合であっても、賃借人の損失が賃貸人の得る利益に比し均衡を失し不公平な結果を招来することが考えられる。例えば、賃借人が資力に欠け不本意に補修を遅滞しているが、反面経済情勢の影響等で貸室希望者が少なく仮に即時に原状回復されたとしてもこれを他に賃貸し得る蓋然性が低いことが予想されるにもかかわらず、賃貸人は補修が遅滞する間(少なくとも保証金から明渡遅滞損害金を控除し得る間)毎月賃料の倍額及び共益費用に相当する明渡遅滞損害金を取得し得るという結果を容認することにもなるのである。 これに対し前記の如き解釈をすれば、右のような不都合結果は避け得るし、また貸室希望者の多い場合には、保証金が残存する限り賃貸人が賃借物件の補修が可能となった時点において直ちに補修に着手すれば、その費用及び補修のため賃借物件を利用し得ない損害を明渡遅滞損害金控除という形で十分回復のうえ他に賃貸することができるのであるから、賃貸人にとって不利益をもたらすということはない。」 |
|
| 東京地判平成18年12月28日(平18(ワ)8980号建物明渡等請求事件(本訴)、平18(ワ)17940号敷金返還請求事件(反訴)、ウエストロー・ジャパン) | |
|
民法上,借用物の返還義務と原状回復義務は異なるものであり,後者が履行されなければ前者が履行されていない,という関係にはないというべきである。 この点につき原告は,一般に,事務所の賃貸借契約においては,賃貸人はいわゆるスケルトンの状態で目的不動産を引き渡し,賃貸借契約終了に際しては賃借人が行った内装すべてを撤去して賃貸人に引き渡すのが通例であると主張する。確かに,一般にオフィスビルの賃貸借においては,次の賃借人に賃貸する必要から,賃借人には返還に際して賃貸借契約締結時の原状に回復することまで要求される場合が多いとしても,原状回復義務は目的物返還後に履行することも可能であるから,賃貸借契約において,目的物の返還に先立って原状回復することが定められていれば格別,そうでない限り原状回復義務が目的物返環義務に必然的に先行する関係にあるとはいえない。 |
|
| 東京地判平成22年7月22日(平21(ワ)24465号、ウエストロー・ジャパン) | |
|
原告が被告に対して平成20年9月30日に本件建物①の鍵類等をすべて引き渡して本件建物①の事実上の支配を移転し、もって本件建物①を明け渡したことが認められる。被告は、本件建物①内の備品の撤去費用の精算等が行われていないから、その明渡しは完了していないと主張しているけれども、不動産の明渡しとは、不動産の事実上の支配の移転を意味するから、原告が被告に対して本件建物①の鍵類等をすべて引き渡して本件建物①の事実上の支配を移転した以上、本件建物①の明渡しは完了したものと認めるべきであり、被告の上記主張は採用することができない。 |
|
| 東京地判平成22年12月20日(平21(ワ)39001号、ウエストロー・ジャパン) | |
|
当事者間で原状回復義務の範囲,程度やその存否が争われているような場合に,賃借人において,賃貸人が主張するとおりの「原状回復」を履行しない限り,半永久的に賃貸物件の明渡し自体が終わらず,賃借人は賃貸人に対し,賃料その他の諸経費相当額の支払義務を負い続けるなどと解することは,余りに不合理である。しかも当事者間では,そのように紛争性の高い原状回復費用をも担保する趣旨で,敷金の授受がなされているのであるから,賃貸人が,賃借人の主張する原状回復の程度では不足と主張するのであれば,自ら原状回復工事を実施した上,当該敷金をもってその費用に充てるなどした後に,双方が敷金の返還もしくは不足金の支払を巡って,まさに本訴のような事後的な金銭の支払請求をすることにより,その精算を図ることは十分可能である。 |
|
| 東京地判平成23年7月6日(平22(ワ)35212号建物明渡請求事件、ウエストロー・ジャパン) | |
|
賃貸借契約における賃借物の明渡義務とは賃借人が賃借物の占有を賃貸人に移転することをいうのに対し,原状回復義務とは賃借物を契約時の原状と同じ状態に戻す義務をいい,両者は別個のものである。そうすると,被告が原状回復義務の一つである本件中2階設備の撤去義務を履行していないとしても,原状回復義務違反の問題が生ずるのは格別,原告の明渡義務が不履行とされるものではない。むしろ,本件において,被告は平成22年8月14日に原告に対し本件倉庫の鍵を返還して本件倉庫を明け渡したことは前示のとおりであり,これにより被告の明渡義務は履行されている。 |
|
| 東京地判平成28年2月19日(平27(ワ)4842号原状回復費用請求事件、ウエストロー・ジャパン) | |
|
(1) (略)被告Y1は,平成26年2月10日,管理会社に対し,本件居室の鍵を返却して本件居室を退室し,その事実的支配を原告に移転したことが認められるところ,これをもって,本件更新契約16条所定の被告Y1の原告に対する明渡し義務の履行は終了したと解すべきである。 (2) 原告は,被告らが本件賃貸借契約終了後,原告が費用を支出して本件居室の修理を完了させるまでの間,原状回復費用の支払を一切行わなかったことにより本件居室の原状回復はなされなかったことや,被告Y1が本件居室に設置したエアコンを撤去していないことを指摘して,その明渡しは完了していない旨を主張する。 しかし,本件賃貸借契約及び本件更新契約において,本件居室の明渡しにつき「原状回復をした上で明け渡すこと」を指す旨合意したことを認めるに足りる証拠はない。かえって,本件更新契約15条1項は,原状回復と返還(明渡し)とが別の行為であることを前提とし,明渡しに先立って原状回復が行われなければならない旨を定めているものと解されるのであって,被告Y1が本件居室に設置されたエアコンを撤去しなかったことなど,原状回復をせずに明渡しをした場合には,明渡し前の原状回復義務違反を理由とする債務不履行が成立するにすぎないから,原状回復がなされていないことは,明渡し義務の未履行を意味するものではない。 |
|
原状回復完了まで、賃貸人は明渡しを拒み、賃料を受領し続けることができるか?
この問いは、先に解説した「原状回復完了まで、返還(明渡し)未了なのか?」と同じです。
お気に入り書籍の一冊に分かりやすい解説がありましたので、引用しておきます。
後掲・借家の法律相談 第3版補訂版/430頁
|
家主は明渡を受けることを適法に拒むことはできません。(中略)特約のないかぎり、借家人は、明渡義務の発生した時点、すなわち賃貸借契約の終了した時の借室をあるがままの状態で家主に明け渡せば、建物明渡という特定物明渡の債務についてはその債務の本旨に従った履行となるわけです(民法483条)。したがって、目的物件が汚染・毀損していてもそのままの状態で明け渡せば、借家人としては、建物明渡という債務の履行については債務者としてなすべき義務を果たすことになり、家主はその受領を拒むことはできないのです。というのは、特定物の引渡は、代替性がなく、その物件の引渡が大切なのであって、目的物件の毀損・汚染とは直接関係がないからです。 |
契約書に「原状回復のうえ明け渡す」とある場合
賃貸借契約書の中には、次のような条項があることが多いです。
| 賃貸借契約書第○条(明渡時の原状回復) | |
|
賃貸借契約が終了したときは、賃借人は建物を原状に回復をしたうえで、明け渡す。 |
|
成り立つ2つの解釈
この条項は、2通りの解釈ができます。
- 【解釈A】賃借人には明渡前に原状回復する義務があることを確認にしたものに過ぎない。
☛原状回復の有無は、明渡し完了に影響しません。民法通りです。
- 【解釈B】原状回復しない限り、明渡しは完了しないという「特約」である。
☛原状回復の有無が、明渡し完了に影響するので、民法の原則を変更する「特約」になります。
※【解釈A】【解釈B】は、筆者が、説明のためにつけた名前で、公式のものではありません。
【解釈A】の帰結
下記裁判例では【解釈A】を採用しています。
| 東京地判令和元年7月16日(平28(ワ)37576号建物明渡等請求事件、ウエストロー・ジャパン) | |
|
賃借人が目的物の占有を賃貸人に移転させることは原状回復義務の履行の有無にかかわらず可能である以上,賃貸借契約が終了した場合における目的物の返還義務は,当事者間に特段の合意がない限り,賃借人が目的物の占有を解き,その占有が賃貸人に移転した時点で履行されたものと評価すべきであり,そのことは,原状回復義務の履行の有無とは別個の問題であるというべきである。 本件では,上記前提事実のとおり,本件契約書20条(1)において,賃借人は,契約終了と同時に,本件住戸を引渡時の原状に回復の上,本件住戸を明け渡さなければならない旨規定しているものの,これは,賃借人が引き渡す前に原状回復工事を行う義務があることを明確にするにとどまり,原状回復工事が終了しなければ明渡しがあったとはみなさないという規定ではなく,またその他の証拠からも,上記特段の合意があったとは認められない。そうすると,本件住戸の明渡しは,上記(1)のとおり,遅くとも平成27年12月頃には完了していたものというべきである。また,原告は,スペース社が平成28年1月以降,賃料ないし約定損害金が発生することを前提として,賃料送金明細書を原告に送付してきている点を指摘するが,仮にそのような事実があるとしても,上記評価を左右するものではない。 |
|
【解釈B】の帰結
賃借人が消費者のときには、消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)により、条項が無効になる可能性が高いと思います。
賃借人が事業者のときには、契約自由の原則から、条項が有効になる可能性もあろうかと思います。
次の裁判例は、【解釈B】を採用したうえ、事業者である賃借人を勝たせています。
| 東京高判昭和60年7月25日(昭60(ネ)149号、昭60(ネ)250号保証金返還請求控訴事件、ウエストロー・ジャパン) | |
|
要旨 ◆営業用建物賃貸借の当事者間で賃貸借終了後原状回復・明渡済みに至るまで賃料相当額等の損害金を支払う旨の特約をした場合における特約の趣旨と原状回復義務の内容 (要旨はウエストロー・ジャパンによる) |
|
|
抜粋 本件賃貸借契約の締結に際して当事者間で交わされた契約書には、「賃借人は、賃貸借契約が終了したときは、賃借人の加えた造作、間仕切、模様替その他の施設及び自然破壊と認めることのできない破損箇所を賃貸人の指示に従って契約終了の日から一五日以内に賃借人の費用をもって原状に回復しなければならない。」、「賃借人は、右の条項による明渡完了に至るまでの賃借料及び付加使用料に相当する金額を賃貸人に支払い、なお損害のある場合にはこれを賠償しなければならない。」との各条項が記載されていることが認められるところ、本件建物のような営業用建物の賃貸借契約の実情に照らして判断すれば、その趣旨とするところは、賃貸借契約の終了に伴う目的物の返還義務と原状回復義務とは本来必ずしも一致するものではないけれども、賃貸人が新たな賃貸借契約を締結するのに妨げとなるような重大な原状回復義務の違背が賃借人にある場合には、これを目的物返還義務(明渡義務)の不履行と同視して、賃借人は賃貸借契約終了後一六日目から右のような原状回復義務履行済みに至るまで賃料相当額の損害金を賃貸人に支払わなければならないとするにあるものと解するのが相当である。したがって、右の程度に至らない程度の軽微な原状回復義務の違背があるに過ぎない場合においては、賃貸人は、それによって被った損害の賠償を請求し又はその代替履行のために要した費用の償還を請求することができるのは格別、当然に賃料相当額の損害金を賃借人に請求することができるものではないものといわなければならない。 さらに、建物賃貸借契約の終了に伴う原状回復義務といっても、その範囲は必ずしも一義的に明らかなものではなく、とりわけ本件におけるように営業店舗用建物の賃貸借契約にあっては、賃借人が自己の営業目的に適合するように改めて内、外装工事等を行うような例が多いため、字義どおり賃貸借契約締結時の原状に回復することが常に合理的であるとは限らず、賃貸人にとっても格別の意義がないことが多いのであるから、原状回復義務の履行に当たっては、賃借人としては、賃貸人との協議の結果と社会通念とに従って、賃貸人が新たな賃貸借契約を締結するについて障害が生じることがないようにすることを要し、かつ、そうすることをもって足りるものというべきである(前掲契約書には、賃借人は賃貸人の指示に従って原状回復義務を果たすべき旨の条項が含まれているが、その趣旨は、以上に説示したところと特に異なる意味を持つものではない。)。 |
|
| 東京地判平成22年12月20日(平21(ワ)39001号、ウエストロー・ジャパン) | |
|
(1)一般的に,賃貸借契約の目的である不動産の明渡しは,賃借人が賃貸物件から立ち退くとともに,賃貸物件内にあった動産を取り除いて,賃貸物件に対する直接的な支配を賃貸人に引き継ぐことをいうと解されるが,原告は,特約があることを理由に,本件各賃貸借契約では,原状回復義務が履行されない限り明渡しは完了しないと主張する。 そして確かに,本件各賃貸借契約では,物件の明渡しについて,以下のような条項がもうけられているのであり(契約書19条,甲1,2,7,8,乙1),かかる条項は,被告アートや被告広仁社において,201又は202を明け渡す以前に,その原状回復をなすべき義務があることを,特に定めた規定と解し得るところである。 ア 契約が終了したときは賃借人は物件を原状に復して無条件で直ちに賃貸人に明け渡すものとする。 イ 賃借人が賃貸借契約終了後30日を過ぎてもなお物件の明渡しを完了しないときは,賃借人は物件内の物品の所有権を放棄する。この場合,賃貸人が物件内に立ち入り,賃借人の負担で物件を原状に復し,残置物品を賃借人の負担で賃貸人が任意にこれを処分することができることを賃借人が予め承諾する。この場合,賃借人の処分が完了した日をもって物件の引渡しがあったものとする。 (2)しかし,およそ賃貸借契約終了時における原状回復義務の範囲,程度,あるいは存否については,しばしば当事者間に厳しい意見対立が生じることがあるのは周知のことである。にもかかわらず,上記条項における「原状回復」については,その内容,程度について,何ら具体的な規定がないから,賃借人としては,前記規定のみをもってしては,自らが行うべき「原状回復」の内容,程度について,あらかじめ予測することができない。現に本件でも,最終的に原告が実施したと主張する原状回復工事の程度内容が,まさに「原状回復」に相当するものであるのか自体が熾烈に争われているのであるし,後記のとおり,その点を批判する被告らの主張にも,相応の理由があると認められるのである。 このように,当事者間で原状回復義務の範囲,程度やその存否が争われているような場合に,賃借人において,賃貸人が主張するとおりの「原状回復」を履行しない限り,半永久的に賃貸物件の明渡し自体が終わらず,賃借人は賃貸人に対し,賃料その他の諸経費相当額の支払義務を負い続けるなどと解することは,余りに不合理である。しかも当事者間では,そのように紛争性の高い原状回復費用をも担保する趣旨で,敷金の授受がなされているのであるから,賃貸人が,賃借人の主張する原状回復の程度では不足と主張するのであれば,自ら原状回復工事を実施した上,当該敷金をもってその費用に充てるなどした後に,双方が敷金の返還もしくは不足金の支払を巡って,まさに本訴のような事後的な金銭の支払請求をすることにより,その精算を図ることは十分可能である。 かかる事情を考慮すれば,本件各賃貸借契約のように,特約として「明渡し」の定義自体として,原状回復を履行した上での明渡しをなすべきことが定められている場合であっても,当該原状回復の内容について,賃借人が一義的に把握できる程度の明確な定めが予め置かれていない限り,そこで求められる「原状回復」とは,賃借人が一般的になすべき程度の原状回復のことを指すものというべきであり,それが当事者の合理的意思にも合致するものというべきである。 |
|
【解釈B】を採用した裁判例(事業者間の賃貸借契約の場合)の中には、原状回復未了では、明渡しを認めないものもあります。
この場合、賃借人は、賃貸人に対して、原状回復工事完了まで使用損害金を支払う必要が生じます。
| 東京地判平成20年3月10日(平17(ワ)22396号敷金返還等請求事件(本訴事件)、平18(ワ)8069号反訴請求事件(反訴事件)、ウエストロー・ジャパン) | |
|
本件賃貸借契約(乙1号証)によれば,原告は,本件建物のうち原告において修理,改造,模様替えなどをした箇所については原告の負担で原状に回復した上で本件建物を被告に明け渡すとされているが(第11条),そうではない箇所については修理,清掃して原状に回復するとだけあり(第14条),このような一般の原状回復工事と明渡時期との先後関係については,特に明示の約定は存在していないことが認められる。 ただし,上記のような本件賃貸借契約における各条項の先後関係や内容の趣旨を考慮すれば,本件においては,原告が負担すべき原状回復工事については,これを実施した後に被告に本件建物を明け渡す趣旨の契約であると考えるのが相当である。したがって,本件賃貸借契約においては,原告は,原告が実施すべき原状回復工事を完了して本件建物を引き渡すまでは,本件建物の明渡があったものとはいえないというべきである。 |
|
| 東京地判平成23年11月25日(平22(ワ)47700号保証金返還請求事件、ウエストロー・ジャパン) | |
| 本件賃貸借契約によれば,原告は,本件各建物を原状に復した上で明け渡すものとされており,また,本件各建物を明け渡す際には,本件事務所の1階~4階について,ハウスクリーニングを実施することとされている(甲2)。そうすると,被告は,本件各建物について,上記原状回復及びハウスクリーニングを実施した上で,本件各建物を明け渡さなければ,本件各建物を明け渡したことにならないものと解するのが相当である。 | |
契約書の「原状回復のうえ明け渡す」条項の解釈(まとめ)
| 解釈A | 解釈B | |
| 賃借人には明渡前に原状回復する義務があることを確認にした確認条項に過ぎない。 | 原状回復しない限り、明渡しは完了しないという「特約」である。 | |
|
原状回復の有無は、明渡し完了に影響しない。 つまり、民法通りです。 |
原状回復の有無が、明渡し完了に影響する。 つまり、民法の原則を変更する「特約」です。 |
|
| ▼ | ||
| 賃借人が消費者の場合 | 賃借人が事業者の場合 | |
| 消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)により無効な特約になり得る。 |
契約自由の原則から、有効な特約とされる可能性もある。 結論は事案による。 |
|
契約書の条項で、複数の解釈が成り立つと面倒
そこで、皆様にお願いしたいのは、次の3点です。
- 各条項について、複数の解釈が成り立つような契約書を作らない。
- 各条項について、複数の解釈が成り立つような契約書には押印しない。
- 契約書の作成や精査は、専門家である司法書士に依頼する。
参考文献
以下の書籍等を参照しました。
- 渡辺晋(弁護士)著『実務家が陥りやすい借地借家の落とし穴』新日本法規出版/2020/207頁
- 水本浩 (元立教大学教授),澤野順彦 (弁護士),内田勝一 (早稲田大学教授)編『借家の法律相談第3版補訂版』有斐閣/2002/430頁
- 法律実務研究会(編集)齋藤重也、佐脇敦子、山田博(編集代表)『社会生活六法』新日本法規/1993/384ノ3頁
 企業・事業者向けサービス
企業・事業者向けサービス
 トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)
トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)


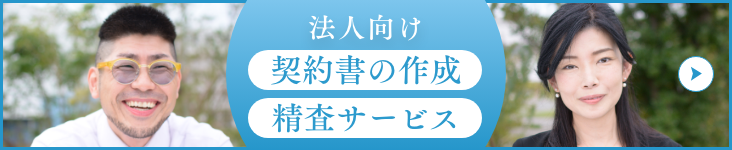


















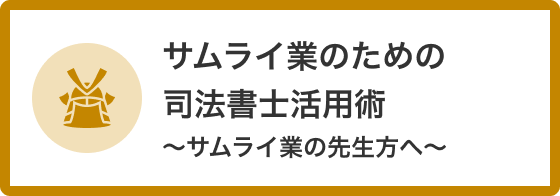
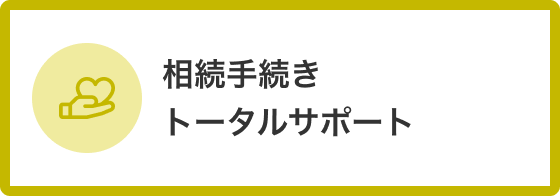
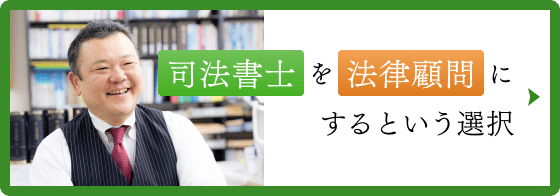
 個人向けサービス
個人向けサービス