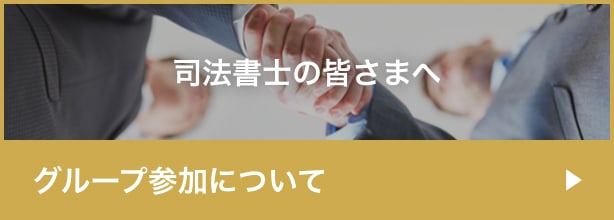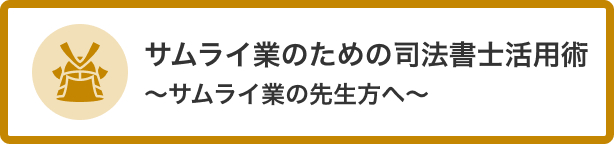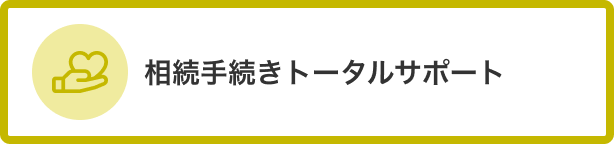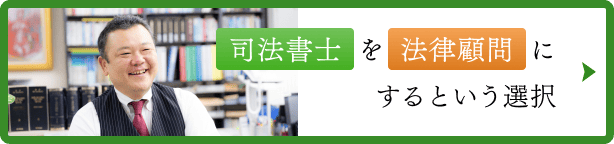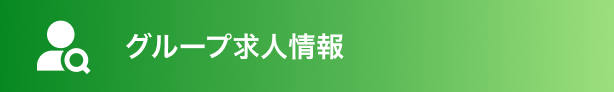- トラブル解決総論
- 相続・遺産分割トラブル解決
- 夫婦子供のトラブル解決
- その他親族トラブル解決
- 企業・事業者のトラブル解決
- 不動産・借地借家・隣近所のトラブル解決
- 不動産の取得時効と登記の関係
- 不動産賃貸借における関西方式・関東方式
- 敷金・保証金・建設協力金の違い
- 賃貸借契約の当事者が変更した場合、誰が誰に敷金を返せば良いか?
- 敷引特約の有効性
- 賃貸借契約で「中途解約を禁止する条項」は有効か?
- 賃貸借契約における更新料条項の有効性、更新料不払いの効果、法定更新との関係ほか後日もめないための具体的な対策
- 賃貸借契約で遅延損害金を年14.6%とする条項は有効か?
- 明渡しが遅れたときに賃料倍額の使用損害金を請求する条項は有効か?
- 滞納賃料(家賃・地代)の請求を受けた連帯保証人の対応
- 借主の軽微な契約違反だけでは解除できない賃貸借契約「信頼関係破壊の法理」
- 家賃滞納による建物明渡請求
- 賃借人が連帯保証人を立てない場合、賃貸人は賃貸借契約を解除できるか?!
- 賃料(地代・家賃)増減額請求
- 借地に関する契約
- 借地権登記できない場合の「借地上の建物登記」民法177条の例外
- 建物賃貸借の契約期間を設定するときの注意点
- 借地上の建物を賃貸借するときの注意点
- 定期借家契約のメリットと注意点
- DIY型賃貸借契約のメリットと注意点
- 原状回復・敷金返還に関するトラブル解決
- 建物賃貸借で「通常損耗をも借家人負担とする」特約の有効性
- 原状回復義務と明渡義務の関係|原状回復が終わらないと、建物明渡し完了にならない?!
- マンションの滞納管理費・修繕費・積立金の回収
- マンション義務違反者への対応
- 連棟建物(長屋、二戸一、三戸一)の切り離しトラブル
- マンション上階や二戸一の隣家からの水漏れトラブル解決
- 隣近所とのトラブル解決
- 隣地の建築計画はどこで確認するか?!宅地開発から建物建築までの流れ
- 建物建築に際しての周辺住民への説明義務
- 隣地が境界ギリギリに建築するのを止められませんか?!
- 崖地の擁壁・石垣の補修に関するトラブル【図解】
- 隣地に対する目隠し設置請求権
- 境界トラブル(筆界と所有権界)
- 私道の通行権をめぐるトラブル
- (ケガの後遺症や精神疾患などが原因で)騒音、大声、奇行などの問題行動をおこし周囲に迷惑をかけている方への対応(グループ会員限定記事)
- 交通事故解決
- 消費者トラブルの解決
- 借金が返済できないときの個人の債務整理(任意整理・民事再生・自己破産)
- 判決が出ても従わない相手方への強制執行による債権回収(差押え)
- 仮差押・仮処分など保全処分
- 刑事事件(被害者・加害者)
- 少年事件(被害者・加害者)
賃料(地代・家賃)の増減額請求|不動産賃貸借契約
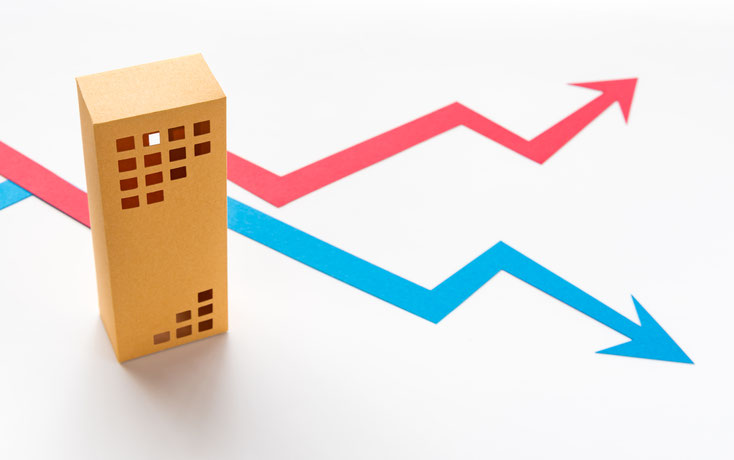
不動産オーナーの皆様、物価等が上昇しつつあるときは、賃料増額請求のチャンスかもしれません。
賃借人の皆様、物価等が上昇しつつあるときは、賃料増額請求を受けることが多いと思います。
反対に、物価等が下落しているときや、周辺のテナント賃料が下落しているときは、賃料減額請求が多く行われます。
この記事では、賃料増額請求、賃料減額請求を行う方法、請求を受けた場合の対応について、解説しています。
| もくじ | |
|
賃料増減額請求とは
賃貸人(家主/地主)にも、賃借人(借主)にも認められる権利です。
賃料増減額請求とは、賃貸借契約において、①経済事情の変動や近隣相場との比較などの事情の変更により、②現在の賃料が不相当となった場合に、賃貸人(家主/地主)または賃借人(借主)が将来に向かって賃料の増額または減額を相手方に請求できる権利です。
それぞれ次の法律が規定しています。
土地の賃貸借(借地)について:借地借家法11条
建物の賃貸借(借家)について:借地借家法32条
条文は、後ほど掲載します。
効力発生時期
賃料増減額請求は、その意思表示が相手方に到達した時点から、将来に向かって効力が生じます。
× 過去の賃料が安かったという理由で、過去分からの値上げは認められません。
× 過去の賃料が高かったという理由で、過去分からの値下げは認められません。
特徴(形成権)
賃料増減額請求は、一方的な意思表示で効力が発生する形成権であり、相手方の同意がなくても、裁判がなくても、効力が生じます(最判昭和32年9月3日民集第11巻9号1467頁、最判昭和36年2月24日民集第15巻2号304頁、 最判昭和43年6月27日集民第91号517頁、最判昭和45年6月4日民集第24巻6号482頁など)。
賃料増減額請求を受けた後、具体的にいくら支払えば良いのかは、後ほど、この記事の項目「増減額請求を受けた後の賃料の支払い」で説明します。
賃料増減額請求の要件
土地賃貸借、建物賃貸借どちらの場合も、賃料の増減額請求するためには下記2つの要件を両方とも充たす必要があります(借地借家法11、同32)。
➊事情の変更があったこと
➋現行賃料が不相当になったこと
もう少し情報を加えると下表のとおりです。
|
土 地 の 場 合 |
要件➊下記のような事情の変更【1】
|
+ | 要件➋現行賃料が不相当になったこと【2】 | |
|
建 物 の 場 合 |
要件➊下記のような事情の変更【1】
|
+ | 要件➋現行賃料が不相当になったこと【2】 |
| 借地借家法第11条(地代等増減請求権) | |
|
|
| 借地借家法第32条(借賃増減請求権) | |
|
|
【1】事情の変更とは?
事情の変更(借地借家法11条1項本文、同32条1項本文)は限定列挙か?
判例は「同項所定の諸事情(租税等の負担の増減、土地建物価格の変動その他の経済事情の変動、近傍同種の建物の賃料相場)のほか、賃貸借契約の当事者が賃料額決定の要素とした事情その他諸般の事情を総合的に考慮すべきである」としています(後掲・最判平成17年3月10日)。
「直近合意賃料が、当時の相場と乖離していた」というのは考慮すべき事情か?
直近合意賃料(今、合意して支払っている賃料)は、当事者が自由に設定できる(契約自由の原則)ため、たとえその額が合意当時の賃料相場と乖離していたとしても、借地借家法が介入すべきものではない(考慮すべき事情ではない。)というのが、判例の傾向です。
|
最判平成17年3月10日(集民216号389頁、裁判所ウェブサイト、判タ1179-185、ウエストロージャパン) |
|
|
借地借家法32条1項の規定は、強行法規であり、賃料自動改定特約等の特約によってその適用を排除することはできないものである(最高裁昭和28年(オ)第861号同31年5月15日第三小法廷判決・民集10巻5号496頁、最高裁昭和54年(オ)第593号同56年4月20日第二小法廷判決・民集35巻3号656頁、最高裁平成14年(受)第689号同15年6月12日第一小法廷判決・民集57巻6号595頁、最高裁平成12年(受)第573号、第574号同15年10月21日第三小法廷判決・民集57巻9号1213頁、最高裁平成14年(受)第852号同15年10月23日第一小法廷判決・裁判集民事211号253頁参照)。そして、同項の規定に基づく賃料減額請求の当否及び相当賃料額を判断するに当たっては、同項所定の諸事情(租税等の負担の増減、土地建物価格の変動その他の経済事情の変動、近傍同種の建物の賃料相場)のほか、賃貸借契約の当事者が賃料額決定の要素とした事情その他諸般の事情を総合的に考慮すべきである(最高裁昭和43年(オ)第439号同44年9月25日第一小法廷判決・裁判集民事96号625頁、上記平成15年10月21日第三小法廷判決、上記平成15年10月23日第一小法廷判決参照)。 本件建物は、賃借人の要望に沿って建築され、これを大型スーパーストアの店舗以外の用途に転用することが困難であるというのであって、本件賃貸借契約においては、賃貸人が将来にわたり安定した賃料収入を得ること等を目的として本件特約が付され、このような事情も考慮されて賃料額が定められたものであることがうかがわれる。しかしながら、本件賃貸借契約が締結された経緯や賃料額が決定された経緯が上記のようなものであったとしても、本件賃貸借契約の基本的な内容は、賃貸人が賃借人に対して本件建物を使用収益させ、賃借人が賃貸人に対してその対価として賃料を支払うというもので、通常の建物賃貸借契約と異なるものではない。したがって、本件賃貸借契約について賃料減額請求の当否を判断するに当たっては、前記のとおり諸般の事情を総合的に考慮すべきであり、賃借人の経営状態など特定の要素を基にした上で、当初の合意賃料を維持することが公平を失し信義に反するというような特段の事情があるか否かをみるなどの独自の基準を設けて、これを判断することは許されないものというべきである。 原審は、上記特段の事情の有無で賃料減額請求の当否を判断すべきものとし、専ら公租公課の上昇及び上告人の経営状態のみを参酌し、土地建物の価格等の変動、近傍同種の建物の賃料相場等賃料減額請求の当否の判断に際して総合考慮すべき他の重要な事情を参酌しないまま、上記特段の事情が認められないとして賃料減額請求権の行使を否定したものであって、その判断は借地借家法32条1項の解釈適用を誤ったものというべきである。 |
|
【2】不相当となったとは?
現行賃料が「不相当となったこと」も、賃料増減額請求の要件です。
現行賃料と適正賃料との乖離が小さい場合
「不相当となった」要件を欠く(すなわち賃料増減額請求権がない)と判断される可能性もあります(東京地判平成23年5月20日ウエストロージャパン:250万円の従前賃料を適正賃料251万円と判断したうえ、不相当ではないとして請求を棄却した事例)。
現行賃料が不相当に高額な場合
「現行賃料が客観的に見て不相当に高額な場合において、近隣の賃料相場の上昇など、本来であれば賃料を増額すべき事情変更が生じたというケースも問題となる。これまで述べてきたことからすれば、増額請求を認めるべきとも思えるが、事情変更によって現行賃料の額が相対的に低下したことで不相当さが是正されているのに、事情変更を理由に増額を認めると、かえって不相当さが維持されることになりかねない。よって、このようなケースでは、現行賃料が「不相当となったこと」の要件を満たさないものとして、増額請求は認めるべきではないと思われる(弁護士・中小企業診断士伊藤英之『企業が押さえておきたい賃料増額請求対応の基礎知識』Lexis Nexis「BUSINESS LAW JOURNAL 2019年7月号 No.136(2019年)74頁)
賃料増減額請求の方法
次の手順で行います。
- 「賃料の増額請求をしない」特約がないか契約書を確認します。
- 賃料増減額請求の理由があるか、資料を収集します。
- 請求する際は、証拠を残すため、配達証明付きの内容証明郵便で行うのが一般的です。
【1】「賃料の減額請求をしない」旨の特約は無効です(借地借家法11条、32条の規定は、強行規定とされているためです。最判平成16年6月29日集民214-595)。
賃料増減額請求を受けた場合の対応
契約書に「一定期間、賃料増額しない」特約が無いか確認する。
契約書に「一定期間、増額しない」旨の特約がある場合、その期間は、増減額請求はできません(借地の場合:借地借家法11Ⅰただし書、借家の場合:借地借家法32Ⅰただし書)。
「賃料の減額請求をしない」旨の特約は無効です(借地借家法11条、32条の規定は、強行規定とされているためです。最判平成16年6月29日集民214-595)。
請求内容の確認
請求の理由(近隣相場の変動、固定資産税の増減、物価の変動等)や、具体的な増減額、適用開始時期などを確認しましょう。
不動産鑑定士に意見を求めるのも、良い方法です。
請求を受けた側の選択肢
増額請求を受けた賃借人の対応
- 増額請求された金額をそのまま支払う。
☛合意書を作成しましょう。 - 従前どおりの金額を支払い続ける。
☛応じられない場合には、その旨を書面で回答します。 - 適正賃料について交渉する。
☛交渉で合意が成立した場合には、合意書を作成しましょう。
減額請求を受けた賃貸人の対応
- 減額請求に応じて減額する。
☛合意書を作成しましょう。 - 従前どおりの金額を請求し続ける。
☛応じられない場合には、その旨を書面で回答します。 - 適正賃料について交渉する。
☛交渉で合意が成立した場合には、合意書を作成しましょう。
応じられないときはその旨を回答する。
応じられないときには、その旨を回答します。
回答は、証拠として残すために、配達証明付きの内容証明郵便をおすすめします。
回答する場合には①全く応じられない(ゼロ回答)のか、②少しなら増減額に応じられるのか、明記しましょう。
合意できたら書面を作成する。
後日問題が生じないように、合意が成立したら、合意書を作成します。
賃料増減額請求に相手方が応じない場合の対応
交渉が成立しない場合には、調停を申し立てます。
調停前置
- 賃料増減額請求について、訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければなりません(民事調停法24の2Ⅰ)。
- 調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、その事件を調停に付さなければなりません。ただし、裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない(民事調停法24の2Ⅱ)。
訴訟
- 調停で合意に達しないときは、訴訟を提起します。
- 調停が不調になったときでも、自動的に訴訟に移行するという訳ではありません。
賃料増減額請求を受けた後の賃料の支払い
賃料増額請求を受けた賃借人の場合
賃借人は、裁判で増額が正当と確定するまでは、相当と認める額の賃料を支払えば足ります。ただし、相当と認めて支払っていた賃料が、裁判所が認定する適正賃料に不足していた場合、賃借人は、賃貸人に対して、年1割の利息をつけて支払う必要があります(借地の場合:借地借家法11Ⅱ、借家の場合:借地借家法32Ⅱ)。
賃料減額請求を受けた賃貸人の場合
賃貸人は、裁判で減額が正当と確定するまでは、相当と認める額の賃料を請求できます。ただし、相当と認めて支払ってもらっていた賃料が、裁判所が認定する適正賃料を超えていた場合、賃貸人は、賃借人に対して、年1割の利息をつけて返還する必要があります(借地の場合:借地借家法11Ⅲ、借家の場合:借地借家法32Ⅲ)。
「相当と認める額」とは
法律上、明確な基準が定められているわけではなく、当事者が事情を踏まえて主観的に判断した金額で結構です。
今の賃料が、公租公課を下回ることを知っていた賃借人が、賃料増額請求を受けた後も、今の賃料と同額を支払っていた場合、相当賃料の支払をしたとはいえない(すなわち賃借人には債務不履行がある)とした判例(最判平成8年7月12日民集50巻7号1876頁)もありますので、ご注意ください。
また、賃料の増額請求を受けた場合において、今の賃料を下回る額を支払っても「相当と認める額」とは認められません。
増額後の賃料でなければ受領しないと言われた賃借人は「供託」
賃料増額請求がなされ、賃借人が実際に賃料を支払おうとしたのに、賃貸人が「増額後の賃料でなければ受領しない」と、賃料の受領を拒否した場合、賃借人は従前賃料を法務局に供託します(民法494Ⅰ①)。
供託は、賃借人が、債務不履行責任を免れるために必要です。
広島法務局HP「地代、家賃の受領を拒否された場合にする供託」最終アクセス250527
賃貸人による「供託金」の受領
賃貸人は供託された金銭をいつでも引き出せますが、無条件で受け取ると「増額を撤回し、従前賃料を認めた」と判断されるリスクがあります。そのため、受領時には「供託金は賃料の一部として受領する」と内容証明郵便などで明記しておくことが実務上重要です。
賃料増減額請求の前提知識(独自の用語)
新規賃料(しんき・ちんりょう)
新たに賃貸借契約を締結する場合、一般の賃貸市場で成立するであろう賃料のことです。
いわゆる「正常賃料」とも呼ばれ、市場原理に基づく現在の相場を反映した賃料です。
新規契約時の「一時点」のみを考慮して決定されます。
継続賃料(けいぞく・ちんりょう)
既存の賃貸借契約が継続している場合、当事者間で成立するであろう賃料のことです。
現行賃料を前提に、契約継続中の特定の当事者間での経済価値を適正に考慮したうえで算出される賃料のことです。
「直近合意時点」から「現在時点(価格時点)」までの事情変更を考慮し、過去と現在の二時点間の関係性を重視して決定されます。
例えば、10年前に賃料10万円(適正な賃料)で始まった賃貸借契約で、賃貸人が賃料増額請求をした場合、現時点の新規賃料が15万円であったとしても、継続賃料は15万円にはなりません。
継続賃料は、新規賃料よりも、緩やかに上昇します。
直近合意賃料(ちょっきんごうい・ちんりょう)
当事者が最後に現行賃料について「現実の合意」をした時点の賃料です。
賃料増減額請求の際、この直近合意賃料が基準となり、経済事情等の変動により不相当となったかが判断されます。
単なる自動更新や機械的な合意更新ではなく、実質的な賃料交渉・合意があった時点の賃料を指します。
下記、重要な最高裁判決があります。
| 最判平成20年2月29日集民227-383、裁判所ウェブサイト、判タ1267号161頁 | |
|
〔裁判要旨〕 賃料自動改定特約のある建物賃貸借契約の賃借人から借地借家法32条1項の規定に基づく賃料減額請求がされた場合において、当該請求の当否及び相当賃料額を判断するに当たり、上記特約による改定前に賃貸借契約の当事者が現実に合意した直近の賃料を基にして、その合意された日から当該請求の日までの間の経済事情の変動等を考慮しなければならないにもかかわらず、上記特約によって増額された賃料を基にして、増額前の経済事情の変動等を考慮の対象から除外し、増額された日から当該請求の日までの間に限定して、その間の経済事情の変動等を考慮した原審の判断には、違法がある。 (上記裁判要旨は、ウエストロージャパン。) |
|
直近合意時点
現行賃料について当事者間で「現実の合意」が成立し、その賃料が適用された時点のことです。
この時点が賃料増減額請求における基準時点となり、以後の経済・社会事情の変動等を踏まえて賃料の相当性が判断されます。
適正な賃料の算定のためには「現行賃料が決まった時点」以降に生じた事情変更だけ考慮すれば足りるということです。
直近合意時点は「当事者が、その時点で、その当時の経済事情等を踏まえることなく、単に従前の賃料額を確認したにとどまるような場合には、当該時点を直近合意時点にあたるとはいえない。」と判示していますが、あくまで下級審裁判例です(神戸地判平成30年2月21日判決)。
賃料増減額請求の流れ
基本的に賃料増減額請求を受けた場合も対応は同じですので、ご参照ください。
ご相談
次の情報をお知らせください。
- 賃貸借物件の情報(賃貸借契約書をいただければ幸いです。)
- 現在の賃料(共益費込み)
- 現在の賃料になったのは、何年何月からか?

不動産鑑定士によるチョイ聞きサービス
司法書士から提携先の不動産鑑定士に意見を聞きます。
(この時点では、不動産鑑定士に対する費用は発生しません。)

どれくらいの賃料に増減額するのか相談
この時点では、不動産鑑定士の意見を相手方に伝えないようにしましょう。
相手方も不動産鑑定士に依頼することになり、基本的に後出しの方が、先の意見書の穴を突ける分有利だからです。

示談交渉
賃料増減額請求は、請求したときから効力を発揮しますので、通常は内容証明で請求します。

調停前置
賃料増減額請求は、できるだけ話合いによる解決を図ることが適切であるとの趣旨から、調停前置主義がとられています(民調法24条の2第1項)。なお、調停前置に違反して訴訟提起した場合は、原則として、受訴裁判所により調停に付されることになります(同条2項)。

訴訟
司法書士が代理で交渉・訴訟できる範囲
司法書士に代理権があるか否かは、訴訟物の価額で判断します。
そこで、まずは賃料増減額請求の訴訟物の価額の算定方法を確認します。
なお、訴訟物の価額は、調停や訴訟の際、申立書、訴状に貼り付ける印紙代も決定します。
訴訟物価額の算定基準(経済的利益の額)
1か月当たりの賃料差額 × (増額又は減額の始期から訴え提起までの期間+12か月)
ただし、訴え提起時に、原告が目的不動産の価額の2分の1の額の方が低額であることを疎明したときは、その額。
- 「増額又は減額の始期から訴え提起までの期間+12か月」に1か月未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てる。
- 原則的な取扱いによるときは、疎明は不要である。
- ただし書の目的不動産の価額の疎明方法は、1を参照〔筆者注:土地=固定資産評価証明書の価額の2分の1、建物=固定資産税評価証明書の価額。〕
司法書士が代理権を行使できる期間(期限)
司法書士の代理権は、140万円以下に限定されています。
賃料増額(減額)請求の訴額は、期間が経過すれば大きくなりますので、司法書士の代理権に期限がある珍しいケースです。
140万円 ≧ 1か月当たりの賃料差額 × (増額又は減額の始期から訴え提起までの期間+12か月)
司法書士の代理権の期限は、次のとおり計算できます。
<司法書士の代理権の期限の計算方法>
(増額又は減額の始期から訴え提起までの期間)
=(140万円 ÷ 1か月当たりの賃料差額) - 12か月
=○か月
<検算>
下の計算式の「増額又は減額の始期から訴え提起までの期間」に計算結果「○か月」を入れて計算したときに、140万円になれば、計算結果は正確です。
1か月当たりの賃料差額 × (増額又は減額の始期から訴え提起までの期間+12か月)
<計算結果>
-(マイナス)になった場合:司法書士には、(一瞬たりとも)代理権はありません。不動産訴訟に強い弁護士を紹介します。
+(プラス)になった場合:その期間が不十分な場合には、賃料増減額請求は調停前置ですので、簡裁訴訟まで見据えて頑張りたい依頼者様のときには、厳しいです(最初から弁護士をご紹介します。)。
司法書士の報酬・費用
| 業務内容 | 司法書士の報酬 | 実費 | |
| 賃料増減額請求書の作成(ご本人名) | 55,000円(税込) | 内容証明費用 | |
|
賃料増減額請求への回答書の作成発送 (ご本人名) |
55,000円(税込) | 内容証明費用 | |
| 合意書作成 | 110,000円(税込) | ||
| 示談折衝 | 着手金 | 165,000円(税込) | |
| 成功報酬 | 増減額賃料×1年分×11% | ||
| 調停申立 | 着手金 | 220,000円(税込) | 印紙切手20,000円ほど |
| 日当 | 16,500円(税込)/回×3~5回 | 交通費など | |
| 成功報酬 |
増減額賃料×1年分×16.5% |
||
| 訴訟 | 追加着手金 | 110,000円(税込) |
印紙切手20,000円ほど 不動産鑑定士報酬 |
| 成功報酬 | 増減額賃料×1年分×16.5% | ||
参考文献等
この記事を執筆するために、以下の書籍等を参考にしました。
- 稻本洋之助 澤野順彦 編『コンメンタール借地借家法[第4版]』(日本評論社、2019年)
- 弁護士・中小企業診断士伊藤英之『企業が押さえておきたい賃料増額請求対応の基礎知識』Lexis Nexis「BUSINESS LAW JOURNAL 2019年7月号 No.136(2019年)74頁
人気の関連ページ
- 不動産賃貸借トラブル
-
- 不動産賃貸借契約書の作成・精査
- 期間満了による契約書の更新
- 不動産賃貸借における関西方式・関東法式
- 敷金・保証金・建設協力金の違い
- 権利金・礼金とは
- 賃貸借契約の当事者が変更した場合、誰が誰に敷金を返せば良いか?
- 敷引特約の有効性
- 賃貸借契約で「中途解約を禁止する条項」は有効か?
- 賃貸借契約における更新料条項の有効性、更新料不払いの効果、法定更新との関係ほか後日もめないための具体的な対策
- 賃貸借契約で遅延損害金を年14.6%の定めは有効か?
- 明渡しが遅れたときに賃料倍額の使用損害金を請求する条項は有効か?
- 滞納賃料(地代・家賃)の回収
- 滞納賃料(地代・家賃)の支払請求を受けた連帯保証人の対応
-
- 賃貸借契約の解除「信頼関係破壊の法理」借主の軽微な契約違反では解除できない
- 家賃滞納による建物明渡請求
- 滞納賃料(地代・家賃)の支払請求を受けた連帯保証人の対応
- 無断譲渡・無断転貸による明渡請求
- 賃借人が連帯保証人を立てない場合、賃貸人は解除できるか?!
- 賃借人が借家人賠償責任保険(火災保険)に加入しない場合、賃貸人は解除できるか?
- 賃料(地代・家賃)増減額請求事件
-
- 借地に関する契約
- 借地権登記できない場合の「借地上の建物登記」民法177条の例外
- 借地上建物を取り壊したときの「借地借家法10条2項の掲示」民法177条の例外
- 借地非訟事件
-
- 借家に関する契約
- 建物賃貸借の契約期間を設定するときの注意点
- 借地上の建物を賃貸借するときの注意点
- 居抜き物件を賃貸借するときの注意点
- 定期借家契約のメリットと注意点
- DIY型賃貸借契約のメリットと注意点
- 原状回復・敷金返還に関するトラブル解決
- 建物賃貸借で「通常損耗をも借家人負担とする」特約の有効性
- 原状回復義務と明渡義務との関係|原状回復が完了しないと明渡完了にならないか?
 企業・事業者向けサービス
企業・事業者向けサービス
 トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)
トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)



















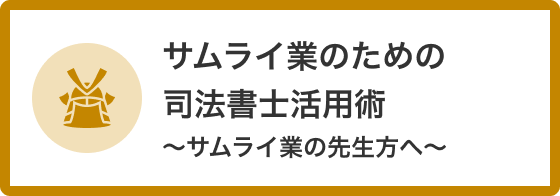
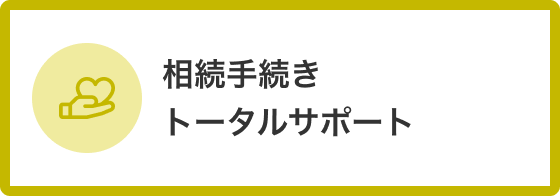
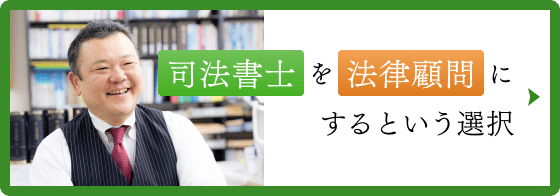

 個人向けサービス
個人向けサービス