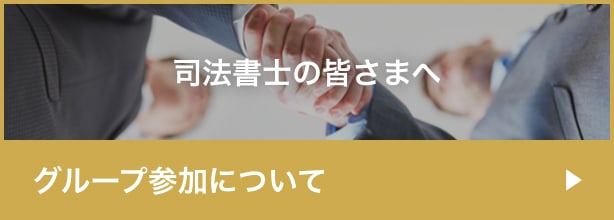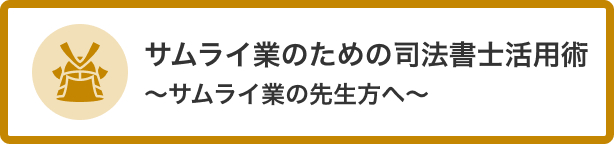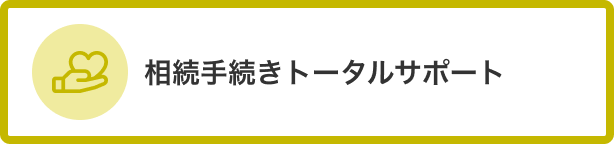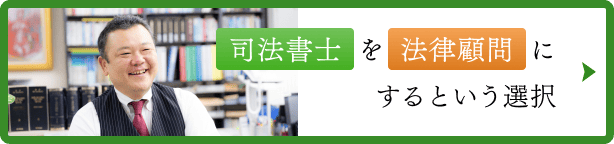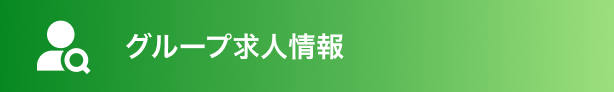- トラブル解決総論
- 相続・遺産分割トラブル解決
- 夫婦子供のトラブル解決
- その他親族トラブル解決
- 企業・事業者のトラブル解決
- 不動産・借地借家・隣近所のトラブル解決
- 不動産の取得時効と登記の関係
- 不動産賃貸借における関西方式・関東方式
- 敷金・保証金・建設協力金の違い
- 賃貸借契約の当事者が変更した場合、誰が誰に敷金を返せば良いか?
- 敷引特約の有効性
- 賃貸借契約で「中途解約を禁止する条項」は有効か?
- 賃貸借契約における更新料条項の有効性、更新料不払いの効果、法定更新との関係ほか後日もめないための具体的な対策
- 賃貸借契約で遅延損害金を年14.6%とする条項は有効か?
- 明渡しが遅れたときに賃料倍額の使用損害金を請求する条項は有効か?
- 滞納賃料(家賃・地代)の請求を受けた連帯保証人の対応
- 借主の軽微な契約違反だけでは解除できない賃貸借契約「信頼関係破壊の法理」
- 家賃滞納による建物明渡請求
- 賃借人が連帯保証人を立てない場合、賃貸人は賃貸借契約を解除できるか?!
- 賃料(地代・家賃)増減額請求
- 借地に関する契約
- 借地権登記できない場合の「借地上の建物登記」民法177条の例外
- 建物賃貸借の契約期間を設定するときの注意点
- 借地上の建物を賃貸借するときの注意点
- 定期借家契約のメリットと注意点
- DIY型賃貸借契約のメリットと注意点
- 原状回復・敷金返還に関するトラブル解決
- 建物賃貸借で「通常損耗をも借家人負担とする」特約の有効性
- 原状回復義務と明渡義務の関係|原状回復が終わらないと、建物明渡し完了にならない?!
- マンションの滞納管理費・修繕費・積立金の回収
- マンション義務違反者への対応
- 連棟建物(長屋、二戸一、三戸一)の切り離しトラブル
- マンション上階や二戸一の隣家からの水漏れトラブル解決
- 隣近所とのトラブル解決
- 隣地の建築計画はどこで確認するか?!宅地開発から建物建築までの流れ
- 建物建築に際しての周辺住民への説明義務
- 隣地が境界ギリギリに建築するのを止められませんか?!
- 崖地の擁壁・石垣の補修に関するトラブル【図解】
- 隣地に対する目隠し設置請求権
- 境界トラブル(筆界と所有権界)
- 私道の通行権をめぐるトラブル
- (ケガの後遺症や精神疾患などが原因で)騒音、大声、奇行などの問題行動をおこし周囲に迷惑をかけている方への対応(グループ会員限定記事)
- 交通事故解決
- 消費者トラブルの解決
- 借金が返済できないときの個人の債務整理(任意整理・民事再生・自己破産)
- 判決が出ても従わない相手方への強制執行による債権回収(差押え)
- 仮差押・仮処分など保全処分
- 刑事事件(被害者・加害者)
- 少年事件(被害者・加害者)

隣に建物の新築工事が進んでいる場合において、新築建物の窓が当家を覗けるようになっているときは、嫌ですよね。民法は、目隠しの設置請求権という権利を定めています。
この記事では、目隠しの設置請求権について、解説しています。
| もくじ | |
|
目隠し設置が認められるか分かるフローチャート
|
隣の窓・縁側・ベランダは、境界線から1m未満で、かつ、当方の宅地を見通すことができるか? 【1】 |
||||
| ▼ | ▼ | |||
| はい | いいえ | |||
| ▼ | ▼ | |||
|
民法235条に基づく目隠し設置請求が権利濫用に当たらないか?【2】 |
民法235条に基づく目隠し設置請求はできないが、総合的に検討して、覗き見によってプライバシーが侵害されるおそれが大きく、受忍限度を超える場合は「人格権ないしプライバシーの権利」に基づいて目隠しの設置を請求できることもある。【3】 |
|||
|
▼ |
▼ | |||
|
当たらない |
当たる | |||
|
▼ |
▼ | |||
|
民法235条に基づき目隠し設置請求できる |
目隠し設置請求はできない | |||
【1】目隠し設置について、民法235条と異なる慣習があるときは、慣習が優先します。
【2】権利濫用にあたるとされた例
- 窓から見えるのが屋根だけ
- 樹木があって見通しが利かない
- 隣は高層マンションであって殊更に下をのぞき込まない限り隣地を覗くことが困難
【2】「隣に目隠しをつけてもらえるか」社会生活六法112頁。裁判例を見ると、容易には認められていないことに注意が必要です。
法律に定められたルール
|
民法第235条 |
|
|
|
| 民法第236条(境界線付近の建築に関する慣習) | |
| 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 | |
裁判例
目隠し設置請求が認められたもの
令和7年4月29日、ウエストロージャパンを民法235条で検索したところ31件ヒットしました。このうち目隠し設置請求が認められたものは、次の15件です。
境界から窓までの距離が1m以上あるにも関わらず、目隠し設置請求が認められたものはゼロ件でした。
(要旨はウエストロー・ジャパン、抜粋は筆者によるものです。)
| 東京地判平成24年6月21日 | |
|
要旨 ◆原告が、その所有し居住する建物の隣接建物を所有し居住する被告に対し、主位的に境界線上に原告と共同で目隠しを設置することを求め、予備的に被告建物の2階ベランダ部分に目隠しを設置することを求めた事案において、被告建物のベランダは境界線から1メートル未満の距離にあり、原告建物の宅地を見通すことができるから、民法235条の適用があり、原告が被告に対して民法235条に基づく目隠し設置を請求することが権利濫用に当たるとはいえないとした上で、被告建物のベランダの位置や原告所有建物の窓の位置に加え、原告が同窓に目隠しを設置することも容易であることなど衡平の観点からみて、原告が請求する目隠しは過大であるとして、予備的請求を一部認容した事例 |
|
| さいたま地判平成20年1月30日 | |
|
要旨 ◆土地の境界線をはさんで、双方の土地に建物が建築され、いずれの建物も1メートル以内に窓が設置されている場合に、双方の土地の所有者が互いに民法235条に基づき目隠しの設置を求めたところ、一方の所有者の請求のみが認められ、他方の所有者の請求が権利濫用になるとされた事例
|
|
| 東京地判平成19年6月18日 | |
|
要旨
◆原告らが、隣地に地上六階建てのビルの建築を計画する被告に対し、サービスバルコニーに目隠しを設置することを求めた事案において、本件バルコニーは民法二三五条一項にいう「縁側(ベランダを含む。)」に当たるというべきであるが、目隠しの設置の位置、大きさ、材質等は観望を遮るに足るものであることが必要かつ十分というべきであるとして、その請求の一部を認容した事例 |
|
| 東京地判平成19年4月27日 | |
|
要旨
◆被告らが建設したマンションの隣地に建物を所有して居住する原告が、マンション建設に際して被告らが設置を約束したとする目隠しや防犯装置等の設備の設置を求め、また、被告らが本件合意の履行を怠ったことによる損害賠償を求めた事案において、本件合意は被告らから委任を受けた代理人が原告との間で締結したものであると認められるので被告らに対する拘束力があるとし、本件合意当時原告が期待していた防犯上の意味をもたなくなってしまっている設備を除く目隠し等の設備の設置及び慰謝料等の請求を認容した事例 |
|
| 東京地判平成17年10月27日 | |
|
要旨
◆他人の宅地を見通すことのできる窓への目隠し設置の請求に対して、異なる慣習の存在、権利濫用との主張が認められなかった事例 |
|
| 東京地判平成16年1月30日 | |
|
要旨
◆民法二三五条一項に基づく目隠し設置の請求が一部認められた事例 |
|
| 東京地判平成5年3月5日 | |
|
要旨
◆三階建アパートの窓及びベランダの一部について、民法二三五条に基づき、目隠設置請求が認められた事例 ◆本件小窓及び三階に設置されたベランダについては、通常の状態で原告A宅地内を眺望しうるものではないから、民法二三五条にいう「他人の宅地を観望すべき窓」に該当しないといわざるを得ない。さらに、二階ベランダと本件引戸窓のうち(6)、(12)及び(15)を除く窓については、原告B宅地内を眺望しうるものではなく、また、(6)及び(15)の本件引戸については原告A宅地内を眺望しうるものではないから、右各原告との関係においては、いずれも同様に、民法二三五条にいう「他人の宅地を観望すべき窓」に該当しないといわざるを得ない。しかしながら、本件引戸窓のうち(1)、(7)及び(12)の各窓及び二階ベランダからは原告A宅地内の一部を、本件引戸窓(6)、(12)及び(15)からは原告B宅地内の一部をそれぞれ眺望しうるものであるから、民法二三五条にいう「他人の宅地を観望すべき窓」に該当する。もつとも、本件引戸窓は、いずれも曇り硝子がはめこまれていて締め切つた状態では硝子を通して外部を見ることができないものの、右各窓はいわゆるはめ殺し窓ではなく、換気のため等の理由で開けることを日常的に予定されているものと考えられるから、本件引戸窓が曇りガラスであるというだけでは右の判断を左右するものではない。 |
|
| 東京地判平成3年1月22日 | |
|
要旨
◆建ぺい率・容積率には違反するが日影規制には違反しない第一種住居専用地域内の隣接建物による日照阻害等が受忍限度内であるとして建物の一部撤去請求を棄却し、目隠設置請求を認容した事例 |
|
| 京都地判昭和61年11月13日 | |
|
要旨
◆建築中の七階建分譲マンションについて、日照権及び生活権侵害等を理由とする建築禁止の仮処分申請は却下されたが、民法二三五条に基づく目隠しの設置を求める仮処分が一部認容された事例 |
|
| 東京地判昭和61年5月27日 | |
|
要旨
◆隣接の二階建居宅の二階の窓に目隠しの設置を命じたが、プライバシー侵害の慰藉料請求を認めなかつた事例 |
|
| 名古屋高判昭和56年6月16日 | |
|
要旨
◆マンションのベランダが民法二三五条一項の縁側に該当するとして目隠しの設置を命じた事例 |
|
| 大阪地判昭和56年2月4日 | |
|
要旨 ◆民法二三五条により窓に目隠しの設置が命ぜられた事例 |
|
| 名古屋地判昭和54年10月15日 | |
|
要旨
◆六階建マンションのベランダについて、民法二三五条一項の縁側に該当するとして目隠しの設置を命じた事例 |
|
|
抜粋 「以上の事実によれば、本件窓は、境界線までの距離の点において民法二三五条一項の要件を欠き、これに該当しないことは明らかであるけれども、本件ベランダは、同条項の縁側としてこれに該当するから、被告において目隠しを設置する義務がある。 被告は、民法二三五条一項にいう縁側とは、日本式木造家屋の内部に設けられ、居室の一部として利用されているものを指し、本件ベランダのように床面が外部に突き出し、洗濯物の干し場等としての効用をもつものとは、その構造、機能において根本的に異なるから、これに含まれない旨主張するけれども、本件ベランダも、縁側と同じく建物の一部に属し、居室の外側にある縁であることに変りがなく、手すりをもつて外部とも遮断され、居住者の生活上の各種用に供されているのであるから、右条項の縁側にあたることは明らかであり、右主張は採用のかぎりでない。」 |
|
| 大阪高判昭和52年9月12日騒音差止等仮処分申請事件〔枚方市駅前ビル屋上住居プライバシー事件・抗告審〕 | |
|
要旨
◆百貨店のビル屋上に設置された住居に居住する住民のプライバシーを保護するため、百貨店専有部分と住居との境界上に障壁設置の必要があると認めた事例 |
|
| 京都地判昭和42年12月5日 | |
|
要旨
◆民法二三五条一項の「観望スヘキ窓」の意義 ◆隣地を観望できるビルの窓に目隠し施設を命じた事例 |
|
|
抜粋 「被告は右窓はいづれも各階の階段、便所に設置されたもので通風、採光のためのものであつて、観望用のものでないと主張するので、この点につき判断するに、前記証拠によると、右窓はいづれも各階の便所及び階段に設置されていることが認められる。従つて右窓は主として通風、採光のために設置されたものと推認するに難くない。しかしながら民法第二三五条は、みだりに他人の私生活をのぞくことを制止する趣旨であるから、同条にいう「観望すべき窓」とは、特に観望の目的で設けたものと解すべきでなく、窓を設置した目的の如何を問わず、その窓から他人の宅地を観望することが物理的に可能であるような位置、構造を有する窓と解するのが相当である。」 |
|
関連裁判例
| 東京高判平成5年5月31日 | |
|
要旨
◆作業場所又は事務所に使用されている建物の敷地の所有者が、民法二三五条に基づき、隣接する建物の所有者に対し目隠しの設置を求めた事案につき、作業場所又は事務所の敷地が同条一項の宅地に該当しないとされた事例 |
|
| 東京地判平成19年7月27日 | |
|
要旨 ◆原告所有のマンションの隣に建築された一戸建て2棟についての建築確認が違法であったために原告の日照権等が侵害され損害を被ったとして損害賠償が請求された事案において、建築主事は申請書に基づき建築計画が建築基準関係規定適合性を形式的に審査すればよく現地調査を怠って建築確認をしたことが違法とはいえないこと、小平市建築物建築指導要綱(以下、小平市要綱という。)は建築基準関係規定に該当せず建築確認の審査において小平市要綱への適合性を考慮しなかったとしても違法とはいえないこと、建築主事は建築基準関係規定への適合性を審査する義務のみを負い私人間の実体上の権利義務関係の内容を審査する義務や権限を有しないので建築確認の審査において民法235条1項で要求される目隠しをしていないことが考慮されなかったとしても違法とはいえないこと等から、請求が棄却された事例 |
|
| 東京地判昭和60年10月30日 | |
|
要旨
◆建築工事による生活妨害につき損害賠償が認容された事例 ◆民法二三四条と建築基準法六五条との関係(特則) ◆双方の目隠設置請求につき先後関係を考慮した事例 |
|
|
抜粋 「原告土屋の建築した建物は被告山田隆一所有の建物に遅れて建築されたものであること、原告建物は境界線より二七・五センチメートル被告建物は八〇センチメートル離れていることが認められるから、このような場合には目隠し設置の請求はできないものと解するのが相当である。けだし、相隣関係に基づく互譲の精神から目隠し設置が義務づけられたものであるが、後で境界線に接近して建築した者から既存建物に対し目隠設置を請求するのはまさに互譲の精神にもとるからである。」 |
|
| 東京地判昭和56年12月25日 | |
|
要旨
◆マンションの階段から各区分住宅へ通ずる通路は民法二三五条所定の縁側又はこれと同列に扱うべき場所に当たらないとして、隣地所有者の右通路部分への目隠設置請求を棄却した事例 |
|
|
抜粋 「原告所有地と被告敷地との境界からの距離が民法235条の要件を満たすものではなく、同条に基づくところの右窓について目隠の設置を求める原告の請求は失当である。 この点について原告は、原告及び被告側の諸事情を考慮し相隣関係の法理から同条を類推適用すべきことを主張するが、同条において明確に一定の距離をもって要件としている以上、特段の事由のない限り右距離を安易に伸縮することは妥当でない。しかし、右窓からの観望により隣地居住者の生活が侵害される場合においては、被害者は加害者に対し前述日照被害の法理と同じ理由で、右窓に対する目隠の設置を求めうると解すべきところ、《証拠省略》によると、右(3)の窓は、被告建物の踊り場兼出入口、廊下という、通常、人の立ち止まることのない場所に設置され、しかも、右窓には曇りガラスがはめ込まれており、これを通じて原告建物を見透すことができない状況にあることを認めることができるから、このような状況下で、原告が被告に対し、更に、右窓に目隠の設置を求めることはできないというべきである。」 |
|
| 大阪地判昭和55年11月17日 | |
|
要旨
◆マンションの階段から各区分住宅へ通ずる通路は民法325条所定の縁側又はこれと同列に扱うべき場所に当たらないとして、隣地所有者の右通路部分への目隠設置請求を棄却した事例 |
|
| 東京地判昭和45年7月14日 | |
|
要旨
◆日照・通風を妨げる塀の撤去請求を認めた事例 |
|
|
抜粋 「本件工作物Bは、前記(二)の(3)認定のとおり、これによって遮断されている窓Bの部分からの、被告方の裏庭、居宅等の観望を防止するという目的達成に必要な限度を超えて、右部分から原告居宅内への日照、通風を殆んど全く遮断しており、かつ、本件工作物Aのように、原告居宅内からの被告方への観望を防止するとともに、原告居宅内への日照、通風を相当程度可能とする構造の遮断物を設置することが、本件工作物Bの設置に比して著しく多額の費用を必要とするとは考えられないことからすれば、本件工作物Bによって原告が受けている不利益は、前記のように窓Bに目穏設置義務を負っている原告としても甘受すべき程度を超えているということができる。 結論 以上のとおりであるから、原告の本件請求は、被告が設置した別紙第一物件記載の工作物のうちの、原告居宅一階東南側に作られた窓のうち東側の窓の前面に張られたベニヤ板の部分の徹去を求める限度においては理由があるが、右の限度を超える部分は理由がない。」 |
|
| 大阪高裁昭和42年9月18日 | |
|
要旨
◆相隣者の一方甲が隣地居住者乙との境界上に設けた囲障牆壁が必要な程度を超える規模構造のものである場合には、乙は相隣地・建物の占有権又は所有権に基づいてその一部の除去を請求できるとした事例 ◆右囲障牆壁が設置されたのは隣地居住者乙が甲の宅地・建物を観望する窓に目隠しを付置すべき義務を果さないためであつても、甲の右牆壁設置を正当とする理由にはならないとして、乙の牆壁一部除去請求を認めた事例 |
|
対処方法
建築中の場合
施主に引渡しされる前に、あなたから、工事会社に対して、請求しましょう。
工事会社が不誠実である場合には、施主に直接、依頼するのも良いです。
(工事会社から施主への)引渡し前であれば、工事会社は施主からの依頼であれば、聞いてくれる傾向にあります。施主に対しては「引渡し前なら、工事会社の費用負担で改善できるのではないか」という伝え方をすれば良いでしょう。
一方、引渡しが完了してしまうと、工事会社は、工事代金を受け取っていますので、施主からの依頼であっても、なかなか応じてくれなくなります。
人気の関連ページ
- 不動産賃貸借トラブル
-
- 家賃滞納による建物明渡請求
- 借地に関する契約
- 借地上の建物を賃貸借するときに注意すべき事項
- 短期賃貸借保護制度から明渡猶予制度へ
- 借家に関する契約
- 不動産賃貸借における関西方式・関東方式
- 居抜き物件を借りたときのトラブル
- 原状回復に関するトラブル
- 敷引特約の有効性
- 賃貸借契約における更新料条項の有効性、更新料不払いの効果、法定更新との関係ほか後日もめないための具体策
- 賃貸借契約における遅延損害金14.6%の定め、使用損害金を賃料倍額とする定めは有効か
- 不動産売買トラブル
-
- 地中埋設物に関するトラブル
- 不動産建築トラブル
- マンションのトラブル
-
- 区分建物(マンション)とは何か?!知らないと分からない区分所有法の特殊な規定ほか
- マンション管理規約の設定、変更または廃止の方法
- マンション共用部分に関する訴訟
- マンションの滞納管理費・修繕費・積立金の回収
- マンション義務違反者への対応
- マンション復旧、立替に関する訴訟
- マンション管理組合総会決議無効・不存在確認の訴え
- マンション管理者の解任請求
- マンション会計帳簿等閲覧謄写請求
- マンション改修工事への協力請求
- 連棟建物(長屋、二戸一、三戸一)の切り離しトラブル
- マンションや二戸一建物における水漏れトラブル
- 隣近所のトラブル
-
- 隣近所とのトラブル解決
- 隣近所とのトラブルの種類
- 雨水など通水トラブル
- 崖地の擁壁・石垣の補修に関するトラブル【図解】
- 騒音トラブル
- 境界トラブル(筆界と所有権界)
- 境界トラブル(筆界特定制度)
- 境界トラブル(境界確定訴訟)
- 境界トラブル(所有権確認訴訟)
- 私道の通行権をめぐるトラブル
- 共有私道の工事をめぐるトラブル
- 私橋の通行権をめぐるトラブル
- 猫への餌付け被害の回復
- ハト・スズメなど鳥への餌付けによる被害の回復
- 敷地への放置車両の撤去
- 司法書士による法律顧問サービス
 企業・事業者向けサービス
企業・事業者向けサービス
 トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)
トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)



















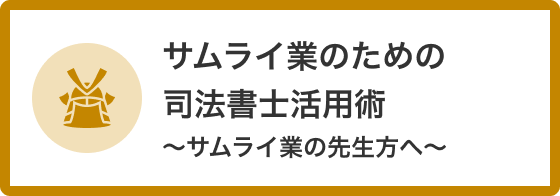
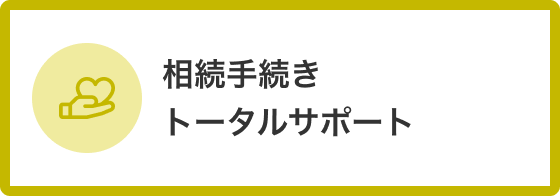
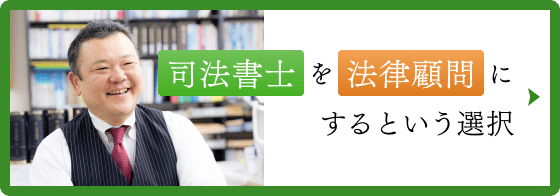

 個人向けサービス
個人向けサービス