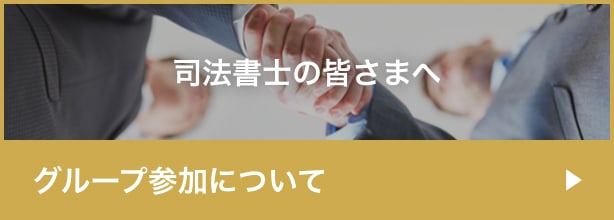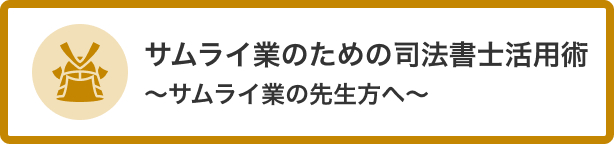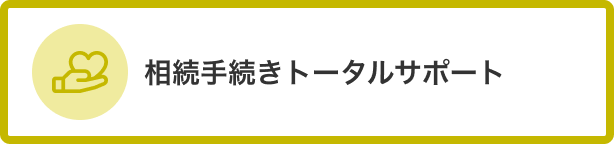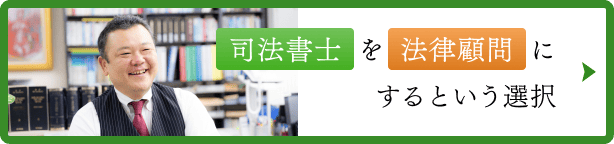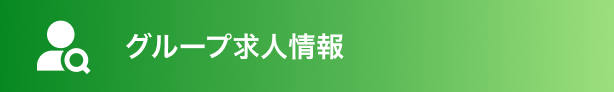- 不動産名義変更・不動産登記TOP
- 終活(成年後見・家族信託・遺言)TOP
- 相続手続き・遺産整理TOP
- ▼知ってお得な相続知識(もくじ)▼
- 相続クイズ50問(間違いだらけのネット情報)
- 自分で相続登記手続をした方に聞きました「相続手続で苦労した理由!ベスト10」
- 相続に関与しようとする民間資格や民間団体にご注意ください。
- 最期の時が近づいたとき(葬儀前に)ご家族が確認・準備するべきこと
- 相続開始直後(葬儀後すぐ)に行なうべき手続一覧
- 相続手続トータルサポート
- 遺言寄付の受け入れトータルサポート
- 相続は早い者勝ちになりました
- 相続登記・遺贈登記の特急申請(グループ会員限定記事)
- 銀行・信託銀行の相続手続は、本当に「質の悪いブランド品」なのか?!士業の相続手続と徹底比較!
- 法定相続情報~ややこしい戸籍を読むのは司法書士が一回で十分です。銀行預金の相続手続前に司法書士にご依頼ください。
- 相続による銀行口座凍結とは?!
- 銀行預金の仮払制度(遺産分割前の預金払戻し制度)
- ▼相続財産の調査(もくじ)▼
- 相続によって引き継ぐ財産・引き継がない財産(相続の対象財産)
- 行方不明の相続預金・相続貯金の探索
- 相続で負債・借金がないかの調査方法
- 被相続人の遺品の中から、相続人や第三者名義の通帳が出てきた場合どうすれば良いのか?(いわゆる名義預金の問題)
- 相続登記や遺言の際に欠かせない不動産の近隣地調査(名寄せ)
- 相続生命保険の調査
- ▼相続人の調査(もくじ)▼
- 相続人は誰か❶基本編(法定相続人・法定相続分)
- 相続人は誰か❷数次相続・再転相続・代襲相続の区別
- 子が親より(妻が夫より)①先に死亡したとき、②同時に死亡したとき、③死亡の先後が分からないときの相続(同時存在の原則、同時死亡の推定)
- 義父母の遺産を受け取る「特別寄与料制度」
- 相続手続のための戸籍収集
- 戸籍の広域交付制度とその盲点
- あなたの戸籍謄本(住民票)が取得されましたとの通知を受けた方へ:本人通知制度
- 旧民法(明治民法・応急措置法)による相続
- ▼相続税申告の要否▼
- ▼遺産分割協議(もくじ)▼
- 遺産分割協議書の基礎知識、作成の流れ
- 遺産分割協議の種類と流れ
- 遺産分割協議成立後、相続人の漏れに気付いた場合の対応方法[グループ会員限定]
- 遺産分割協議の期間制限
- 一次相続の遺産分割協議では、二次相続のことも考えましょう。
- 相続分の譲渡・相続分の放棄
- 平成13年6月までに相続開始又は代襲原因発生の場合は注意「非嫡出子の法定相続分」
- 特別受益証明書(相続分ないことの証明書)による相続登記が流行した理由、消滅した理由から、特別受益証明書の可能性を探る
- 配偶者居住権(2020.4.1以降開始相続)
- 配偶者居住権の法的性質
- 配偶者短期居住権(2020.4.1以降開始相続)
- ▼不動産の相続手続(もくじ)▼
- 不動産の相続手続(相続登記)
- 相続登記後、売却する不動産は誰名義で相続登記したら良いですか?!
- 相続不動産売却サポート
- 何代も前の相続で、途中の相続登記を省略できる場合~数次相続で中間省略登記が認められる条件
- 相続登記に上申書が必要な場合(戸籍不足の相続登記)
- 進まない相続登記(協力しない相続人がいる場合、相続人が何十人もいる場合)の対応【調停や判決による相続登記】
- 長期相続登記未了の通知を受けた方へ/法定相続人情報
- 相続登記義務化:令和6(2024)年4月1日施行
- 相続登記義務を免れるための「相続人申告登記」の意味と申請手続
- 所有者不明土地問題を解消するための法改正と施行時期【一覧】
- 相続した土地を国に引き取って貰う制度『相続土地国庫帰属法』令和5(2023)年4月27日施行
- ▼不動産以外の相続手続(もくじ)▼
- 銀行預金・郵便貯金の相続手続
- 上場株式・非上場株式(株券)の相続手続
- 生命保険の相続手続・税金・遺言執行
- ゴルフ会員権の相続手続
- デジタル遺産の相続手続
- 未支給年金の相続手続
- 自動車の相続手続
- ▼借金貸付金の相続手続(もくじ)▼
- 他人への貸付金(借主)に相続が発生したときの債権者の対応
- 他人への貸付金(貸主)の相続手続
- 借金の相続手続
- NHK未払い受信料の相続手続
- 相続承認・放棄の期間伸長の申立
- 相続放棄(申述)の意味と申立手続
- 相続放棄(申述)できなくなる法定単純承認とは?
- 法定単純承認となることなく、遺品を処分することは可能か?!
- 相続放棄(申述)をしても免れないことがある?!固定資産税・都市計画税のハナシ
- 相続放棄(申述)と数次相続・代襲相続
- 遺贈の放棄|遺言で受けた贈与(遺贈)を放棄する方法は、遺言の書き方によって異なります。
- 限定承認の意味と方法
- ▼遺言があるときの相続(もくじ)▼
- 遺言書を探す方法(公正証書遺言、法務局保管自筆証書遺言の探索)
- 遺言検認申立
- 遺言執行者選任申立
- 遺言解釈・遺言執行
- 遺言解釈(受遺者や受益相続人が遺言者よりも①先に死亡したとき、②同時に死亡したとき)
- 遺言解釈(負担付遺贈か条件付遺贈か)
- 遺言解釈(負担付遺贈を受遺者が放棄した場合)
- 遺言解釈(負担付遺贈の受遺者が負担を履行しないとき)
- 遺言執行(執行対象に動産がある場合)
- 遺言執行(執行対象に動産がある場合)[グループ会員限定記事]
- ▼相続に関する他の手続(もくじ)▼
- 外国(海外)在住日本人の相続手続・相続放棄手続とその必要書類(在留証明・署名証明・法定相続情報・日本公証役場)
- 日本在住外国人の相続手続(各国の相続法)
- 特別代理人選任申立(未成年者がいる場合の遺産分割協議)
- 不在者財産管理人選任申立
- 失踪宣告申立
- (民法952条の)相続財産清算人選任申立
- 相続財産法人への登記名義人氏名変更登記
- 特別縁故者からの相続財産の分与請求
- 他の共有者が死亡したとき、どうすれば良いのか?!~共有者の相続人への共有物分割請求~
- 相続・遺産分割のトラブル解決
- 契約書作成・精査
- 外国人の帰化
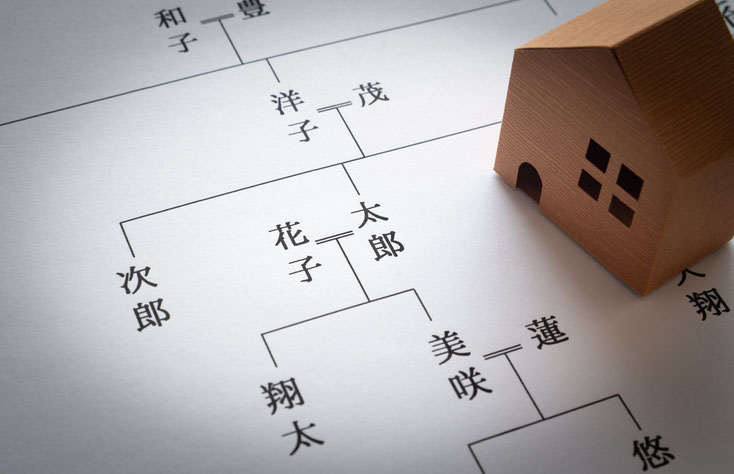
どなたかがお亡くなりになった場合、誰が何を相続するか話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。遺産分割協議に先立って、「人」に関して確認すべきことは、次の2点です。
- 遺産分割は誰と話し合えば良いのか(法定相続人)
- 話し合いの基本となる割合は、いくらなのか(法定相続分)
この記事では、条文を引用しながら、法定相続人や法定相続分について、解説しています。
| もくじ | |
|
〔凡例〕この記事では、次のように略記します。
- 民889Ⅰ①ただし書き:民法第891条第1項第1号ただし書き
相続人を確定すべき理由
相続人を確定するのは、遺産分割協議へ参加資格がある人を確定するためです。
相続人を一人でも欠いていた場合、遺産分割協議は成立しません。
そのため、相続人の確定作業は大変重要です。
相続人を確定する必要がない場合
遺言書で全財産の行き先が決まっているときは?
遺言を執行する段階では不要ですが、他の相続人から「遺言を隠した」と主張されると最悪、相続人資格を失うこととなります(相続欠格。民法891⑤)。
このような主張をされないために、実務では、全相続人に対して、遺言書を添付して通知します。
そのため、最終的には相続人の確定は必要です。
| 民法第891条(相続人の欠格事由) | |
|
次に掲げる者は、相続人となることができない。 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。 三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 |
|
相続人が自分一人であるときは?
一人の場合、遺産分割協議は不要です。
しかしながら、相続人が一人しかいないことを確定するために必要です。
法定相続人とは
遺産分割協議への参加資格の一つ
遺産分割協議に参加できる資格は、法律で決まっており、下記のとおりです。
- 法律で定められた相続人(法律で決まっているので「法定相続人」といいます。民法896条から民法895条まで。)
- 亡くなった方が遺言で定めた包括受遺者(民法964条、民法965条)
法定相続人
遺産分割協議に参加できる資格の一つ「法定相続人」は、次表のとおりです。
遺産分割協議が成立するためには、法定相続人全員が参加して、合意する必要があります。
| 第1順位 | 子【2】(民法887) |
配偶者【1】は常に相続人 (民法890) |
| 第2順位(子・孫・曽孫がいないとき) | 直系尊属【3】(民法889) | |
| 第3順位(直系尊属もいないとき) | 兄弟姉妹【4】(民法889) |
【1】配偶者には、事実婚(同棲しているが、婚姻届を提出していないカップル)は含まれません。
事実婚の相手に遺産を遺したいときには、遺言が必要です。
「遺言作成トータルサポート」の利用をご検討ください。
【2】被相続人の子が、被相続人よりも前に亡くなっている場合には、被相続人の孫が相続人になります(民887Ⅱ)。代襲して相続するので「代襲相続」といいます。また、この場合のお孫さんを「代襲相続人」といいます。
記事「相続人は誰か❷数次相続、再転相続、代襲相続の区別」もご参照ください。
| 祖父A | ーーーーーー | 父B | ーーーーー | 子C |
| ➋死亡 | ➊死亡 | 代襲相続人 |
さらに、被相続人の子だけでなく孫も、被相続人よりも前に亡くなっている場合には、被相続人の曾孫(ひまご)が相続人になります(民887Ⅲ)。これを「再代襲相続」といいます。
曽孫も、被相続人よりも前に亡くなっている場合には、その下が相続人となります。
| 民法第887条(子及びその代襲者等の相続権) | |
|
|
【3】被相続人の父母です。父母が被相続人よりも前に亡くなっている場合は、祖父母。祖父母も亡くなっている場合には、曾祖父母というように、順の上の世代の血族に遡って、相続人となります(民889Ⅰ①ただし書き)。
【4】被相続人の兄弟姉妹です。兄弟姉妹が被相続人よりも前に亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子、つまり、甥(おい)や姪(めい)が第3順位の代襲相続人となります。
兄弟姉妹の代襲相続は、一代で止まります。子や孫への代襲相続が、無制限であることとの大きな違いです。被相続人の兄弟姉妹の代襲相続を定めた民法889条2項は、民法887条2項のみを準用し、3項を準用していません。
| 民法第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) | |
|
|
法定相続人を確定する方法
被相続人の戸籍を収集します。収集すべき戸籍は、出生から死亡までの全ての戸籍です。
集めた戸籍を読み込んで、被相続人が認知などをしていないかを確認していき、相続人を確定します。
下記記事もご参照ください。
法定相続分とは
❶法定相続人が誰であるのかが確定したら、次は、❷各法定相続人の法定相続分を確認しましょう。
法定相続分(基本)
法定相続分は次のとおりです(民900①②③)。
| 法定相続人 | 法定相続分 |
| 配偶者と子であるとき |
配偶者:子=1/2:1/2(民900①) |
| 配偶者と親であるとき |
配偶者:親=2/3:1/3(民900②) |
| 配偶者と兄弟姉妹であるとき |
配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4(民900③) |
法定相続分(同順位の相続人が複数いるとき)
子や直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合は、法定相続分を人数で分けることになります(民900④本文)。
例えば、配偶者と子2人が法定相続人の場合は、次のように計算します。
配偶者:子2人=1/2:1/2(民900①)
子が二人いる(同順位の相続人が複数いる)場合なので、人数で分けるため、*1/2します(民900④本文)。
配偶者:長男:長女=1/2:1/2*1/2:1/2*1/2=2/4:1/4:1/4
|
民法第900条(法定相続分) |
|
|
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。 |
|
法定相続分(全血の兄弟、半血の兄弟)
被相続人に子も孫も親も祖父母もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります(下図)。
(亡) (亡) (亡)
母====┬====父====┬====父の前妻
┌ー┴ー┐ |
| | |
被相続人 弟 姉
(全血の兄弟) (半血の兄弟)
このような場合、父母が同じ弟のことを「全血の兄弟」、父のみが同じ姉のことを「半血の兄弟」といいます。半血の兄弟の法定相続分は、全血の兄弟の法定相続分の半分です(民900④ただし書き)。
父母が同じ弟:父だけ同じ姉=2:1=2/3:1/3
法定相続分(代襲相続人)
| 祖父A | ーーーーーー | 父B | ーーーーー | 子C |
| ➋死亡 | ➊死亡 | 代襲相続人 |
代襲相続人(C)の相続分は、被代襲者(B)の法定相続分と同じです(民901Ⅰ本文)。
代襲相続人が複数いる場合には、民法900条の規定どおりです(民901Ⅰただし書き)。
| 民法第901条(代襲相続人の相続分) | |
|
|
法定相続分を守る必要があるのか?
ここまで説明してきました「法定相続分」ですが、遺産分割協議をするときには、必ずしも守る必要はありません(民906)。全相続人の法定相続分を確保しなければならないということはありません。
「自分は生前、被相続人から十分にしてもらったから何も要らない。」もOKです。
「自分は十分お金を持っているから何も要らない。」もOKです。
法定相続人全員が協議して、全員が納得するなら、法定相続分は無視しても支障ありません。
ただし、遺産分割が話し合いで成立しない場合には、最終的には、家庭裁判所が審判で決定します。この審判では、裁判官は、法定相続分に縛られます。
| 民法第906条(遺産の分割の基準) | |
| 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 | |
指定相続分とは
ここまで説明してきました「法定相続分」ですが、遺言で変更することができます(民法902)。この遺言で変更した相続分のことを「指定相続分」といいます。
| 民法第902条(遺言による相続分の指定) | |
|
|
具体的相続分とは
民法には出てこない言葉ですが、「具体的相続分」という言葉もあります。
「具体的相続分」は、法定相続分や指定相続分をもとに、特別受益(民903)や寄与分(民904の2)等を考慮して調整した相続分のことです。
特別受益とは
特別受益は、相続人間の不公平を是正するための制度です。
「特別受益」とは、被相続人から生前贈与や遺言による贈与を受けている場合をいいます(民903.904)。そのまま法定相続分で分割すると不平等になるので、計算上、相続財産に戻す処理をすることがあり、これを「特別受益の持戻し」といいます。
記事「特別受益(の持ち戻し)」もご参照ください。
寄与分とは
寄与分も、相続人間の不公平を是正するための制度です。
被相続人の財産維持や増加に、特別に役立つ働きをした(特別の寄与をした)相続人の相続分が、上乗せされることです(民法904の2)。
遺産分割協議や調停で相続人全員で合意した場合や審判によって獲得することができます。
記事「寄与分(特別の寄与)」もご参照ください。
人気の関連ページ
 企業・事業者向けサービス
企業・事業者向けサービス
 トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)
トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)


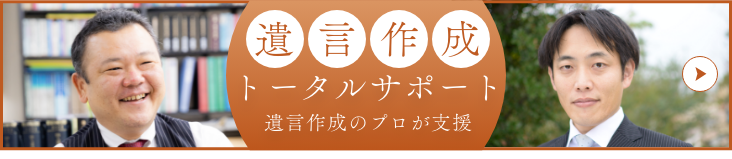


















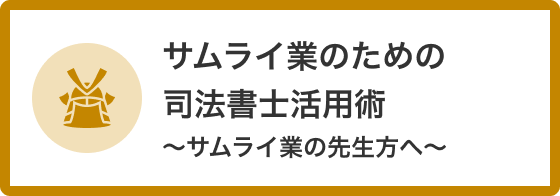
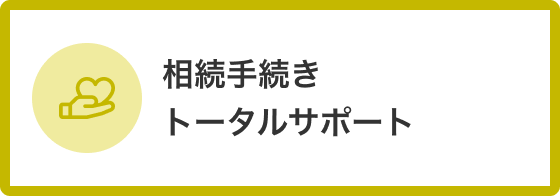
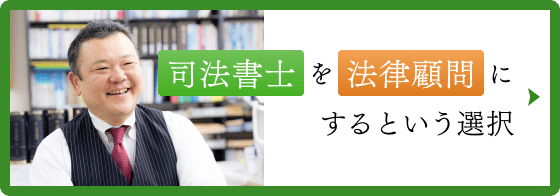

 個人向けサービス
個人向けサービス