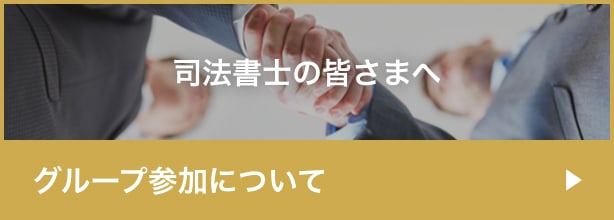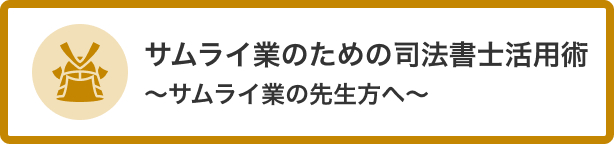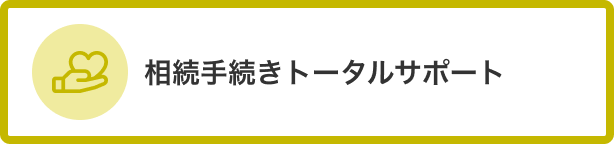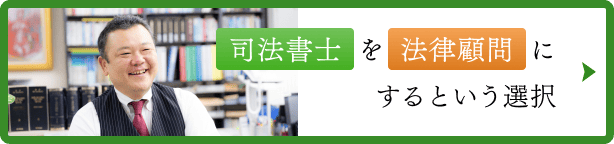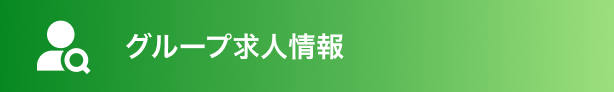- トラブル解決総論
- 相続・遺産分割トラブル解決
- 夫婦子供のトラブル解決
- その他親族トラブル解決
- 企業・事業者のトラブル解決
- 不動産・借地借家・隣近所のトラブル解決
- 不動産の取得時効と登記の関係
- 不動産賃貸借における関西方式・関東方式
- 敷金・保証金・建設協力金の違い
- 賃貸借契約の当事者が変更した場合、誰が誰に敷金を返せば良いか?
- 敷引特約の有効性
- 賃貸借契約で「中途解約を禁止する条項」は有効か?
- 賃貸借契約における更新料条項の有効性、更新料不払いの効果、法定更新との関係ほか後日もめないための具体的な対策
- 賃貸借契約で遅延損害金を年14.6%とする条項は有効か?
- 明渡しが遅れたときに賃料倍額の使用損害金を請求する条項は有効か?
- 滞納賃料(家賃・地代)の請求を受けた連帯保証人の対応
- 借主の軽微な契約違反だけでは解除できない賃貸借契約「信頼関係破壊の法理」
- 家賃滞納による建物明渡請求
- 賃借人が連帯保証人を立てない場合、賃貸人は賃貸借契約を解除できるか?!
- 賃料(地代・家賃)増減額請求
- 借地に関する契約
- 借地権登記できない場合の「借地上の建物登記」民法177条の例外
- 建物賃貸借の契約期間を設定するときの注意点
- 借地上の建物を賃貸借するときの注意点
- 定期借家契約のメリットと注意点
- DIY型賃貸借契約のメリットと注意点
- 原状回復・敷金返還に関するトラブル解決
- 建物賃貸借で「通常損耗をも借家人負担とする」特約の有効性
- 原状回復義務と明渡義務の関係|原状回復が終わらないと、建物明渡し完了にならない?!
- マンションの滞納管理費・修繕費・積立金の回収
- マンション義務違反者への対応
- 連棟建物(長屋、二戸一、三戸一)の切り離しトラブル
- マンション上階や二戸一の隣家からの水漏れトラブル解決
- 隣近所とのトラブル解決
- 隣地の建築計画はどこで確認するか?!宅地開発から建物建築までの流れ
- 建物建築に際しての周辺住民への説明義務
- 隣地が境界ギリギリに建築するのを止められませんか?!
- 崖地の擁壁・石垣の補修に関するトラブル【図解】
- 隣地に対する目隠し設置請求権
- 境界トラブル(筆界と所有権界)
- 私道の通行権をめぐるトラブル
- (ケガの後遺症や精神疾患などが原因で)騒音、大声、奇行などの問題行動をおこし周囲に迷惑をかけている方への対応(グループ会員限定記事)
- 交通事故解決
- 消費者トラブルの解決
- 借金が返済できないときの個人の債務整理(任意整理・民事再生・自己破産)
- 判決が出ても従わない相手方への強制執行による債権回収(差押え)
- 仮差押・仮処分など保全処分
- 刑事事件(被害者・加害者)
- 少年事件(被害者・加害者)
定期借家契約(定期建物賃貸借契約)のメリットと注意点|不動産賃貸借契約

定期借家契約は、家主にとって、有利な契約です。ところが、定期借家契約の要件を備えていないために、通常の借家契約になっている例が散見されます。
この記事では、定期借家契約の特徴と、定期借家契約の流れを解説しています。
| もくじ | |
|
〔凡例〕この記事では、次の法令が出てきます。法令名が長いときは、次のとおり略記します。
- 借地借家38Ⅰ:借地借家法(平成三年法律第九十号)第38条第1項
〔凡例2〕次の言葉は、同じ意味です。この記事では、一番左の用語を使用します。
- 借家契約=建物賃貸借契約
- 定期借家契約=定期建物賃貸借契約
- 借主=賃借人=家を借りる人
- 家主=貸主=賃貸人=家を貸す人
- 家賃≒賃料(=地代、家賃)
普通の借家契約の特徴
普通の借家契約では、借主は、法律で手厚い保護がなされています。
すなわち、普通の借家契約では、契約期間が満了しても「法定更新」制度があり、家主に「正当事由」がなければ、家主は借家契約を解除できません。賃料が相場よりも安くなったとしても、一気に賃料を相場まで上げることはできません(継続賃料と新規賃料の問題)。
その結果、次のような弊害を生んでいました。
- 家主側の問題:家主が不動産を返してほしいと望んでも、契約を終了させることが困難であった。
- 賃貸市場への影響:不動産所有者が、一度貸すと返ってこないことを恐れて不動産を貸し出さなくなり、賃貸物件の供給が不足した。
- 不動産の有効活用阻害: 賃貸需要に見合う物件の供給がなくなることで、不動産の有効活用が十分になされていないと問題視された。
- 価格形成の歪み: 借家の供給が萎縮した結果、高額な権利金や立退料が要求されるなど、合理的な価格形成が阻害されていた。
「借主に対する手厚すぎる保護」と「家主の権利」を調整したのが、次にご紹介する「定期借家契約」です。
定期借家契約の特徴
定期借家契約は、借主の保護を弱める一方で、家主に少し面倒な手続きを要求しています。
| 定期建物賃貸借契約=定期借家契約 | (普通の)建物賃貸借契約 | |
| 貸主側 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 借主側 |
|
|
【1】定期建物賃貸借契約において、中途解約できる旨の特約がない場合には、定期建物賃貸借契約は、契約期間満了まで継続します。契約の終期まで、賃料を支払う義務を負うということです。
記事「賃貸借契約で『中途解約を禁止する条項』は有効か」も参照ください。
ただし、定期建物賃貸借契約の場合であっても「居住用建物の賃貸借で床面積が200㎡未満の建物のとき」には、中途解約権が法律によって付与されています(借地借家38Ⅶ)。
【2】借地借家法32条1項は次のとおり定めています。
| 借地借家法第32条 (借賃増減請求権) | |
|
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。 |
|
これを整理すると下表のとおりです。
| 賃料減額しない特約(借主不利) | 無効(借地借家32Ⅰ本文) |
| 賃料増額しない特約(貸主不利) | 有効(借地借家32Ⅰただし書) |
(弁護士法人 御堂筋法律事務所『契約違反と信頼関係の破壊による 建物賃貸借契約の解除 ―違反類型別 賃貸人の判断のポイント―』新日本法規出版/2019/10頁、 澤野 順彦『実務解説 借地借家法 (第3版)』青林書院/2020/139頁)
【3】賃貸人の意向によって、再契約ができるか否かが分からないからです。また、従前賃料と同額で借りられるとは限りません(相場が上がっていれば、値上げされます。)。
定期借家契約の流れ
★印をつけたところが、「定期借家契約」の特徴です。
定期借家契約であることを明示して入居者の募集

入居申込書の提出

★定期借家契約についての事前説明★
建物の貸主は、あらかじめ、建物の賃借人に対し「建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了する」旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法38Ⅱ)。建物の貸主が、説明をしなかったときは、普通の建物賃貸借契約になってしまいます(借地借家法38Ⅲ)。
不動産仲介会社が行う「重要事項説明」は、宅建業者が行うものであり主体が異なるため、別途「事前説明」が必要です。

★定期借家契約の締結★(契約書への署名押印)
普通の借家契約は、口頭でも成立しますが、「定期借家契約」は必ず書面による契約が必要です(借地借家38Ⅰ前段)。

物件への入居

★期間満了前に通知★
建物の貸主は、期間満了の1年前から6か月前までの間(通知期間)に建物の借主に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができません。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から6か月を経過した後は、この限りではありません(借地借家法38Ⅳ)。

借主が借り続けたい場合、賃貸人に再契約の申込み

(このフローチャートの最初に戻る)
条文
直接条文を確認したい皆様のために、定期建物賃貸借契約に関する条文を挙げておきます。
記号〔〕の中の文言は、筆者が追記したものです。
| 借地借家法第38条 (定期建物賃貸借) | |
|
|
司法書士の報酬・費用
家主も借主も、定期借家契約の締結を希望している場合には、司法書士にご用命ください。
司法書士が法律の要件を充たした契約書等をご用意することにより、ご希望どおりの定期借家契約の成立をお手伝いします。
| 業務の種類 | 司法書士の費用 | 実費 |
|
275,000円(税込) | 登記簿取得費、郵送費、交通費など |
|
33,000円(税込) | 郵送費等 |
人気の関連ページ
- 不動産・借地借家・隣近所のトラブル解決TOP
-
- 不動産賃貸借トラブル
- 不動産売買トラブル
- 不動産建築トラブル
- マンションのトラブル
- 隣近所とのトラブル
- 不動産に関する時効
 企業・事業者向けサービス
企業・事業者向けサービス
 トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)
トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)



















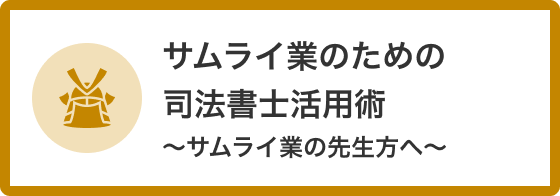
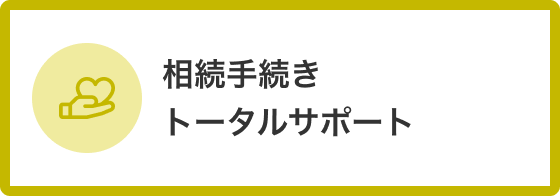
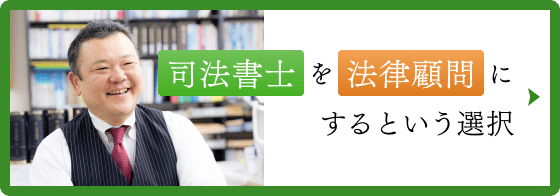

 個人向けサービス
個人向けサービス