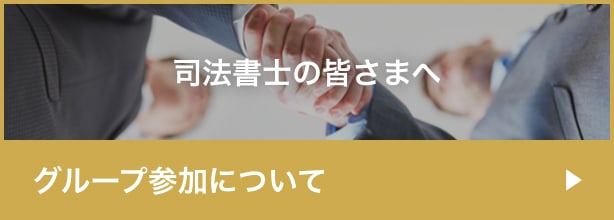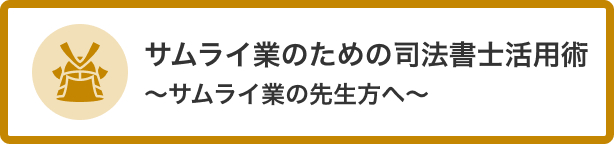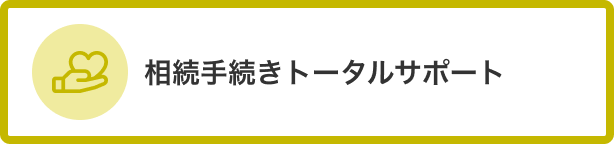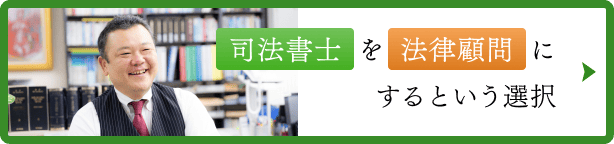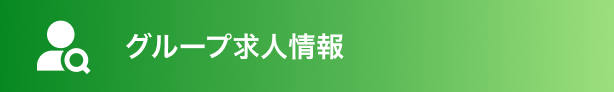- 不動産名義変更・不動産登記TOP
- 終活(成年後見・家族信託・遺言)TOP
- 相続手続き・遺産整理TOP
- ▼知ってお得な相続知識(もくじ)▼
- 相続クイズ50問(間違いだらけのネット情報)
- 自分で相続登記手続をした方に聞きました「相続手続で苦労した理由!ベスト10」
- 相続に関与しようとする民間資格や民間団体にご注意ください。
- 最期の時が近づいたとき(葬儀前に)ご家族が確認・準備するべきこと
- 相続開始直後(葬儀後すぐ)に行なうべき手続一覧
- 相続手続トータルサポート
- 遺言寄付の受け入れトータルサポート
- 相続は早い者勝ちになりました
- 相続登記・遺贈登記の特急申請(グループ会員限定記事)
- 銀行・信託銀行の相続手続は、本当に「質の悪いブランド品」なのか?!士業の相続手続と徹底比較!
- 法定相続情報~ややこしい戸籍を読むのは司法書士が一回で十分です。銀行預金の相続手続前に司法書士にご依頼ください。
- 相続による銀行口座凍結とは?!
- 銀行預金の仮払制度(遺産分割前の預金払戻し制度)
- ▼相続財産の調査(もくじ)▼
- 相続によって引き継ぐ財産・引き継がない財産(相続の対象財産)
- 行方不明の相続預金・相続貯金の探索
- 相続で負債・借金がないかの調査方法
- 被相続人の遺品の中から、相続人や第三者名義の通帳が出てきた場合どうすれば良いのか?(いわゆる名義預金の問題)
- 相続登記や遺言の際に欠かせない不動産の近隣地調査(名寄せ)
- 相続生命保険の調査
- ▼相続人の調査(もくじ)▼
- 相続人は誰か❶基本編(法定相続人・法定相続分)
- 相続人は誰か❷数次相続・再転相続・代襲相続の区別
- 子が親より(妻が夫より)①先に死亡したとき、②同時に死亡したとき、③死亡の先後が分からないときの相続(同時存在の原則、同時死亡の推定)
- 義父母の遺産を受け取る「特別寄与料制度」
- 相続手続のための戸籍収集
- 戸籍の広域交付制度とその盲点
- あなたの戸籍謄本(住民票)が取得されましたとの通知を受けた方へ:本人通知制度
- 旧民法(明治民法・応急措置法)による相続
- ▼相続税申告の要否▼
- ▼遺産分割協議(もくじ)▼
- 遺産分割協議書の基礎知識、作成の流れ
- 遺産分割協議の種類と流れ
- 遺産分割協議成立後、相続人の漏れに気付いた場合の対応方法[グループ会員限定]
- 遺産分割協議の期間制限
- 一次相続の遺産分割協議では、二次相続のことも考えましょう。
- 相続分の譲渡・相続分の放棄
- 平成13年6月までに相続開始又は代襲原因発生の場合は注意「非嫡出子の法定相続分」
- 特別受益証明書(相続分ないことの証明書)による相続登記が流行した理由、消滅した理由から、特別受益証明書の可能性を探る
- 配偶者居住権(2020.4.1以降開始相続)
- 配偶者居住権の法的性質
- 配偶者短期居住権(2020.4.1以降開始相続)
- ▼不動産の相続手続(もくじ)▼
- 不動産の相続手続(相続登記)
- 相続登記後、売却する不動産は誰名義で相続登記したら良いですか?!
- 相続不動産売却サポート
- 何代も前の相続で、途中の相続登記を省略できる場合~数次相続で中間省略登記が認められる条件
- 相続登記に上申書が必要な場合(戸籍不足の相続登記)
- 進まない相続登記(協力しない相続人がいる場合、相続人が何十人もいる場合)の対応【調停や判決による相続登記】
- 長期相続登記未了の通知を受けた方へ/法定相続人情報
- 相続登記義務化:令和6(2024)年4月1日施行
- 相続登記義務を免れるための「相続人申告登記」の意味と申請手続
- 所有者不明土地問題を解消するための法改正と施行時期【一覧】
- 相続した土地を国に引き取って貰う制度『相続土地国庫帰属法』令和5(2023)年4月27日施行
- ▼不動産以外の相続手続(もくじ)▼
- 銀行預金・郵便貯金の相続手続
- 上場株式・非上場株式(株券)の相続手続
- 生命保険の相続手続・税金・遺言執行
- ゴルフ会員権の相続手続
- デジタル遺産の相続手続
- 未支給年金の相続手続
- 自動車の相続手続
- ▼借金貸付金の相続手続(もくじ)▼
- 他人への貸付金(借主)に相続が発生したときの債権者の対応
- 他人への貸付金(貸主)の相続手続
- 借金の相続手続
- NHK未払い受信料の相続手続
- 相続承認・放棄の期間伸長の申立
- 相続放棄(申述)の意味と申立手続
- 相続放棄(申述)できなくなる法定単純承認とは?
- 法定単純承認となることなく、遺品を処分することは可能か?!
- 相続放棄(申述)をしても免れないことがある?!固定資産税・都市計画税のハナシ
- 相続放棄(申述)と数次相続・代襲相続
- 遺贈の放棄|遺言で受けた贈与(遺贈)を放棄する方法は、遺言の書き方によって異なります。
- 限定承認の意味と方法
- ▼遺言があるときの相続(もくじ)▼
- 遺言書を探す方法(公正証書遺言、法務局保管自筆証書遺言の探索)
- 遺言検認申立
- 遺言執行者選任申立
- 遺言解釈・遺言執行
- 遺言解釈(受遺者や受益相続人が遺言者よりも①先に死亡したとき、②同時に死亡したとき)
- 遺言解釈(負担付遺贈か条件付遺贈か)
- 遺言解釈(負担付遺贈を受遺者が放棄した場合)
- 遺言解釈(負担付遺贈の受遺者が負担を履行しないとき)
- 遺言執行(執行対象に動産がある場合)
- 遺言執行(執行対象に動産がある場合)[グループ会員限定記事]
- ▼相続に関する他の手続(もくじ)▼
- 外国(海外)在住日本人の相続手続・相続放棄手続とその必要書類(在留証明・署名証明・法定相続情報・日本公証役場)
- 日本在住外国人の相続手続(各国の相続法)
- 特別代理人選任申立(未成年者がいる場合の遺産分割協議)
- 不在者財産管理人選任申立
- 失踪宣告申立
- (民法952条の)相続財産清算人選任申立
- 相続財産法人への登記名義人氏名変更登記
- 特別縁故者からの相続財産の分与請求
- 他の共有者が死亡したとき、どうすれば良いのか?!~共有者の相続人への共有物分割請求~
- 相続・遺産分割のトラブル解決
- 契約書作成・精査
- 外国人の帰化

相続が発生して家の整理をしていたところ、NHK(日本放送協会)から受信料の請求書が見つかった場合、相続人は、どう対応すれば良いのでしょうか?
また、NHK受信料については、色々な問題がありました。
そこで、この記事では、前半で「NHK受信料問題」について、後半で「相続人の対応方法」について解説しています。
なお、当グループでは「NHK受信料問題」単独では、お取り扱いしておりません。
| もくじ | |
|
〔凡例〕この記事では、次の法令が出てきます。法令名が長いときは、次のとおり略記します。
- 憲法:日本国憲法(昭和二十一年憲法)
- 民:民法(明治二十九年法律第八十九号)
- 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
- 日本放送協会放送受信規約
- 日本放送協会放送受信料免除基準
NHK受信料問題とは
「NHK受信料問題」とは、テレビがあるだけでNHKを一切見なくても、法律によって「NHKとの契約」が義務付けられている制度をめぐる様々な論争のことです。
NHKの言い分
「公共放送NHKは、“いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える”ことを基本的な役割として担っており、その運営財源が受信料です。税金でも広告収入でもなく、みなさまに公平に負担していただく受信料だからこそ、特定の利益や意向に左右されることなく、公共放送の役割を果たしていけると考えています。(NHK『受信料の公平負担に向けた取り組みについて知りたい』最終アクセス2025/09/06)」
法律の定め
| 放送法第64条 | |
|
|
主な論争
-
受信契約義務: 放送法64条1項が「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と受信契約を締結しなければならない」と定められています。テレビ放送を受信できる機器を所有しているだけで対象となり、契約義務が発生します。
☛ 国民に契約を強制する点について、憲法の保障する自由権の侵害(憲法違反)ではないかという反論がなされてきました。 -
支払いの義務:NHKとの放送受信契約を締結することにより、その契約(規約)により、受信契約者は受信料を支払う義務を負います。
☛ 契約は法律ではないため「契約は義務だが、支払いは任意ではないか」という反論がなされてきました。 -
受信料の使途: 巨額の受信料収入がどのように使われているか、その経営の効率性や透明性について、国民からの厳しい目が向けられています。過去に生じたNHK職員による不祥事が、受信料不払いの増加の一因となりました。
筆者のコメント
NHKのテレビ番組には、民間放送局のテレビ番組と異なり、テレビCMがありません。
これは、NHKが、視聴者からの受信料で運営されているからです。
(特定のスポンサーに、放送内容を乗っ取られることを予防している。)
民間放送は、テレビCMの出稿料などで運営されていますので、スポンサー(テレビCMを流す事業者)の都合の悪いニュースを流しません。かつて、民間放送が武富士、アコム、アイフル、プロミス等の悪質サラ金に乗っ取られ、多数の市民が犠牲になりました。
(ただし、NHKがサラ金問題を真っ先に取り上げ、国民に啓蒙活動を行ったかというと、そういう記憶は私にはありません。)
憲法の条文を確認したのち、司法(裁判所)がどのような判断をくだしたのか、見ていきましょう。
憲法の条文
| 憲法第13条 | |
|
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 |
|
| 憲法第19条 | |
|
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 |
|
|
憲法第21条 |
|
|
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 |
|
| 憲法第29条 | |
|
財産権は、これを侵してはならない。 ② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 ③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 |
|
最高裁判決
| 最大判平成29年12月6日民集71巻10号1817頁 | |
|
Westlaw Japan 〔裁判要旨〕 ◆放送法64条1項は、日本放送協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に対しその放送の受信についての契約の締結を強制する旨を定めた規定であり、日本放送協会からの上記契約の申込みに対して上記の者が承諾をしない場合には、日本放送協会がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決の確定によって上記契約が成立する ◆放送法64条1項は、同法に定められた日本放送協会の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の、日本放送協会の放送の受信についての契約の締結を強制する旨を定めたものとして、憲法13条、21条、29条に違反しない ◆日本放送協会の放送の受信についての契約を締結した者は受信設備の設置の月から定められた受信料を支払わなければならない旨の条項を含む上記契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により同契約が成立した場合、同契約に基づき、受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する ◆日本放送協会の放送の受信についての契約に基づき発生する、受信設備の設置の月以降の分の受信料債権(上記契約成立後に履行期が到来するものを除く。)の消滅時効は、上記契約成立時から進行する |
|
この最判によって「テレビを設置すればNHKとの受信契約が強制されること」は憲法違反ではないことが確定しました。
ついでに下級審の裁判例も掲載しておきます。
| 東京高判平成22年6月29日判時2104号40頁 | |
|
「控訴人らは,どのような情報を取得するかについては,人格形成及びその発展にとって必要かつ不可欠のものであるから,憲法13条によりいかなる番組を視聴し又は視聴しないかに関する意思決定権の自由が保障されているところ,法32条がこの意思決定権の自由を侵害する旨主張する。しかしながら,法32条及び放送受信規約9条は,放送受信契約の締結及び被控訴人の放送を受信できる受信機を廃止しない間の放送受信料の支払を義務づけるだけであって,どのような番組を視聴するかについて強制するものでも妨害するものでもない。」ので、憲法13条に違反しない。 「憲法19条で保障される内心とは、特定の歴史観、世界観等の人格形成に関わる内心を指すものであって」NHKの「放送に対する嫌悪感や法で定められた放送受信料の支払いを回避したいという内心がこれに含まれないことは明らか」なので、憲法19条に反しない。 「控訴人らは,控訴人らが放送受信料の支払を免れようとすると,必然的に民放のテレビ番組の視聴を妨げられ,民放のテレビ番組を視聴することにより情報を取得する自由を侵害される旨主張するが,法32条及び放送受信規約9条は,放送受信契約の締結及び被控訴人の放送を受信できる受信機を廃止しない間の放送受信料の支払を義務づけるだけであって,民放のテレビ番組を視聴することを制限するものではない。」したがって,憲法21条に反しない。 「控訴人らは,放送受信規約9条が被控訴人の放送を受信できる受信機を廃止しない限り,原告との放送受信契約の解約を禁止しているのは,消費者契約法10条に定める「民法,商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し,消費者の権利を制限し,又は消費者の義務を加重する」条項であるから,無効である旨主張する。しかしながら,消費者契約法は,事業者と消費者との情報の質及び量ないし交渉力の格差にかんがみ,事業者と消費者との間で締結された契約について,消費者の利益を不当に害することとなる条項を無効としたり,取り消すことができること等を定めたものであるところ,法32条が放送受信契約の締結を義務づけ,放送受信規約9条はこのことと同趣旨のことを定めるものであって(法32条が適用されることは,消費者契約法11条2項),法32条は,当事者間でこれと異なる合意をすることを禁止する強行規定と解されることからすれば,そもそも,法32条と異なる契約を締結することができない場合であって,消費者契約法10条が適用され得る余地はないといわなければならない。」 「民法761条に定める,日常家事に関する法律行為によって発生した債務とは,婚姻共同体において家庭生活を営むために通常必要とされる法律行為に基づく債務であるが,問題となる具体的な法律行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属するか否かを決するに当たっては,同条が,夫婦の一方と取引関係に立つ第三者の保護を目的とする規定であることにかんがみ,内部的な事情やその行為の個別的な目的のみを重視して判断すべきではなく,客観的に,その法律行為の種類,性質等を考慮して判断すべきであるところ,現代社会において,テレビ番組の視聴は,日常生活に必要な情報を収集するため又は相当な範囲内の娯楽として,夫婦の共同生活を営む上で通常必要なものといえ,そして,放送法(以下「法」という。)32条は,「協会(被控訴人)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会(被控訴人)とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と規定しており,この規定によれば,被控訴人の番組の視聴をするか否かを問わず,契約締結を強制しているものということができる。したがって,法32条の規定の文言を前提とする限り,放送受信契約の締結は,民法761条本文の日常の家事に関する法律行為の範囲に属するということができる。」 |
|
NHK受信料の時効消滅
過去の受信料の請求をされた場合、どう対応すべきでしょうか?
消滅時効を援用できる【1】場合があります。消滅時効を援用した証拠を残しておくため、内容証明郵便で行います。
【1】消滅時効の援用とは、契約者(債務者)が、NHKに対して、消滅時効期間経過後、消滅時効の恩恵を受ける(すなわち債務を消滅させる)意思表示を行うことです。
NHK受信契約(基本権)の消滅時効
注意すべき最高裁判決があります。
| 最判平成30年7月17日民集 72巻3号297頁、裁判所ウェブサイト | |
|
♦要旨♦ 受信契約に基づく受信料債権には,民法168条1項前段の規定は適用されない ♦理由抜粋♦ 「受信契約に基づく受信料債権は,一定の金銭を定期に給付させることを目的とする債権であり,定期金債権に当たるといえる。しかし,放送法は,公共放送事業者である被上告人の事業運営の財源を,被上告人の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に広く公平に受信料を負担させることによって賄うこととし,上記の者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定を置いているのであり,受信料債権は,このような規律の下で締結される受信契約に基づき発生するものである。受信契約に基づく受信料債権について民法168条1項前段の規定の適用があるとすれば,受信契約を締結している者が将来生ずべき受信料の支払義務についてまでこれを免れ得ることとなり,上記規律の下で受信料債権を発生させることとした放送法の趣旨に反するものと解される。」 |
|
上記最判を理解するためには、「定期金債権」と「定期給付債権」の違いを、ご理解いただく必要があります。
定期金債権と定期給付債権
「定期金債権」と「定期給付債権」の違いは、下表のとおりです。
| 定期金債権(基本権) | 定期給付債権(支分権) | |
| 定義 | 一定額の金銭を定期的に継続して受け取る権利 | 定期金債権から派生し、各回ごとの個別支払請求権 |
| 例 |
|
|
| 条文 |
民法168条(定期金債権の消滅時効) |
旧民法169条(定期給付債権の消滅時効) 現行民法166条(債権等の消滅時効) |
| 時効 |
|
|
| 考え方 |
基本権そのものが時効消滅すると、その後、支分権は発生しなくなり、一旦発生した支分権も消滅する。 |
発生した個々の請求権(支分権)が、それぞれ時効で消滅していきます。 |
定期金債権(基本権)について、消滅時効が定められているのは「定期に発生する支分権について権利行使が全くされないときでも、基本権である定期金債権がいつまでも時効にかからず、支分権が発生し続けるのは適当でないという考慮に基づくもの」とされています。
上記、平成30年最判は、この定期金債権(基本権)の消滅時効がNHKとの受信契約には適用されない(つまり、NHKとの受信契約は消滅時効にかからない。)といっているわけです。
次は、毎月発生するNHK受信料(上記表の右側「定期給付債権(支分権)」)の消滅時効について、見ていきましょう。
(毎月発生するNHK受信料の)消滅時効の起算点
もう一度、上記最高裁判決を引用します。
| 最大判平成29年12月6日民集71巻10号1817頁 | |
|
Westlaw Japan 〔裁判要旨〕 ◆日本放送協会の放送の受信についての契約を締結した者は受信設備の設置の月から定められた受信料を支払わなければならない旨の条項を含む上記契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により同契約が成立した場合、同契約に基づき、受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する ◆日本放送協会の放送の受信についての契約に基づき発生する、受信設備の設置の月以降の分の受信料債権(上記契約成立後に履行期が到来するものを除く。)の消滅時効は、上記契約成立時から進行する |
|
つまり、こういうことです。
- NHKとの契約が成立した場合、テレビを設置した月から受信料の支払い義務が発生する。
- NHKとの契約が成立した場合、契約成立前に生じていた受信料の消滅時効は、契約成立のときから進行する。
(毎月発生するNHK受信料の)時効期間
「時効期間」とは、起算点とは「起算点」から何年経てば「消滅時効が完成するか」その期間のことです。別の最高裁判例も引用します。
| 最判平成26年9月5日裁判集民247号159頁、裁判所ウェブサイト | |
|
Westlaw Japan 〔裁判要旨〕 ◆受信料が月額又は6箇月若しくは12箇月前払額で定められ、その支払方法が2箇月ごとの各期に当該期分を一括して支払う方法又は6箇月分若しくは12箇月分を一括して前払する方法によるものとされている日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間は、民法169条により5年と解すべきである。 |
|
平成26年最判は「民法169条により5年」といっていますので、民法169条を見てみましょう。なんと・・・平成26年最判の時点(改正前民法)にはあった民法169条が、改正後は無くなっています。
| 改正前民法 | 現行民法 <令和2年4月1日施行> | |
第168条(定期金債権の消滅時効)
|
第168条(定期金債権の消滅時効)
|
|
|
第169条(定期給付債権の短期消滅時効) 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。 |
第169条 (削除されて、全く違う条文に差し替えられています)
|
一瞬「5年では無くなってしまったのか?」と思いますよね。削除された理由は次のとおりです。
削除前169条の「[削除の趣旨]定期給付債権(支分権等)の消滅時効期間は、削除前169条により5年とされているが、原則的な債権の消滅時効期間を主観的起算点から5年とする改正がなされたので、多くの場合は、各支払期の到来時に、債権者は『権利を行使することができることを知』ることになり、定期給付債権の特則を定める意義はなくなる。そこで、削除前169条は削除された(『我妻・有泉コンメンタール民法[第8版]』344頁)」
つまり、NHK受信料の消滅時効期間は、民法166条1項に定められたとおりで(下記)、平成26年最判が変わったわけではありません。
| 民法第166条(債権等の消滅時効) | |
|
|
ある月の受信料(支分権)が時効消滅した場合、他の月の受信料(支分権)はどうなるか?
NHKの受信料(支分権)は、毎月請求され、毎月の請求分は、支払い期日(期限)が異なります。
(前掲平成26年最判は、毎月の受信料を定期給付債権(支分権)であると判断しています。)
したがって、消滅時効を迎える日も支払い期日ごとにそれぞれ異なります。
よって、NHKの受信料は、①消滅時効が成立している受信料と②成立していない受信料に分けられます。
また、消滅時効は、滞納を請求する訴訟中は完成しません(時効の完成猶予)し、判決や強制執行があったとき、債務者が返済の意思を示したときなどは時効はゼロからスタート(時効の更新)となります(民法147~152)。
ある月の受信料(支分権)が時効完成猶予や時効更新となった場合、他の月の受信料(支分権)はどうなるか?
消滅時効を援用する前に、裁判上の請求や、強制執行を受けたりした場合には、消滅時効は完成しません(時効の完成猶予:民法147Ⅰ、148Ⅰ、149、150、151)。
また、判決をとられたり、契約者が債務を承認したりした場合には、時効は最初からやり直しになります(時効の更新:民法147Ⅱ、148Ⅱ、152)。
NHK(債権者)側の行為:滞納月分をまとめて請求(民150:時効完成猶予)や訴訟(民147Ⅰ:時効完成猶予、同Ⅱ:時効更新)してきます。契約者(債務者)としては、支払期限から5年経過しているものについて消滅時効を援用したのち、残金を支払うことになるでしょう。
契約者(債務者)側の行為:
契約者が滞納受信料全額の支払い義務を承認した場合、滞納受信料全額について、消滅時効は更新されます(民法152)。
一方、契約者が滞納受信料の一部を弁済した場合、滞納額全額について消滅時効が更新されるのでしょうか、それとも他の月分の請求については消滅時効が完成する余地はあるのでしょうか?筆者は次のように考えます。
すなわち、NHK受信料は月ごとに発生する債務ですので定期給付債権です。したがって、消滅時効更新事由の有無については、それぞれの月ごとに判断し、一部弁済によって、全体の消滅時効が更新されることはありません。
次に、一部のみの弁済は、民法488条によって充当処理すべきと考えます。すなわち、どの月の受信料に充当されるのかは、次のように決定します。
- 契約者が弁済時に指定したときはその債務に充当され(488Ⅰ)、
- 契約者が弁済時に指定しなかったときは、NHKが指定し(488Ⅱ)、
- 契約者もNHKもいずれもが指定していなかったときは、法定充当(民488Ⅳ)により処理することになります。さらに、弁済期にない受信料の請求を受けることはありません(民488Ⅳ①)から、全ての債務が弁済期にあるときとして「債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する」ことになります(民488Ⅳ②)。
消滅時効が完成して援用を待っている月の請求に充当する利益は、契約者(債務者)にはありませんから「時効完成間際で時効完成していない受信料に充当された」と考えるべきです【1】。
なお、2回目の催告(手紙による請求)は、時効の完成猶予の効力を有しない(民150Ⅱ)ので、消滅時効の完成が間近な場合には、NHKは裁判上の請求(訴訟)を行うこともあるようですので、ご注意ください。
| 民法第488条(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当) | |
|
|
【1】もっとも「債務者のために弁済の利益が多いもの」を勘案するに際して、消滅時効完成の有無をも対象とすべきという論考は見当たりませんので、あくまで筆者の私見です(『民法講義IV新訂債権総論』286頁、『注釈民法第12巻債権⑶』216頁、等を参照)。
相続が発生した場合の対応
NHK受信契約の解約
相続が発生し、どなたもお住まいにならなくなった場合には「NHK受信契約を解約」することで、新たな受信料【1】が発生しなくなります。
また、消滅時効完成を待とうとしても、解約をしなければ新たな受信料が発生するだけ(1か月分時効消滅しても、1か月分新たに発生するだけ)ですので、早めに解約した方が無難です。
なお、虚偽の届出には「割増金制度(料金倍額)」が適用されることがありますので、ご注意ください。
【1】受信料が発生しなくなるのは「解約受理の翌月から」です。
相続開始前に発生していた未払い受信料の性質
可分債務として、各相続人が、法定相続分ずつの割合で未払受信料を負担することになります。
未払いのNHK受信料は債務ですので、仮に「相続人のうち1名が、未払いのNHK受信料全額を負担する」旨の遺産分割協議をしても、NHKの承諾がなければ、一人の相続人に全額を負担することはできません。
相続開始後、解約までに発生した未払い受信料の性質
相続人が、連帯して未払受信料全額を負担することになると思われます。
相続開始の前後を問わず、相続人の皆様が足並みを揃えてご対応いただく必要があります。
未払い受信料があっても、必ずしも全額を支払う必要はない
消滅時効完成後の債務承認にならないよう「消滅時効援用と(消滅時効が完成していない債務へ)充当する旨の通知」をしてから支払う必要があります。
また、相続財産に関する時効の完成猶予(民160)がありますので、相続人が消滅時効援用通知をする際には、ご注意ください。
|
民法第160条(相続財産に関する時効の完成猶予) |
|
| 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 | |
人気の関連ページ
参考文献
- 我妻栄 著『民法講義IV新訂債権総論』岩波書店/1964年
- 磯村哲/編集『注釈民法第12巻債権⑶債権の消滅 -- 474条~520条【復刊版】』有斐閣/2013年
- 我妻榮 有泉亨 清水誠 田山輝明 著『我妻・有泉コンメンタール民法[第8版] 総則・物権・債権』(日本評論社、2022年)
 企業・事業者向けサービス
企業・事業者向けサービス
 トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)
トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)



















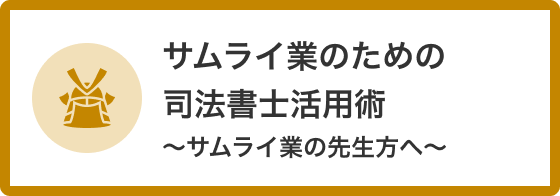
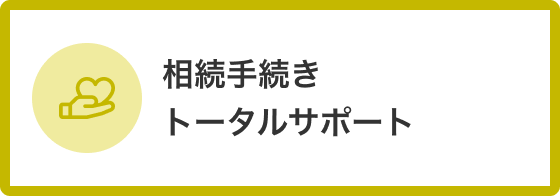
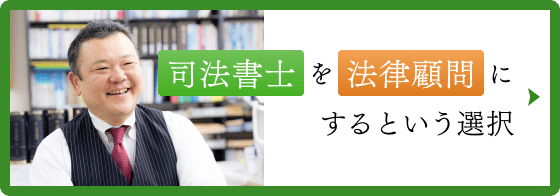

 個人向けサービス
個人向けサービス