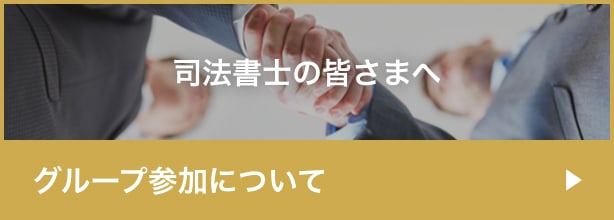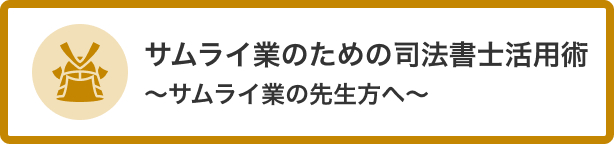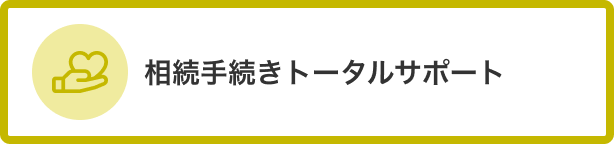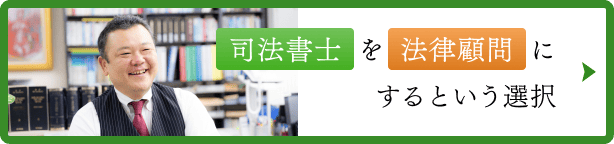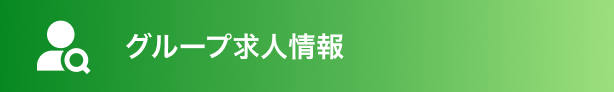- 不動産名義変更・不動産登記TOP
- 終活(成年後見・家族信託・遺言)TOP
- 相続手続き・遺産整理TOP
- ▼知ってお得な相続知識(もくじ)▼
- 相続クイズ50問(間違いだらけのネット情報)
- 自分で相続登記手続をした方に聞きました「相続手続で苦労した理由!ベスト10」
- 相続に関与しようとする民間資格や民間団体にご注意ください。
- 最期の時が近づいたとき(葬儀前に)ご家族が確認・準備するべきこと
- 相続開始直後(葬儀後すぐ)に行なうべき手続一覧
- 相続手続トータルサポート
- 遺言寄付の受け入れトータルサポート
- 相続は早い者勝ちになりました
- 相続登記・遺贈登記の特急申請(グループ会員限定記事)
- 銀行・信託銀行の相続手続は、本当に「質の悪いブランド品」なのか?!士業の相続手続と徹底比較!
- 法定相続情報~ややこしい戸籍を読むのは司法書士が一回で十分です。銀行預金の相続手続前に司法書士にご依頼ください。
- 相続による銀行口座凍結とは?!
- 銀行預金の仮払制度(遺産分割前の預金払戻し制度)
- ▼相続財産の調査(もくじ)▼
- 相続によって引き継ぐ財産・引き継がない財産(相続の対象財産)
- 行方不明の相続預金・相続貯金の探索
- 相続で負債・借金がないかの調査方法
- 被相続人の遺品の中から、相続人や第三者名義の通帳が出てきた場合どうすれば良いのか?(いわゆる名義預金の問題)
- 相続登記や遺言の際に欠かせない不動産の近隣地調査(名寄せ)
- 相続生命保険の調査
- ▼相続人の調査(もくじ)▼
- 相続人は誰か❶基本編(法定相続人・法定相続分)
- 相続人は誰か❷数次相続・再転相続・代襲相続の区別
- 子が親より(妻が夫より)①先に死亡したとき、②同時に死亡したとき、③死亡の先後が分からないときの相続(同時存在の原則、同時死亡の推定)
- 義父母の遺産を受け取る「特別寄与料制度」
- 相続手続のための戸籍収集
- 戸籍の広域交付制度とその盲点
- あなたの戸籍謄本(住民票)が取得されましたとの通知を受けた方へ:本人通知制度
- 旧民法(明治民法・応急措置法)による相続
- ▼相続税申告の要否▼
- ▼遺産分割協議(もくじ)▼
- 遺産分割協議書の基礎知識、作成の流れ
- 遺産分割協議の種類と流れ
- 遺産分割協議の期間制限
- 一次相続の遺産分割協議では、二次相続のことも考えましょう。
- 相続分の譲渡・相続分の放棄
- 平成13年6月までに相続開始又は代襲原因発生の場合は注意「非嫡出子の法定相続分」
- 特別受益証明書(相続分ないことの証明書)による相続登記が流行した理由、消滅した理由から、特別受益証明書の可能性を探る
- 配偶者居住権(2020.4.1以降開始相続)
- 配偶者居住権の法的性質
- 配偶者短期居住権(2020.4.1以降開始相続)
- ▼不動産の相続手続(もくじ)▼
- 不動産の相続手続(相続登記)
- 相続登記後、売却する不動産は誰名義で相続登記したら良いですか?!
- 相続不動産売却サポート
- 何代も前の相続で、途中の相続登記を省略できる場合~数次相続で中間省略登記が認められる条件
- 相続登記に上申書が必要な場合(戸籍不足の相続登記)
- 進まない相続登記(協力しない相続人がいる場合、相続人が何十人もいる場合)の対応【調停や判決による相続登記】
- 長期相続登記未了の通知を受けた方へ/法定相続人情報
- 相続登記義務化:令和6(2024)年4月1日施行
- 相続登記義務を免れるための「相続人申告登記」の意味と申請手続
- 所有者不明土地問題を解消するための法改正と施行時期【一覧】
- 相続した土地を国に引き取って貰う制度『相続土地国庫帰属法』令和5(2023)年4月27日施行
- ▼不動産以外の相続手続(もくじ)▼
- 銀行預金・郵便貯金の相続手続
- 上場株式・非上場株式(株券)の相続手続
- 生命保険の相続手続・税金・遺言執行
- ゴルフ会員権の相続手続
- デジタル遺産の相続手続
- 未支給年金の相続手続
- 自動車の相続手続
- ▼借金貸付金の相続手続(もくじ)▼
- 他人への貸付金(借主)に相続が発生したときの債権者の対応
- 他人への貸付金(貸主)の相続手続
- 借金の相続手続
- NHK未払い受信料の相続手続
- 相続承認・放棄の期間伸長の申立
- 相続放棄(申述)の意味と申立手続
- 相続放棄(申述)できなくなる法定単純承認とは?
- 法定単純承認となることなく、遺品を処分することは可能か?!
- 相続放棄(申述)をしても免れないことがある?!固定資産税・都市計画税のハナシ
- 相続放棄(申述)と数次相続・代襲相続
- 遺贈の放棄|遺言で受けた贈与(遺贈)を放棄する方法は、遺言の書き方によって異なります。
- 限定承認の意味と方法
- ▼遺言があるときの相続(もくじ)▼
- 遺言書を探す方法(公正証書遺言、法務局保管自筆証書遺言の探索)
- 遺言検認申立
- 遺言執行者選任申立
- 遺言解釈・遺言執行
- 遺言解釈(受遺者や受益相続人が遺言者よりも①先に死亡したとき、②同時に死亡したとき)
- 遺言解釈(負担付遺贈か条件付遺贈か)
- 遺言解釈(負担付遺贈を受遺者が放棄した場合)
- 遺言解釈(負担付遺贈の受遺者が負担を履行しないとき)
- ▼相続に関する他の手続(もくじ)▼
- 外国(海外)在住日本人の相続手続・相続放棄手続とその必要書類(在留証明・署名証明・法定相続情報・日本公証役場)
- 日本在住外国人の相続手続(各国の相続法)
- 特別代理人選任申立(未成年者がいる場合の遺産分割協議)
- 不在者財産管理人選任申立
- 失踪宣告申立
- (民法952条の)相続財産清算人選任申立
- 相続財産法人への登記名義人氏名変更登記
- 特別縁故者からの相続財産の分与請求
- 他の共有者が死亡したとき、どうすれば良いのか?!~共有者の相続人への共有物分割請求~
- 相続・遺産分割のトラブル解決
- 契約書作成・精査
- 外国人の帰化
旧民法(明治民法・応急措置法)による相続

令和6(2024)年4月1日に始まった「相続登記義務化」。
その影響からか、大昔に発生していた相続登記のご依頼も増えてきました。ところが、法律は改正されていきますので、被相続人が亡くなった日によって、法定相続人も、法定相続分も、代襲相続の有無等も変わります。
この記事では、被相続人が亡くなった日によって変わる、法定相続人・法定相続分・代襲相続の有無等について、解説しています。
| もくじ | |
|
〔凡例〕この記事では、次の法令が出てきます。法令名が長いときは、次のとおり略記します。
- 明治民法:民法(制定:明治29年4月27日法律第89号)。日本国憲法の施行により、廃止されたわけではなく、現行民法に至るまで改正され続けています。この記事では、家督相続制度や家制度が規定されている当時の民法を「明治民法」といいます。
- 応急措置法:日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(昭和22年法律第74号)
- 現行民法:民法(制定:明治29年4月27日法律第89号、施行:令和7年10月1日)
法改正の概要
相続法は、大きく分けて3回改正されています。
被相続人の死亡の日によって適用される法律が異なります。
明治民法(明治~昭和22年5月2日)
昭和22年以前は家父長制や家制度がありました。
相続でも、戸主か、それ以外かによって、取扱いが全く異なります。
まず、戸主については「家督相続」制度で、一人が全てを相続します。
一方、戸主以外の家族については「遺産相続」制度です。
終戦(昭和20年8月15日)
応急措置法(昭和22年5月3日~昭和22年12月31日)
日本国憲法の施行によって「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の理念が導入されることになりましたので、旧民法の家父長制や家制度(家督相続など)が憲法に反するものとなりました。しかし、民法全体を見直すためには、時間を要するため、暫定的に制定されたのが、応急措置法です。
新民法の施行と改正(昭和23年1月1日~)
昭和23年1月1日、旧民法の家父長制や家制度(家督相続など)を廃止した新民法が施行されました。
それ以降も、時代の要請に応じて、配偶者の法定相続分の強化、非嫡出子と嫡出子の法定相続分の平等化などの改正が行われました。
被相続人の死亡日と適用される法律(相続形態/法定相続人/法定相続分/代襲の有無)
「被相続人が亡くなった日」によって適用される法律をさらに細かく分類し、解説したのが下表です。
法定相続人・法定相続分・代襲相続発生の有無などが異なります。
|
被相続人の 死亡の日 |
相続形態 | 法定相続人【相続分/代襲相続の有無】 |
| ~昭和22.5.2 |
戸主の死亡・ 隠居・国籍喪失等 ▼ 家督相続 (明治民法【1】) |
引取入籍等の場合の例外あり 第1.家族たる直系卑属(法定家督相続人)【全部/代襲相続あり】
第2 被相続人が指定した者(指定家督相続人)【全部/代襲相続なし】 第3 親族会等が法定の家族中から選定した者(第一種選定家督相続人)【全部/代襲相続なし】 第4 家族たる直系尊属(法定・指定・選定の相続人のいない場合)【全部/代襲相続なし】
第5 親族会が選定した者(第二種選定家督相続人)【全部/代襲相続なし】 例外 女戸主の入夫【全部/代襲相続なし】 当事者の反対の意思あるときはこの限りでない。 |
|
戸主の死亡 ▼ 相続 |
法定・指定・選定の家督相続人のいない場合 ☛現行民法相続と同じ(現行民法附則25条【3】) |
|
|
家族の死亡 ▼ 遺産相続 (明治民法【1】) |
第1 直系卑属【全部/代襲相続あり】 親等の近い者が先 数人いる場合は均分 非嫡出子は嫡出子の半分 第2 配偶者【全部/代襲相続なし】 第3 直系尊属【全部/代襲相続なし】 親等の近い者が先 第4 戸主【全部/代襲相続なし】 |
|
|
<大改正> |
||
|
昭和22.5.3~ 昭和22.12.31 |
相続 (応急措置法【2】) |
配偶者は常に相続人【代襲相続なし】 第1 直系卑属【配偶者:直系卑属=1/3:2/3/代襲相続あり】 親等の近い者が先 数人いる場合は均分 非嫡出子は嫡出子の半分 第2 直系尊属【配偶者:尊属=1/2:1/2/代襲相続なし】 親等の近い者が先 数人いる場合は均分 第3 兄弟姉妹【配偶者:兄弟姉妹=2/3:1/3/代襲相続なし】 数人いる場合は均分 半血と全血の区別なし 第1第2第3がいないとき【配偶者=全部】 |
|
昭和23.1.1~ 昭和55.12.31 |
相続【3】 |
配偶者は常に相続人【代襲相続なし】 第1 直系卑属【配偶者:直系卑属=1/3:2/3/代襲相続あり】 数人いる場合は均分 非嫡出子は嫡出子の半分 第2 直系尊属【配偶者:尊属=1/2:1/2/代襲相続なし】 親等の近い者が先 数人いる場合は均分 第3 兄弟姉妹【配偶者:兄弟姉妹=2/3:1/3/代襲相続あり(どこまでも)】 数人いる場合は均分 半血は全血の半分 第1第2第3がいないとき【配偶者=全部】 |
|
昭和56.1.1~ 平成12.9.18 |
相続 |
配偶者は常に相続人【代襲相続なし】 第1 直系卑属【配偶者:直系卑属=1/2:1/2/代襲相続あり】 数人いる場合は均分 非嫡出子は嫡出子の半分 第2 直系尊属【配偶者:尊属=2/3:1/3/代襲相続なし】 数人いる場合は均分 第3 兄弟姉妹【配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4/代襲相続あり(一代のみ)】 数人いる場合は均分 半血は全血の半分 第1第2第3がいないとき【配偶者=全部】 |
|
平成12.9.19~平成13.6 |
相続【4】 |
非嫡出子は嫡出子の半分か、同じか不明 (最高裁が判断していない期間) |
|
平成13.7~ |
相続 (現行民法【5】) |
非嫡出子の法定相続分は、嫡出子と同じ(最大決平成25年9月4日、平成25年12月11日民法改正) |
【2】日本国憲法の施行によって「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の理念が導入されることになりましたので、旧民法の家父長制や家制度(家督相続など)が憲法に反するものとなりました。しかし、民法全体を見直すためには、時間を要するため、暫定的に制定されたのが、応急措置法です。
応急措置法が適用される期間は、わずか6か月ほどです。
| 日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(昭和22年法律第74号) | |
|
第一条 この法律は、日本国憲法の施行に伴い、民法について、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚する応急的措置を講ずることを目的とする。 第二条 妻又は母であることに基いて法律上の能力その他を制限する規定は、これを適用しない。 第三条 戸主、家族その他家に関する規定は、これを適用しない。 第四条 成年者の婚姻、離婚、養子縁組及び離縁については、父母の同意を要しない。 第五条 夫婦は、その協議で定める場所に同居するものとする。 夫婦の財産関係に関する規定で両性の本質的平等に反するものは、これを適用しない。 配偶者の一方に著しい不貞の行為があつたときは、他の一方は、これを原因として離婚の訴を提起することができる。 第六条 親権は、父母が共同してこれを行う。 父母が離婚するとき、又は父が子を認知するときは、親権を行う者は、父母の協議でこれを定めなければならない。協議が調わないとき、又は協議することができないときは、裁判所が、これを定める。 裁判所は、子の利益のために、親権者を変更することができる。 第七条 家督相続に関する規定は、これを適用しない。 相続については、第8条及び第9条の規定によるの外、遺産相続に関する規定に従う。 第八条 直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹は、その順序により相続人となる。 配偶者は、常に相続人となるものとし、その相続分は、左の規定に従う。 一 直系卑属とともに相続人であるときは、3分の1とする。 二 直系尊属とともに相続人であるときは、2分の1とする。 三 兄弟姉妹とともに相続人であるときは、3分の2とする。 第九条 兄弟姉妹以外の相続人の遺留分の額は、左の規定に従う。 一 直系卑属のみが相続人であるとき、又は直系卑属及び配偶者が相続人であるときは、被相続人の財産の2分の1とする。 二 その他の場合は、被相続人の財産の3分の1とする。 第十条 この法律の規定に反する他の法律の規定は、これを適用しない。 附 則 1 この法律は、日本国憲法施行の日〔筆者注:昭和22年5月3日〕から、これを施行する。 2 この法律は、昭和23年1月1日から、その効力を失う。 (以上、国立公文書館デジタルアーカイブ/最終アクセス251013) |
|
|
【3】新法、旧法、応急措置法の適用関係については、民法附則を確認する必要があります。 現行民法附則(昭和22年12月22日法律第222号) |
|
|
第1条 この法律は、昭和23年1月1日から、これを施行する。 第2条 明治35年法律第37号は、これを廃止する。 第3条 この附則で、新法とは、この法律による改正後の民法をいい、旧法とは、従前の民法をいい、応急措置法とは、昭和22年法律第74号をいう。 第4条 新法は、別段の規定のある場合を除いては、新法施行前に生じた事項にもこれを適用する。但し、旧法及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない。 (中略) 第25条 応急措置法施行前に開始した相続に関しては、第2項の場合を除いて、なお、旧法を適用する。 ② 応急措置法施行前に家督相続が開始し、新法施行後に旧法によれば家督相続人を選定しなければならない場合には、その相続に関しては、新法を適用する。但し、その相続の開始が入夫婚姻の取消、入夫の離婚又は養子縁組の取消によるときは、その相続は、財産の相続に関しては開始しなかつたものとみなし、第28条の規定を準用する。 第26条 応急措置法施行の際における戸主が婚姻又は養子縁組によつて他家から入つた者である場合には、その家の家附の継子は、新法施行後に開始する相続に関しては、嫡出である子と同一の権利義務を有する。 ② 前項の戸主であつた者について応急措置法施行後新法施行前に相続が開始した場合には、前項の継子は、相続人に対して相続財産の一部の分配を請求することができる。この場合には、第二十七条第二項及び第三項の規定を準用する。 ③ 前二項の規定は、第一項の戸主であつた者が応急措置法施行後に婚姻の取消若しくは離婚又は縁組の取消若しくは離縁によつて氏を改めた場合には、これを適用しない。 第27条 第二十五条第二項本文の場合を除いて、日本国憲法公布の日以後に戸主の死亡による家督相続が開始した場合には、新法によれば共同相続人となるはずであつた者は、家督相続人に対して相続財産の一部の分配を請求することができる。 ② 前項の規定による相続財産の分配について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家事審判所に対し協議に代わる処分を請求することができる。但し、新法施行の日から一年を経過したときは、この限りでない。 ③ 前項の場合には、家事審判所は、相続財産の状態、分配を受ける者の員数及び資力、被相続人の生前行為又は遺言によつて財産の分配を受けたかどうかその他一切の事情を考慮して、分配をさせるべきかどうか並びに分配の額及び方法を定める。 第28条 応急措置法施行の際戸主であつた者が応急措置法施行後に婚姻の取消若しくは離婚又は養子縁組の取消若しくは離縁によつて氏を改めた場合には、配偶者又は養親、若し配偶者又は養親がないときは新法によるその相続人は、その者に対し財産の一部の分配を請求することができる。この場合には、前条第二項及び第三項の規定を準用する。 第29条 推定の家督相続人又は遺産相続人が旧法第九百七十五条第一項第一号又は第九百九十八条の規定によつて廃除されたときは、新法の適用については、新法第八百九十二条の規定によつて廃除されたものとみなす。 第30条 旧法第九百七十八条(旧法第千条において準用する場合を含む。)の規定によつて遺産の管理についてした処分は、相続が第二十五条第二項本文の規定によつて新法の適用を受ける場合には、これを新法第八百九十五条の規定によつてした処分とみなす。 第31条 応急措置法施行前に分家又は廃絶家再興のため贈与された財産は、新法第九百三条の規定の適用については、これを生計の資本として贈与された財産とみなす。 第32条 新法第906条及び第907条の規定は、第25条第1項の規定によつて遺産相続に関し旧法を適用する場合にこれを準用する。 第33条 新法施行前に旧法第千七十九条第一項の規定に従つてした遺言で、同条第二項の規定による確認を得ないものについては、新法第九百七十九条第二項及び第三項の規定を準用する。 ② 新法施行前に海軍所属の艦船遭難の場合に旧法第千八十一条において準用する旧法第千七十九条第一項の規定に従つてした遺言で、同条第二項の規定による確認を得ないものについても、前項と同様である。 |
|
【4】記事「平成13年6月までに相続開始又は代襲原因発生の場合は注意『非嫡出子の法定相続分』」を参照ください。
【5】現行民法および数年前の民法までは、e-Gov法令検索『民法』で確認できます。
それ以前のものは、WestlawJapanなどの有料サイトで確認できます。
| 現行民法 | |
|
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。 (子及びその代襲者等の相続権) 第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 第八百八十八条 削除 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二 被相続人の兄弟姉妹 2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。 (配偶者の相続権) 第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 |
|
 企業・事業者向けサービス
企業・事業者向けサービス
 トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)
トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)



















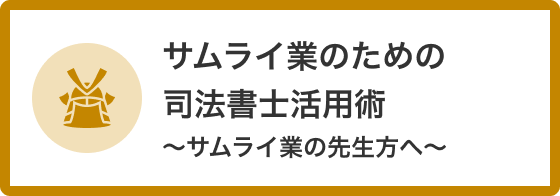
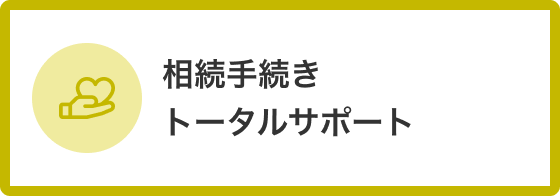
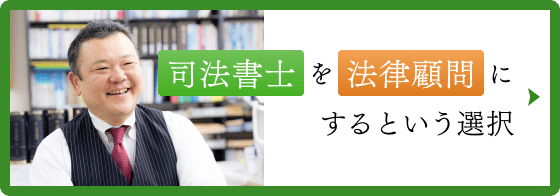

 個人向けサービス
個人向けサービス