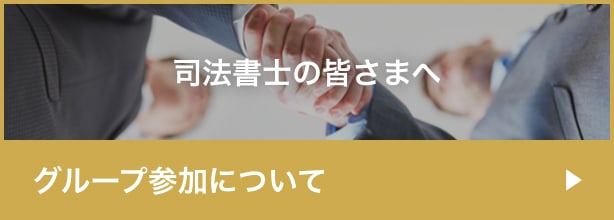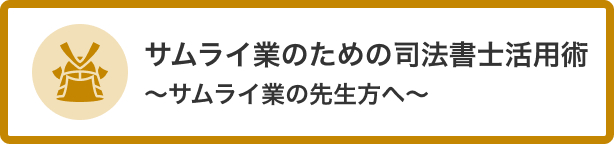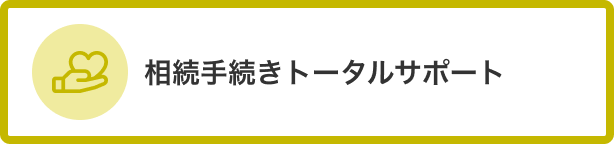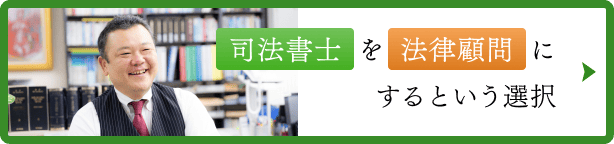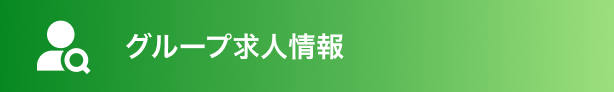- トラブル解決総論
- 相続・遺産分割トラブル解決
- 夫婦子供のトラブル解決
- その他親族トラブル解決
- 企業・事業者のトラブル解決
- 不動産・借地借家・隣近所のトラブル解決
- 不動産の取得時効と登記の関係
- 不動産賃貸借における関西方式・関東方式
- 敷金・保証金・建設協力金の違い
- 賃貸借契約の当事者が変更した場合、誰が誰に敷金を返せば良いか?
- 敷引特約の有効性
- 賃貸借契約で「中途解約を禁止する条項」は有効か?
- 賃貸借契約における更新料条項の有効性、更新料不払いの効果、法定更新との関係ほか後日もめないための具体的な対策
- 賃貸借契約で遅延損害金を年14.6%とする条項は有効か?
- 明渡しが遅れたときに賃料倍額の使用損害金を請求する条項は有効か?
- 滞納賃料(家賃・地代)の請求を受けた連帯保証人の対応
- 借主の軽微な契約違反だけでは解除できない賃貸借契約「信頼関係破壊の法理」
- 家賃滞納による建物明渡請求
- 賃借人が連帯保証人を立てない場合、賃貸人は賃貸借契約を解除できるか?!
- 賃料(地代・家賃)増減額請求
- 借地に関する契約
- 借地権登記できない場合の「借地上の建物登記」民法177条の例外
- 建物賃貸借の契約期間を設定するときの注意点
- 借地上の建物を賃貸借するときの注意点
- 定期借家契約のメリットと注意点
- DIY型賃貸借契約のメリットと注意点
- 原状回復・敷金返還に関するトラブル解決
- 建物賃貸借で「通常損耗をも借家人負担とする」特約の有効性
- 原状回復義務と明渡義務の関係|原状回復が終わらないと、建物明渡し完了にならない?!
- マンションの滞納管理費・修繕費・積立金の回収
- マンション義務違反者への対応
- 連棟建物(長屋、二戸一、三戸一)の切り離しトラブル
- マンション上階や二戸一の隣家からの水漏れトラブル解決
- 隣近所とのトラブル解決
- 隣地の建築計画はどこで確認するか?!宅地開発から建物建築までの流れ
- 建物建築に際しての周辺住民への説明義務
- 隣地が境界ギリギリに建築するのを止められませんか?!
- 崖地の擁壁・石垣の補修に関するトラブル【図解】
- 隣地に対する目隠し設置請求権
- 境界トラブル(筆界と所有権界)
- 私道の通行権をめぐるトラブル
- (ケガの後遺症や精神疾患などが原因で)騒音、大声、奇行などの問題行動をおこし周囲に迷惑をかけている方への対応(グループ会員限定記事)
- 交通事故解決
- 消費者トラブルの解決
- 借金が返済できないときの個人の債務整理(任意整理・民事再生・自己破産)
- 判決が出ても従わない相手方への強制執行による債権回収(差押え)
- 仮差押・仮処分など保全処分
- 刑事事件(被害者・加害者)
- 少年事件(被害者・加害者)

賃貸借契約終了後、過大な原状回復費の請求を受けているというご相談が多数あります。
その中には「家主から『通常損耗も賃借人負担とする』特約があるから、原状回復費を全額負担せよ」と言われているケースもあります。このような特約は有効なのでしょうか?
この記事では「通常損耗も賃借人負担とする」特約の有効性について、判例やガイドラインをご紹介しています。
一般的な原状回復の考え方については、記事「原状回復・敷金返還に関するトラブル解決」をご参照ください。
| もくじ | |
|
修繕費負担に関する原則
民法
| 民法606条(賃貸人による修繕等) | |
|
|
民法には上記のような規定がありますが、この条文は強行規定ではありませんので、当事者間の合意で変更する(特約で借家人負担と定める)ことができます。
借地借家法
賃貸借契約を考えるときには、借地借家法もチェックする必要があります。
条文を読みやすいように〔〕部分は筆者が追記しました。
| 借地借家法37条(強行規定) | |
| 第31条〔借賃増減請求権〕、第34条〔建物賃貸借終了の場合における転借人の保護〕及び第35条〔建物賃貸借終了の場合における転借人の保護〕の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。 | |
借地借家法が強行規定と定めているものの中には、修繕義務についてはありません。
したがって、修繕費の負担を、借家人負担とすることも問題ないことが分かります。
判例とガイドライン
平成10年3月国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を発表
原状回復費の負担に関して、貸主と借主の認識が異なりトラブルが絶えませんでした。
そこで旧・建設省が「トラブルが急増し、大きな問題となっていた賃貸住宅の退去時における原状回復について、原状回復にかかる契約関係、費用負担等のルールのあり方を明確」化するために公表したのが「ガイドライン」です。
「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』について/国交省HP」から抜粋します。
- 現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則ですが、契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、このガイドラインを参考にしながら話し合いをして下さい。
- 原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
⇒ 原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html/最終アクセス240108
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」からも抜粋します。
- 民間賃貸住宅の賃貸借契約については、契約自由の原則により、民法、借地借家法等の法令の強行法規に抵触しない限り有効であって、その内容について行政が規制することは適当ではない。本ガイドラインは、近時の裁判例や取引等の実務を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方等について、トラブルの未然防止の観点からあくまで現時点において妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとしてとりまとめたものである(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)/国土交通省住宅局/平成23年8月/1頁。以下、特に指定しない限り再改訂版のページ数のみ記載します。)。
- 原状回復を次のとおりに定義した。「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」(8頁)

平成13年4月1日消費者契約法が施行される。
居住用建物の賃貸借契約は、消費者契約です(消契法2Ⅲ)。
消費者契約法の施行によって「通常損耗を賃借人負担とする特約」が「消費者の利益を一方的に害するもの」として無効となるか否か(消契法10)が多くの裁判で争われることになります。
|
消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効) |
|
| 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 | |
最判平成17年12月16日裁判集民218号1239頁
同最判は、賃貸借建物の通常の使用に伴い生ずる損耗について賃借人が原状回復義務を負う旨の特約が成立していないとされた事例です。
原状回復の「負担区分表」に賃借人負担であると記載しただけでは、特約は成立しないとしているのです。少し長めに引用します。
| 最判平成17年12月16日裁判集民218号1239頁 | |
|
1 原審の確定した事実関係の概要等は、次のとおりである。 (1) 略 (2) 略 (3) 被上告人は、平成9年12月8日、本件共同住宅の入居説明会を開催した。同説明会においては、参加者に対し、本件共同住宅の各住宅部分についての賃貸借契約書、補修費用の負担基準等についての説明が記載された「すまいのしおり」と題する書面等が配布され、約1時間半の時間をかけて、被上告人の担当者から、特定優良賃貸住宅や賃貸借契約書の条項のうち重要なものについての説明等がされたほか、退去時の補修費用について、賃貸借契約書の別紙「大阪府特定優良賃貸住宅and・youシステム住宅修繕費負担区分表(一)」の「5.退去跡補修費等負担基準」(以下「本件負担区分表」という。)に基づいて負担することになる旨の説明がされたが、本件負担区分表の個々の項目についての説明はされなかった。 上告人は、自分の代わりに妻の母親を上記説明会に出席させた。同人は、被上告人の担当者の説明等を最後まで聞き、配布された書類を全部持ち帰り、上告人に交付した。 (4) 上告人は、平成10年2月1日、被上告人との間で、本件住宅を賃料月額11万7900円で賃借する旨の賃貸借契約を締結し(以下、この契約を「本件契約」、これに係る契約書を「本件契約書」という。)、その引渡しを受ける一方、同日、被上告人に対し、本件契約における敷金約定に基づき、敷金35万3700円(以下「本件敷金」という。)を交付した。 なお、上告人は、本件契約を締結した際、本件負担区分表の内容を理解している旨を記載した書面を提出している。 (5) 本件契約書22条2項は、賃借人が住宅を明け渡すときは、住宅内外に存する賃借人又は同居者の所有するすべての物件を撤去してこれを原状に復するものとし、本件負担区分表に基づき補修費用を被上告人の指示により負担しなければならない旨を定めている(以下、この約定を「本件補修約定」という。)。 (6) 本件負担区分表は、補修の対象物を記載する「項目」欄、当該対象物についての補修を要する状況等(以下「要補修状況」という。)を記載する「基準になる状況」欄、補修方法等を記載する「施工方法」欄及び補修費用の負担者を記載する「負担基準」欄から成る一覧表によって補修費用の負担基準を定めている。このうち、「襖紙・障子紙」の項目についての要補修状況は「汚損(手垢の汚れ、タバコの煤けなど生活することによる変色を含む)・汚れ」、「各種床仕上材」の項目についての要補修状況は「生活することによる変色・汚損・破損と認められるもの」、「各種壁・天井等仕上材」の項目についての要補修状況は「生活することによる変色・汚損・破損」というものであり、いずれも退去者が補修費用を負担するものとしている。また、本件負担区分表には、「破損」とは「こわれていたむこと。また、こわしていためること。」、「汚損」とは「よごれていること。または、よごして傷つけること。」であるとの説明がされている。 (7) 略 2 略 3 略 4 しかしながら、上記2の①の点に関する原審の上記判断のうち(2)は是認することができない。その理由は、次のとおりである。 (1) 賃借人は、賃貸借契約が終了した場合には、賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務があるところ、賃貸借契約は、賃借人による賃借物件の使用とその対価としての賃料の支払を内容とするものであり、賃借物件の損耗の発生は、賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものである。それゆえ、建物の賃貸借においては、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、通常、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている。そうすると、建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約(以下「通常損耗補修特約」という。)が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。 (2) これを本件についてみると、本件契約における原状回復に関する約定を定めているのは本件契約書22条2項であるが、その内容は上記1(5)に記載のとおりであるというのであり、同項自体において通常損耗補修特約の内容が具体的に明記されているということはできない。また、同項において引用されている本件負担区分表についても、その内容は上記1(6)に記載のとおりであるというのであり、要補修状況を記載した「基準になる状況」欄の文言自体からは、通常損耗を含む趣旨であることが一義的に明白であるとはいえない。したがって、本件契約書には、通常損耗補修特約の成立が認められるために必要なその内容を具体的に明記した条項はないといわざるを得ない。被上告人は、本件契約を締結する前に、本件共同住宅の入居説明会を行っているが、その際の原状回復に関する説明内容は上記1(3)に記載のとおりであったというのであるから、上記説明会においても、通常損耗補修特約の内容を明らかにする説明はなかったといわざるを得ない。そうすると、上告人は、本件契約を締結するに当たり、通常損耗補修特約を認識し、これを合意の内容としたものということはできないから、本件契約において通常損耗補修特約の合意が成立しているということはできないというべきである。 |
|
最判平成17年12月16日以降の裁判例
追って掲載していきます。
令和5年3月国土交通省「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』に関する参考資料」を発表
国交省は令和5年3月「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に関する参考資料を公表しています。参考になりますので、同参考資料8頁以下を引用します。
賃借人に特別の負担を課す特約の成立要件(②の解説):ガイドライン 6~7頁関連
賃貸借契約では、契約自由の原則により(民法521 条)、賃借人に特別の負担を課す特約を設けることもできますが、ガイドラインでは、最高裁判例や消費者契約法の規定を踏まえ、賃借人に特別の負担を課す特約が有効に成立するための3つの要件を記載しています。
|
- ①については、特約の内容が問題となります。客観的、合理的理由については、例えば、家賃を周辺相場に比較して明らかに安価に設定する代わりに、賃借人に特別な負担を課す場合等が考えられますが、限定的なものと解すべきとしています。
- ②③については、手続きが問題となります。賃借人が負担することとなる通常損耗等の範囲が契約書に明記されており、賃借人がその内容を理解し、契約内容とすることを明確に合意していることが必要としています。
- 退去時のトラブルを防止する観点から、賃借人が将来負担することになる原状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも重要と考えられます。
- 地方公共団体の条例等では、賃借人の負担内容(特約の有無や内容など)について、 宅地建物取引業者の重要事項説明と併せて、賃借人に別途書面を交付し、説明を行うことが義務付けられている場合があります。
~実務では~
- ペット飼育可の物件において、ペットによるひどいキズや汚れについては経過年数を考慮せず賃借人負担とするといった特約や、消毒・消臭費用を定額で徴収するといった特約が設けられている場合があるようです。
- また、喫煙によるヤニでの変色や臭いがひどいときについても、経過年数を考慮せず賃借人負担とするといった特約が設けられている場合があるようです。
- このような特約の有効性については、上記の要件に照らして個別の判断が必要ですが、入居中及び退去時のトラブルを防止するため、ペットの飼育や喫煙に関する契約内容については契約前によく確認しておくことが重要です。
 企業・事業者向けサービス
企業・事業者向けサービス
 トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)
トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)



















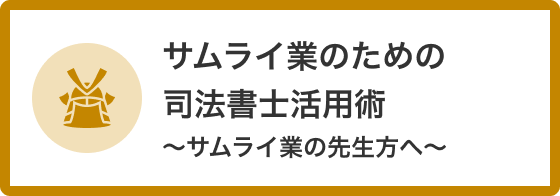
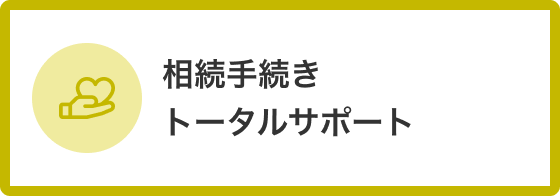
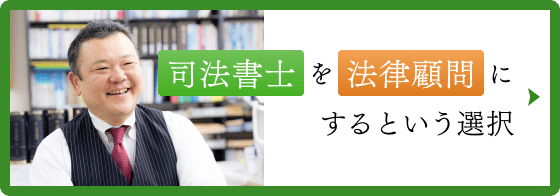

 個人向けサービス
個人向けサービス