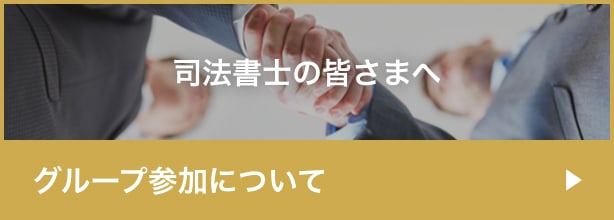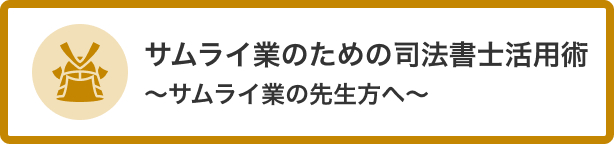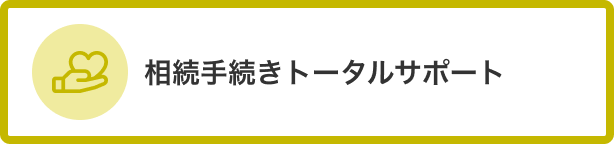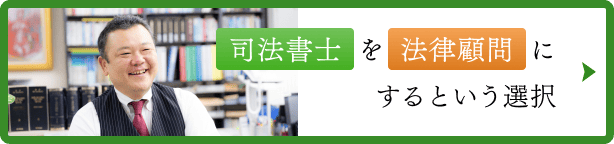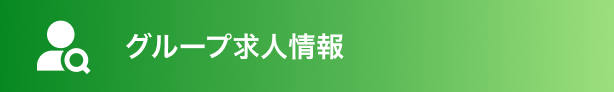- 司法書士による顧問契約のご紹介
- 従業員支援プログラム(EAP)
- 起業支援(会社団体の設立支援)
- スタートアップ(ベンチャー)支援/株式上場(IPO)支援
- 法務部門支援
- 内部統制システム(コーポレートガバナンス)構築支援
- 株主総会・取締役会など運営支援
- 組織再編(組織変更・合併・会社分割・株式移転など)
- 会社・法人の事業承継
- M&A・ジョイントベンチャー(合弁事業)
- 会社や法人の登記
- 会社の登記(はじめに)
- その会社登記は、いつもの司法書士で本当に大丈夫ですか?!
- 商業登記登録免許税の課税根拠表
- 会社法違反事件(選任懈怠・登記懈怠)の過料相場と、過料決定への即時抗告・異議申立
- 会社法違反事件(選任懈怠・登記懈怠)の過料を支払わなかったらどうなるのか?!
- 役員変更登記の論点(株式会社・有限会社)
- 代表取締役住所の非表示措置の是非
- 役員解任リスクとその回避方法
- 役員全員解任登記があった場合の法務局の取扱い(令和2年3月23日付法務省民商第65号法務省民事局商事課長通知)
- 役員任期一覧(会社・社団・法人)
- 役員を迎えるときの注意事項【一覧】
- 役員欠格事由一覧(会社・社団・法人)
- 社長住所・会社本店の表記はどこまで登記を省略できるか?
- 選任・選定・互選の意味~互選は過半数ではない
- 従業員→取締役→代表取締役と出世すると何が変わるのか?!
- 二人代表取締役ってどうでしょうか?!そのメリット・デメリットと「最強の二人代表取締役」になる方法
- 二人代表取締役とハンコ(法人実印)の関係
- 代表取締役と社長の違いー会社TOPが使うべき肩書きは何か?
- 定款変更「付則」の使い方・定め方
- 決算期(事業年度)変更の手続
- 会社の公告(その1)貸借対照表の公告(決算公告)で注意すべき事項
- 官報その他新聞の公告料金・申込掲載期間
- 種類株式(優先株)の設計・発行手続
- 種類株式の登記依頼をはじめて受けるときに読む記事(グループ会員限定記事)
- 種類株式の内容として登記できる事項、登記できない事項
- 株券不発行会社への移行の登記
- 株券発行会社への移行の登記(旧有限会社法、整備法、現行法)
- 株式会社の計算(はじめに)
- 資本金の額の増加
- デット・エクイティ・スワップ実行時の会社法207条9項4号と同5号の使いわけ基準
- 資本金の額の減少、資本準備金の額の減少
- 債権者保護手続の個別催告通知は、到達が必要です(スケジュールは余裕をもって設計ください)
- 支店登記(支店設置・支店移転・支店廃止)
- 工場抵当・工場財団
- 持株会設立・運用
- 動産譲渡登記・債権譲渡登記
- 新しく設立できないけれど実は優れもの?有限会社の特徴
- 有限会社の役員に関する登記
- 有限会社や合同会社の役員について「任期規定導入」の可否
- 持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)の登記事項と定款記載事項【社員・資本金】
- 合同会社の議案、その議決要件、定款による議決要件の変更(緩和・加重)
- 合同会社の計算
- 合同会社「資本金の額」増加
- 一般社団法人の運営と登記
- 一般財団法人の運営と登記
- 公益認定(一般社団法人・一般財団法人の公益法人化)の手続と登記
- 公益法人を一般社団法人・一般財団法人へ戻す手続き
- 各種法人に適用される実体法、登記手続法(商業登記法、商業登記規則、組合等登記令、各種法人等登記規則などの整理)
- NPO法人の一般社団法人への移行手続
- 社会福祉法人の登記
- 宗教法人の法人登記
- 宗教法人が不動産を取得する場合の非課税証明書・公衆礼拝用登記
- 宗教法人が不動産を売却する場合
- 外国会社の登記
- 会社登記事項が無効であるときの抹消登記
- 医療法人その他医療機関の登記
- 企業・事業者の資産管理・運用
- 会社の再生・倒産(負債が大きい会社)
- 会社の通常解散(負債が少ない会社の休業・廃業・解散)
- セミナー講師
資本金の額の減少、資本準備金の額の減少

「資本金の額の減少」は、様々な目的で行なわれます。
また、「資本準備金の減少」は、登記が発生しないため失念しがちですが「資本金の額の減少」同様、厳格な手続きが必要です(減少する資本準備金の全額を資本金に組入れる場合を除く。会社法449)。
目的に応じた手続きを採用することが大切です。
| もくじ | |
|
減資の種類
| 減資の種類 | 減資の目的 | 減資額の処理 | BSへの影響 |
| 実質上の減資【1】 | 現実に株主への払戻しなどを行ない、資本金を減少させる【2】 | 株主への払戻など | 会社の純資産が減少 |
| 名目上の減資 | 欠損金填補のため【3】 | 欠損金の填補 | 会社の純資産は変化なし(すでに欠損金が出ている)。 |
| 欠損金填補により利益配当を可能とするため【4】 | |||
| その他の減資 | 大会社(資本金5億円以上【5】)の要件から外れることで機関設計の簡素化を図るため | 準備金などへ | 資本金が準備金に名前を変える。純資産の変化はない |
| 外形標準課税の適用外(資本金1億円以下)の効果を得るため | |||
| 業種ごとに定められる「中小企業」の要件を充足させ助成金等を受給できるようにするため | |||
| 円滑化法が定める遺留分特例や納税猶予を利用できるようにするため | |||
| 法人住民税の税率を下げる | |||
| 再生などで、株主を入れ替えるための100%減資&増資 |
【1】実質上の減資は「資本金の額の減少」+「剰余金の配当」と整理されるため、「剰余金の配当規制」が適用されます。
すなわち、
- 純資産300万円以上ないと剰余金の配当はできない(会社458、453条)
- 分配可能額=その他資本剰余金の額+その他利益剰余金の額ー自己株式帳簿価額(会461ほか)
というルールがあります。
【2】例えば次のような場合です。
資本金2000万円の会社が1000万円に減資し、減少した1000万円を株主に払い戻す
【3】「欠損填補とは何か?」については、当メディアの「株式会社の計算(はじめに)」をご参照ください。
【4】例えば次のような場合です。
資本金2000万円の会社が1000万円の欠損金を出した場合、1000万円に減資することにより、欠損金を相殺する。また、欠損金がなくなる結果、株主への配当が可能となる。
【5】大会社の定義は、会社法2条6号。
| 会社法第2条(定義) | |
|
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 六 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。 イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第439条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第435条第1項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が5億円以上であること。 ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること。 |
|
大会社に該当するか否かの判断は、「最終事業年度に係る貸借対照表」を基準に行われます。これは、定時株主総会で承認または報告された最も新しい貸借対照表を指します。したがって、各事業年度における定時株主総会の時点で、大会社の要件に該当するかどうかが判断されます。
このため、事業年度の途中で増資や借入れにより資本金や負債の額が基準を超えたとしても、その時点では直ちに大会社とはなりません。例えば、3月決算の会社が期中に資本金が5億円以上になった場合でも、その事業年度の貸借対照表が承認・報告される翌年の定時株主総会の時点ではじめて大会社に該当することになります。
(相澤哲,葉玉匡美,郡谷大輔『論点解説 新・会社法千問の道標』商事法務/2010/277頁、江頭憲治郎『会社法コンメンタール1―総則・設立⑴』商事法務/2022/31頁など)
減資の重要論点
減資の決議機関
| 原則 | 株主総会の特別決議(会309Ⅱ⑨) |
| 例外① |
定時株主総会で減資を決議する場合で、かつ、資本金の減少額の全額を欠損填補に充当する場合
→株主総会の普通決議(会309Ⅱ⑨かっこ書き) |
| 例外② |
株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないとき →取締役決定(取締役会設置会社では、取締役会決議)(会447Ⅲ)。 |
「欠損填補のための減資」の議題・議案
議題・議案としては次のとおりになります(会社法447・452、会社計算規則)。
「欠損填補とは何か?」については、当メディアの「株式会社の計算(はじめに)」をご参照ください。
第1号議案 資本金の額の減少の件
※会社法447
第2号議案 剰余金処分の件(資本金の額の減少の効力発生を条件とする)
※会社法452、会社計算規則153 |
債権者保護手続を要さない準備金の額の減少の要件
会社計算規則151
減資の公告
現在の資本金額は書かないこと。∵急な増資やストックオプション行使に対応するため。
司法書士報酬・費用
※こちらに記載のない登記につきましても、全ての登記に対応可能です。
記載のない場合、お問い合わせをお願いいたします。
※手数料には、基本的な議事録などの作成報酬を含みます。
※顧問契約を締結いただいている場合、割引きがございます。
| 業務の種類 | 司法書士の手数料 | 実費 | |
|
自己株式の消却 |
|||
|
44,000円(税込) | 35,000円 | |
| 株式会社の減資(資本減少) | |||
|
176,000円(税込) | 160,000円(決算公告・減資公告み) | |
|
有限会社の減資(資本減少) |
|||
|
165,000円(税込) | 100,000円(減資公告込み) | |
| 株主総会招集通知の作成・発送代行及び報告 | |||
|
33,000円(税込)~ に発送先1名様ごとに1,100円を加算 |
|||
| 株主総会シナリオ・想定問答集作成 | |||
| 55,000円(税込)~ | |||
| 株主総会立会 | |||
| 55,000円(税込)~ | |||
Q&A よくあるお問い合わせ
減資について
- Q.減資すれば、発行済株式数は減りますか?
-
減資しても、発行済株式総数は減りません。減資に加えて、株式数も減らしたい場合は、「株式併合」又は「自己株式の取得・消却」が必要です。
⇒ 自己株式取得の規制(会社法461条)が適用されます。
分配可能額=その他資本剰余金の額+その他利益剰余金の額ー自己株式帳簿価額(会461ほか)
- Q.減資すれば、貸借対照表はどうなりますか?
-
減資しても、資本金が減り、広義の資本剰余金になるだけで、株主資本内部の振替えに過ぎません。
人気の関連ページ
 企業・事業者向けサービス
企業・事業者向けサービス
 トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)
トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)



















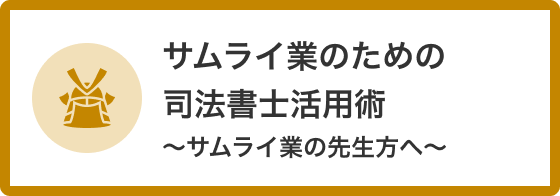
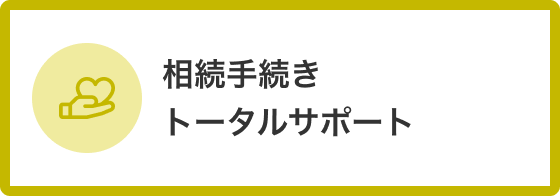
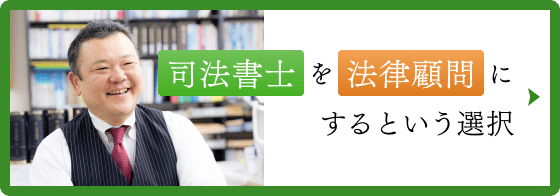

 個人向けサービス
個人向けサービス