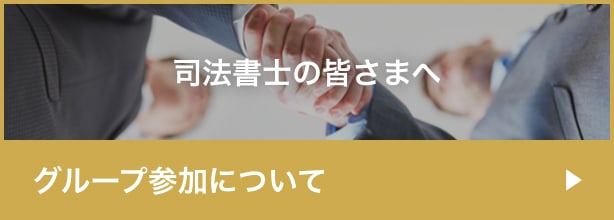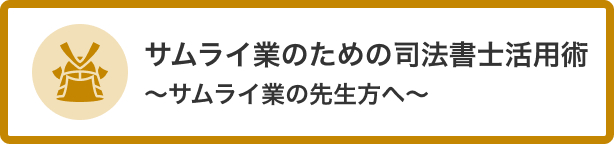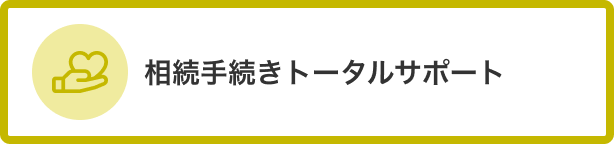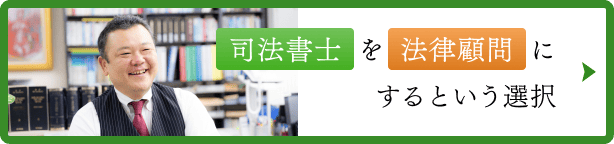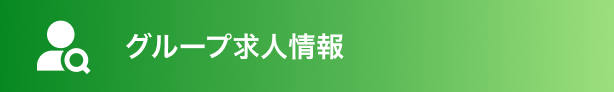- 不動産名義変更・不動産登記TOP
- 終活(成年後見・家族信託・遺言)TOP
- 相続手続き・遺産整理TOP
- ▼知ってお得な相続知識(もくじ)▼
- 相続クイズ50問(間違いだらけのネット情報)
- 自分で相続登記手続をした方に聞きました「相続手続で苦労した理由!ベスト10」
- 相続に関与しようとする民間資格や民間団体にご注意ください。
- 最期の時が近づいたとき(葬儀前に)ご家族が確認・準備するべきこと
- 相続開始直後(葬儀後すぐ)に行なうべき手続一覧
- 相続手続トータルサポート
- 遺言寄付の受け入れトータルサポート
- 相続は早い者勝ちになりました
- 相続登記・遺贈登記の特急申請(グループ会員限定記事)
- 銀行・信託銀行の相続手続は、本当に「質の悪いブランド品」なのか?!士業の相続手続と徹底比較!
- 法定相続情報~ややこしい戸籍を読むのは司法書士が一回で十分です。銀行預金の相続手続前に司法書士にご依頼ください。
- 相続による銀行口座凍結とは?!
- 銀行預金の仮払制度(遺産分割前の預金払戻し制度)
- ▼相続財産の調査(もくじ)▼
- 相続によって引き継ぐ財産・引き継がない財産(相続の対象財産)
- 行方不明の相続預金・相続貯金の探索
- 相続で負債・借金がないかの調査方法
- 被相続人の遺品の中から、相続人や第三者名義の通帳が出てきた場合どうすれば良いのか?(いわゆる名義預金の問題)
- 相続登記や遺言の際に欠かせない不動産の近隣地調査(名寄せ)
- 相続生命保険の調査
- ▼相続人の調査(もくじ)▼
- 相続人は誰か❶基本編(法定相続人・法定相続分)
- 相続人は誰か❷数次相続・再転相続・代襲相続の区別
- 子が親より(妻が夫より)①先に死亡したとき、②同時に死亡したとき、③死亡の先後が分からないときの相続(同時存在の原則、同時死亡の推定)
- 義父母の遺産を受け取る「特別寄与料制度」
- 相続手続のための戸籍収集
- 戸籍の広域交付制度とその盲点
- あなたの戸籍謄本(住民票)が取得されましたとの通知を受けた方へ:本人通知制度
- 旧民法(明治民法・応急措置法)による相続
- ▼相続税申告の要否▼
- ▼遺産分割協議(もくじ)▼
- 遺産分割協議書の基礎知識、作成の流れ
- 遺産分割協議の種類と流れ
- 遺産分割協議成立後、相続人の漏れに気付いた場合の対応方法[グループ会員限定]
- 遺産分割協議の期間制限
- 一次相続の遺産分割協議では、二次相続のことも考えましょう。
- 相続分の譲渡・相続分の放棄
- 平成13年6月までに相続開始又は代襲原因発生の場合は注意「非嫡出子の法定相続分」
- 特別受益証明書(相続分ないことの証明書)による相続登記が流行した理由、消滅した理由から、特別受益証明書の可能性を探る
- 配偶者居住権(2020.4.1以降開始相続)
- 配偶者居住権の法的性質
- 配偶者短期居住権(2020.4.1以降開始相続)
- ▼不動産の相続手続(もくじ)▼
- 不動産の相続手続(相続登記)
- 相続登記後、売却する不動産は誰名義で相続登記したら良いですか?!
- 相続不動産売却サポート
- 何代も前の相続で、途中の相続登記を省略できる場合~数次相続で中間省略登記が認められる条件
- 相続登記に上申書が必要な場合(戸籍不足の相続登記)
- 進まない相続登記(協力しない相続人がいる場合、相続人が何十人もいる場合)の対応【調停や判決による相続登記】
- 長期相続登記未了の通知を受けた方へ/法定相続人情報
- 相続登記義務化:令和6(2024)年4月1日施行
- 相続登記義務を免れるための「相続人申告登記」の意味と申請手続
- 所有者不明土地問題を解消するための法改正と施行時期【一覧】
- 相続した土地を国に引き取って貰う制度『相続土地国庫帰属法』令和5(2023)年4月27日施行
- ▼不動産以外の相続手続(もくじ)▼
- 銀行預金・郵便貯金の相続手続
- 上場株式・非上場株式(株券)の相続手続
- 生命保険の相続手続・税金・遺言執行
- ゴルフ会員権の相続手続
- デジタル遺産の相続手続
- 未支給年金の相続手続
- 自動車の相続手続
- ▼借金貸付金の相続手続(もくじ)▼
- 他人への貸付金(借主)に相続が発生したときの債権者の対応
- 他人への貸付金(貸主)の相続手続
- 借金の相続手続
- NHK未払い受信料の相続手続
- 相続承認・放棄の期間伸長の申立
- 相続放棄(申述)の意味と申立手続
- 相続放棄(申述)できなくなる法定単純承認とは?
- 法定単純承認となることなく、遺品を処分することは可能か?!
- 相続放棄(申述)をしても免れないことがある?!固定資産税・都市計画税のハナシ
- 相続放棄(申述)と数次相続・代襲相続
- 遺贈の放棄|遺言で受けた贈与(遺贈)を放棄する方法は、遺言の書き方によって異なります。
- 限定承認の意味と方法
- ▼遺言があるときの相続(もくじ)▼
- 遺言書を探す方法(公正証書遺言、法務局保管自筆証書遺言の探索)
- 遺言検認申立
- 遺言執行者選任申立
- 遺言解釈・遺言執行
- 遺言解釈(受遺者や受益相続人が遺言者よりも①先に死亡したとき、②同時に死亡したとき)
- 遺言解釈(負担付遺贈か条件付遺贈か)
- 遺言解釈(負担付遺贈を受遺者が放棄した場合)
- 遺言解釈(負担付遺贈の受遺者が負担を履行しないとき)
- 遺言執行(執行対象に動産がある場合)
- 遺言執行(執行対象に動産がある場合)[グループ会員限定記事]
- ▼相続に関する他の手続(もくじ)▼
- 外国(海外)在住日本人の相続手続・相続放棄手続とその必要書類(在留証明・署名証明・法定相続情報・日本公証役場)
- 日本在住外国人の相続手続(各国の相続法)
- 特別代理人選任申立(未成年者がいる場合の遺産分割協議)
- 不在者財産管理人選任申立
- 失踪宣告申立
- (民法952条の)相続財産清算人選任申立
- 相続財産法人への登記名義人氏名変更登記
- 特別縁故者からの相続財産の分与請求
- 他の共有者が死亡したとき、どうすれば良いのか?!~共有者の相続人への共有物分割請求~
- 相続・遺産分割のトラブル解決
- 契約書作成・精査
- 外国人の帰化

国際化が進み、日本に暮らし、日本に財産を遺す外国人の方が増えました。
それに伴い、日本在住外国人のご相続の手続きのご依頼も多いです。
この記事では、被相続人が外国籍のまま亡くなられた場合の相続手続きについて解説しています。
| もくじ | |
|
〔凡例〕この記事では、次のように略記します。
- 通則法36:法の適用に関する通則法第36条
どの国の法律で相続手続すれば良いか
この記事の対象となる相続
まず、この記事の対象となる方をハッキリさせたいと思います。
- 被相続人(亡くなった方)のみが日本に帰化し、相続人は外国籍のままのケース
- 相続人(ご家族)のみが日本に帰化し、被相続人は外国籍のままのケース
様々なケースがあるからです。
| 被相続人の国籍 | |||
| 外国 | 日本 | ||
|
相 続 人 の 国 籍 |
日 本 |
外国人を日本人が相続する相続。 ☛この記事の対象です。 |
日本人を日本人が相続する通常の相続。 ☛この記事の対象ではありません。 |
|
外 国 |
外国人を外国人が相続する相続。 ☛この記事の対象です。 |
日本人を外国人が相続する相続。 ☛この記事の対象ではありません。 ☛記事「外国人住民票と外国人登録原票記載事項証明書」をご参照ください。 |
|
原則
日本にいらっしゃる外国人について、どの国の法律で相続手続すれば良いかは「法の適用に関する通則法」が定めています。
「法の適用に関する通則法」は、以前は「法例」という名前の法律でした。「法例」は、平成18年改正されて「法の適用に関する通則法」になりました(平成19年1月1日施行)。
さて、法の適用に関する通則法36条を見てみましょう。
| 法の適用に関する通則法第36条(相続) | |
| 相続は、被相続人の本国法による(法の適用に関する通則法36)。 | |
本国法とは、被相続人が国籍を置いている国の法律のことです。
つまり、私たち日本人からすれば、本国法とは外国法のことです。
例外(反致)
国際相続について、もう一つ重要な条文が「反致(はんち)」です。
| 法の適用に関する通則法第41条(反致) | |
| 当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第25条(第26条第1項及び第27条において準用する場合を含む。)又は第32条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。 | |
|
ただし書きで引用されている条文は、それぞれ次の内容を規定しています。
|
|
通則法36条で「本国法による」と定めていますので、本国法を調べることになります。
ところが、本国法を調べた結果、本国法でも「日本法による(居住地の法律による)」と規定されていた場合、どの国の法律を適用すれば良いか不明になります。
そんなときに「日本法を適用する」との取扱いを定めているのが「反致」です。
| 通則法の規定 | 本国法の規定 | 反致(通則法の規定) | ||
|
被相続人の本国法による (通則法36) |
☛ | 「本国法による」との規定なら、本国法で手続する。 | ||
| 「日本法による」との規定なら、どの国の法律で手続するか不明になる。 | ☛ | 日本法による(通則法41) |
相続統一主義と相続分割主義
「どの国の相続法を適用するか」については、次のように分類できます。
本国法を調べるときに、ご参照ください。
| 相続統一主義 | 相続分割主義 | |||
| 内容 |
動産と不動産を区別しない。 下のとおり更に分かれます。 |
動産と不動産を区別し、適用される国を決める。 | ||
|
本国法主義 |
住所地主義 |
▼ | ||
| 内容 | 被相続人の国籍で適用する法律を決める。 | 被相続人の最後の住所地で適用する法律を決める。 | ||
| 代表的な採用国 |
|
|
|
|
相続手続の各国の特徴
相続手続きは、本国法によって全く手続きが異なります。
分類すると、おおむね次のとおりです。
| 包括承継主義 | 管理清算主義 | |
| 内容 | 被相続人の死亡によって、相続人が積極財産も消極財産も全て包括的に承継する制度。 | 遺産は、一旦遺産財団に帰属し、裁判所選任の遺産財団管理人による管理清算を行ったのち、残余の積極財産についてのみ相続人への分配・移転を行う。 |
| 代表的な国 |
|
|
| 戸籍がある国 | 戸籍がない国 | |
| 代表的な国 |
|
|
| 結果、生まれた習慣 |
戸籍があるので、相続人が誰かを調査・確定・(第三者へ)証明できる。 ▼
|
戸籍がないので、相続人が誰かを調査・確定・(第三者へ)証明できない。 ▼
|
相続手続を始める前提条件
本国(領事館)に死亡届を提出していないと、相続手続きを開始できません。
司法書士に相続手続きをご依頼いただく前に、本国の領事館に死亡届をご提出ください。
(日本の市役所に死亡届を提出していても、本国にも提出が必要ですので、ご注意ください。)
日本在住外国人の相続手続(被相続人の国籍ごと)
まず、被相続人の本国の国際私法、通則法を調べます。
次に、被相続人の本国法が適用される場合には、本国の民法を調べます。
各国の通則法、各国の民法、各国の相続手続の特徴については、以下のとおりです。
中華民国(台湾)
中華民国(台湾)の渉外民事法律適用法
次のとおり、基本的に中華民国(台湾)の民法が適用されます。
|
台湾・渉外民事法律適用法第58条(相続) |
|
| 相続は、被相続人の死亡の当時の本国法による。ただし、中華民国の法律によれば中華民国国民が相続人となるべきとき、その者は、中華民国に在る遺産につき、これを相続することができる。 | |
|
台湾・渉外民事法律適用法第60条(遺言の準拠法) |
|
|
|
|
台湾・渉外民事法律適用法第61条(遺言の作成及び撤回の方式の準拠法) |
|
|
遺言及びその撤回の方式は、前条によって定められた適用すべき法律のほか、次に掲げるいずれかの法律により、これを行うこともできる。 一 遺言の作成地法 二 遺言者の死亡の当時の住所地法 三 遺言が不動産に関するときは、当該不動産の所在地法 |
|
中華民国(台湾)の民法
| 第1順位 |
直系血族卑属(台湾民法1138) |
配偶者は常に相続人 (台湾民法1144) |
| 第2順位 | 父母(台湾民法1138) | |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(台湾民法1138) | |
| 第4順位 | 祖父母(台湾民法1138) |
中華民国(台湾)の相続手続の特徴
法定相続人の範囲、法定相続分が日本民法とは異なりますので、注意が必要です。
例えば、台湾民法では、法定相続分は同順位の相続人間では等分です(台湾民法1041)。
大韓民国(韓国)
大韓民国(韓国)の国際私法
次のとおり、日本民法も韓国民法も適用される余地があります。
| 韓国・国際私法第49条(相続) | |
|
|
大韓民国(韓国)の民法
韓国民法が適用される場合、韓国民法は日本民法と微妙に異なるため、注意を要します。
| 第1順位 |
被相続人の直系卑属 (韓国民法1001) |
配偶者は常に相続人 (韓国民法1003Ⅰ) |
| 第2順位 |
被相続人の直系尊属 (韓国民法1001) |
|
| 第3順位 |
被相続人の兄弟姉妹 (配偶者がいないときのみ相続人となる。) (韓国民法1001、同1003Ⅰ) |
|
| 第4順位 |
被相続人の4親等内の傍系血族 (配偶者がいないときのみ相続人となる。) (韓国民法1001、同1003Ⅰ) |
大韓民国(韓国)の相続手続の特徴
韓国の戸籍制度は、2007(平成19)年12月31日付で廃止されました。
それに代わるものとして、2008(平成20)年1月1日付で「家族関係登録簿」が始まりました(韓国・家族関係の登録等に関する法律)。
| 証明書の種類 | 記載事項 | |
| 共通して記載される事項 | 個別に記載される事項 | |
| 家族関係証明書 |
|
|
| 基本証明書 |
|
|
| 婚姻関係証明書 |
|
|
| 入養関係証明書 |
|
|
|
親養子入養関係証明書 【4】 |
|
|
相続手続では、下表記載の書類が必要になります。
もっとも在日本大韓民国民団(「民団(みんだん)」で通じます。)に依頼すれば、①どのような書類が必要なのか教えてくださいますし、②取得の代行も、③日本語への翻訳も、適切に行ってくれます。
|
相続開始時 (被相続人が亡くなった日) |
被相続人に関する必要書類 |
| 2007(平成19)年12月31日以前 | 出生からお亡くなりになるまでの(韓国の)除籍等 |
| 2008(平成20)年1月1日以降 | (韓国の)除籍+上記5種類の証明書 |
【1】登録基準地:従来の本籍地にあたるもので、上記証明書を取得する際に必要になるものです。
【2】本:「本」は通常「本貫」と呼ばれ、「姓」と不可分の関係にある父系血統の標識です 。具体的には、同一の父系氏族集団の発祥地や祖先の発祥地名を意味します。韓国では「金」「李」「朴」といった同姓の人が多いため、「姓」と「本貫」を組み合わせることによって、祖先の異なる血族を区別しています。例えば、同じ「金」姓でも、本貫が「金海」か「慶州」かによって、祖先の父系血統が異なります(高翔龍 著『韓国法(第3版)』信山社/2016年/252頁、佐野誠・宮川真史/著『改訂 外国人のための国際結婚手続マニュアル』日本加除出版/2017年/50頁参照)。
【3-1】入養:養子縁組のこと。
【3-2】罷養:養子離縁のこと。
【4】親養子入養:実親との親子関係を断絶させる養子縁組の制度で、日本では「特別養子縁組」に相当します。
中華人民共和国(中国)
中華人民共和国(中国)の渉外民事関係法律適用法
被相続人が日本でお亡くなりになったときは、基本的に日本民法が適用されます(中国・渉外民事関係法律適用法31)。
その他参照すべき規定を抜粋して掲載します。
| 中国・渉外民事関係法律適用法第31条 | |
| 法定相続については、被相続人の死亡時の常居所地法を適用する。ただし、不動産の法定相続には不動産所在地法を適用する。 | |
| 中国・渉外民事関係法律適用法第32条 | |
| 遺言方式が、遺言者の遺言作成時または死亡時の常居所地法・国籍国法または遺言行為地法に適合するときは、その遺言はいずれも成立する。 | |
| 中国・渉外民事関係法律適用法第33条 | |
| 遺言の効力については、遺言者の遺言作成時または死亡時の常居所地法または国籍国法を適用する。 | |
| 中国・渉外民事関係法律適用法第34条 | |
| 遺産管理等の事項については、遺産の所在地法を適用する。 | |
| 中国・渉外民事関係法律適用法第35条 | |
| 相続人不存在の遺産の帰属については、被相続人死亡時の遺産の所在地法を適用する。 | |
中華人民共和国(中国)の民法
被相続人が日本でお亡くなりになったときは、日本民法が適用されます(中国・渉外民事関係法律適用法31)ので、基本的には確認する必要がありません。
中華人民共和国(中国)の相続手続の特徴
被相続人の戸籍等を中国から取得する必要がありますが、日中関係の悪化にともない、容易に出してくれなくなりました。
オーストラリア🐨
オーストラリア(豪国)相続の特徴
- 連邦制国家:州によって、適用される法律が異なります。すなわち、オーストラリアは連邦制国家であり、連邦と各州に独自の法制度があります。家族法の分野では、婚姻と離婚について、連邦が立法権を有しています(The Australian Constitution=オーストラリア憲法51条21項22項)が、「相続法」については各州に委ねられています。
- コモンロー:判例法の国ですが、現在では多くの成文法も制定されています。
- 相続分割主義:不動産については不動産の所在地法が適用され、動産については被相続人の死亡時のドミサイルの法が適用されます。
- 管理清算主義:相続が開始すると裁判所が清算人を選任し、遺産を整理したうえ、相続人に引き渡します。
参考書籍
本記事の執筆のために、以下の書籍等を参考にしました。
- 日本加除出版法令編纂室(編)『戸籍実務六法』日本加除出版
- 民事渉外手続研究会(編)『事例式・民事渉外の実務』新日本法規
- 篠崎哲夫・竹澤雅二郎・野崎昌利(編著)、木村三男(監修)『全訂新版 渉外戸籍のための各国法律と要件』日本加除出版
- リサ・ヤング(著)小川富之(訳・監修 )『オーストラリア家族法 戸籍時報アーカイブ』日本加除出版/2024
人気の関連ページ
 企業・事業者向けサービス
企業・事業者向けサービス
 トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)
トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)





















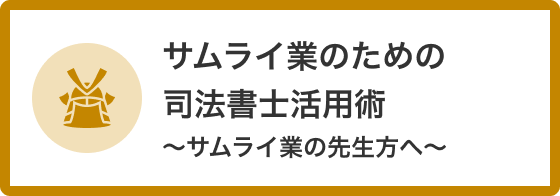
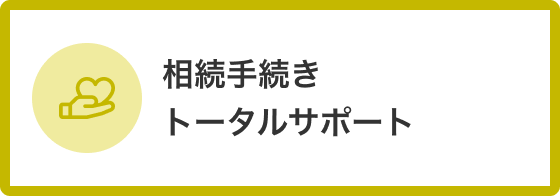
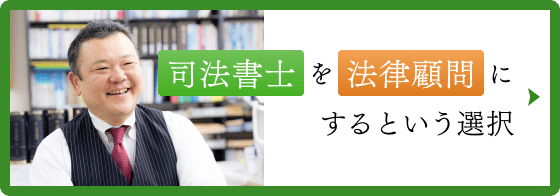

 個人向けサービス
個人向けサービス