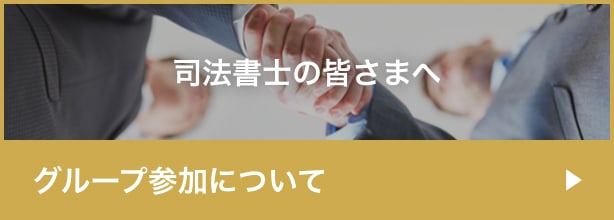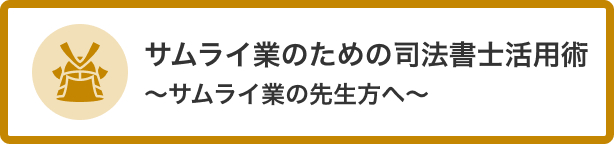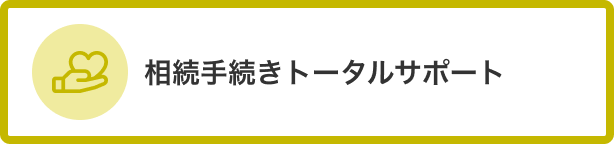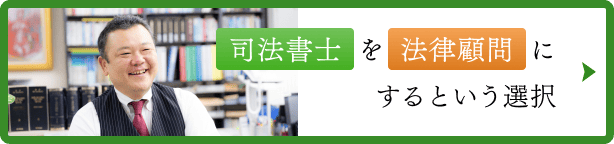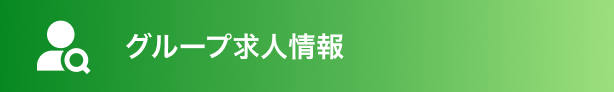- 不動産名義変更・不動産登記TOP
- 終活(成年後見・家族信託・遺言)TOP
- 相続手続き・遺産整理TOP
- ▼知ってお得な相続知識(もくじ)▼
- 相続クイズ50問(間違いだらけのネット情報)
- 自分で相続登記手続をした方に聞きました「相続手続で苦労した理由!ベスト10」
- 相続に関与しようとする民間資格や民間団体にご注意ください。
- 最期の時が近づいたとき(葬儀前に)ご家族が確認・準備するべきこと
- 相続開始直後(葬儀後すぐ)に行なうべき手続一覧
- 相続手続トータルサポート
- 遺言寄付の受け入れトータルサポート
- 相続は早い者勝ちになりました
- 相続登記・遺贈登記の特急申請(グループ会員限定記事)
- 銀行・信託銀行の相続手続は、本当に「質の悪いブランド品」なのか?!士業の相続手続と徹底比較!
- 法定相続情報~ややこしい戸籍を読むのは司法書士が一回で十分です。銀行預金の相続手続前に司法書士にご依頼ください。
- 相続による銀行口座凍結とは?!
- 銀行預金の仮払制度(遺産分割前の預金払戻し制度)
- ▼相続財産の調査(もくじ)▼
- 相続によって引き継ぐ財産・引き継がない財産(相続の対象財産)
- 行方不明の相続預金・相続貯金の探索
- 相続で負債・借金がないかの調査方法
- 被相続人の遺品の中から、相続人や第三者名義の通帳が出てきた場合どうすれば良いのか?(いわゆる名義預金の問題)
- 相続登記や遺言の際に欠かせない不動産の近隣地調査(名寄せ)
- 相続生命保険の調査
- ▼相続人の調査(もくじ)▼
- 相続人は誰か❶基本編(法定相続人・法定相続分)
- 相続人は誰か❷数次相続・再転相続・代襲相続の区別
- 子が親より(妻が夫より)①先に死亡したとき、②同時に死亡したとき、③死亡の先後が分からないときの相続(同時存在の原則、同時死亡の推定)
- 義父母の遺産を受け取る「特別寄与料制度」
- 相続手続のための戸籍収集
- 戸籍の広域交付制度とその盲点
- あなたの戸籍謄本(住民票)が取得されましたとの通知を受けた方へ:本人通知制度
- 旧民法(明治民法・応急措置法)による相続
- ▼相続税申告の要否▼
- ▼遺産分割協議(もくじ)▼
- 遺産分割協議書の基礎知識、作成の流れ
- 遺産分割協議の種類と流れ
- 遺産分割協議の期間制限
- 一次相続の遺産分割協議では、二次相続のことも考えましょう。
- 相続分の譲渡・相続分の放棄
- 平成13年6月までに相続開始又は代襲原因発生の場合は注意「非嫡出子の法定相続分」
- 特別受益証明書(相続分ないことの証明書)による相続登記が流行した理由、消滅した理由から、特別受益証明書の可能性を探る
- 配偶者居住権(2020.4.1以降開始相続)
- 配偶者居住権の法的性質
- 配偶者短期居住権(2020.4.1以降開始相続)
- ▼不動産の相続手続(もくじ)▼
- 不動産の相続手続(相続登記)
- 相続登記後、売却する不動産は誰名義で相続登記したら良いですか?!
- 相続不動産売却サポート
- 何代も前の相続で、途中の相続登記を省略できる場合~数次相続で中間省略登記が認められる条件
- 相続登記に上申書が必要な場合(戸籍不足の相続登記)
- 進まない相続登記(協力しない相続人がいる場合、相続人が何十人もいる場合)の対応【調停や判決による相続登記】
- 長期相続登記未了の通知を受けた方へ/法定相続人情報
- 相続登記義務化:令和6(2024)年4月1日施行
- 相続登記義務を免れるための「相続人申告登記」の意味と申請手続
- 所有者不明土地問題を解消するための法改正と施行時期【一覧】
- 相続した土地を国に引き取って貰う制度『相続土地国庫帰属法』令和5(2023)年4月27日施行
- ▼不動産以外の相続手続(もくじ)▼
- 銀行預金・郵便貯金の相続手続
- 上場株式・非上場株式(株券)の相続手続
- 生命保険の相続手続・税金・遺言執行
- ゴルフ会員権の相続手続
- デジタル遺産の相続手続
- 未支給年金の相続手続
- 自動車の相続手続
- ▼借金貸付金の相続手続(もくじ)▼
- 他人への貸付金(借主)に相続が発生したときの債権者の対応
- 他人への貸付金(貸主)の相続手続
- 借金の相続手続
- NHK未払い受信料の相続手続
- 相続承認・放棄の期間伸長の申立
- 相続放棄(申述)の意味と申立手続
- 相続放棄(申述)できなくなる法定単純承認とは?
- 法定単純承認となることなく、遺品を処分することは可能か?!
- 相続放棄(申述)をしても免れないことがある?!固定資産税・都市計画税のハナシ
- 相続放棄(申述)と数次相続・代襲相続
- 遺贈の放棄|遺言で受けた贈与(遺贈)を放棄する方法は、遺言の書き方によって異なります。
- 限定承認の意味と方法
- ▼遺言があるときの相続(もくじ)▼
- 遺言書を探す方法(公正証書遺言、法務局保管自筆証書遺言の探索)
- 遺言検認申立
- 遺言執行者選任申立
- 遺言解釈・遺言執行
- 遺言解釈(受遺者や受益相続人が遺言者よりも①先に死亡したとき、②同時に死亡したとき)
- 遺言解釈(負担付遺贈か条件付遺贈か)
- 遺言解釈(負担付遺贈を受遺者が放棄した場合)
- 遺言解釈(負担付遺贈の受遺者が負担を履行しないとき)
- 遺言執行(執行対象に動産がある場合)
- 遺言執行(執行対象に動産がある場合)[グループ会員限定記事]
- ▼相続に関する他の手続(もくじ)▼
- 外国(海外)在住日本人の相続手続・相続放棄手続とその必要書類(在留証明・署名証明・法定相続情報・日本公証役場)
- 日本在住外国人の相続手続(各国の相続法)
- 特別代理人選任申立(未成年者がいる場合の遺産分割協議)
- 不在者財産管理人選任申立
- 失踪宣告申立
- (民法952条の)相続財産清算人選任申立
- 相続財産法人への登記名義人氏名変更登記
- 特別縁故者からの相続財産の分与請求
- 他の共有者が死亡したとき、どうすれば良いのか?!~共有者の相続人への共有物分割請求~
- 相続・遺産分割のトラブル解決
- 契約書作成・精査
- 外国人の帰化

遺言執行では、悩むことも多いです。特に「動産」が対象となるときには、まとめて書かれている書籍も少なく苦慮します。
この記事では、遺言執行のうち「動産」がその対象となるときの➊遺言執行の注意点と➋遺言執行の流れについて、解説しています。
| もくじ | |
|
〔凡例〕この記事では、次の法令が出てきます。法令名が長いときは、次のとおり略記します。
- 民:民法(明治二十九年法律第八十九号)
動産に対する遺言執行の注意点
- 被相続人名義の動産は、財産的な価値の有無を問わず、すべて相続財産です。
- 動産は散逸しやすいため、遺言執行者への就任後、早めの保全措置が必要です。
- 遺言執行者は、善管注意義務を負います(民1012Ⅲ→民644)。
- 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければなりません。また、相続人の請求があるときは、相続人の立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければなりません(民1011)。
- 「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有」しています(民1012Ⅰ)。「必要な一切の行為」とは、「そのために(相続財産の管理その他遺言の執行のために)相当かつ適切と認める行為」(最判昭44年6月26日判時563・38)を意味します。具体的にどのような行為が「相当かつ適切と認める行為」かは、遺言内容から遺言執行者の責任で判断します。遺言者(被相続人)の真意に沿った行為であるか否かで判断することになります。
動産に対する遺言執行の流れ
細かく分類すると、次のような流れになります。
| 事前準備 |
|
| 当日 |
|
| 後日 |
|
以下、一つずつ細かく見ていきましょう。
<事前準備>
1■遺言書を確認する。
遺言書をしっかりと確認し、下記内容をチェックします。
- 遺言対象に「動産」が含まれているか?遺言書に具体的な動産が明示されている場合はもちろん、「その他一切の財産」とある場合にも、動産【1】【2】は遺言の対象となります。
- 遺言執行対象に「動産」が含まれているか(遺言執行者の権限が動産にも及んでいるか)?銀行等が関与して作成された公正証書遺言の場合において、銀行等を遺言執行者として指定しておきながら、動産を遺言執行の対象外としている遺言書も見受けられる。
- 動産は、遺産分割協議を経ずに、各相続人(受遺者)に帰属するか?遺言では、各動産の取得割合だけを定めている遺言書も見受けられる。このような場合、具体的にどの動産を取得するかについては、相続人による協議を要することとなる。
- 動産は、動産のまま相続人に渡せば良いのか?遺言執行者が換価して現金で渡すことを要するのか?
- 貸金庫の契約がある場合、遺言書では遺言執行者に対して「貸金庫の開扉、内容物の受領の権限」が付与されているか?付与されている場合、貸金庫内の動産も遺言執行の対象となります。
【1】「動産」とは、不動産以外の有体物のことをいいます(民85、民86)。貴金属、宝飾品、骨董品、書画、刀剣、家財道具、什器備品、ペット(動物)、自動車、船舶なども全て動産です。
【2】不動産の他の財産について「身のまはりの品」「現金」「動産」の語が使用され、金融資産を有しているにもかかわらず「債券」「有価証券」「預金」などの語が使用されていない遺言書の解釈が争われた事例で、「動産」は、不動産以外の有体物のみならず、金融機関に預け入れた有価証券等や預貯金も示すと解釈された裁判例(東京地判平成24年1月20日(平20(ワ)32286号))もありますので、遺言は後日、疑義が生じないよう、じっくりと確認する必要があります。

2■遺産(動産)占有者に対して、通知する。
遺言執行者の就任通知(民1007)とともに、包括的に処分禁止や引渡しを求めることが通常です。
- 動産を相続人が占有しているとき:遺言執行者は、遺言執行上必要があるときは、動産を占有している第三者に対して、その引渡しを求めることができます(民1013)。
- 動産を非相続人が占有しているとき:遺言執行者は、遺言執行上必要があるときは、動産を占有している第三者に対して、その引渡しを求めることができます(大審院判昭和15年12月20日大民集19巻2283頁、WestlawJapan)。
遺言執行者の就任時点で判明している銀行には、預金払戻し禁止とともに、貸金庫の開扉禁止も通知します。銀行へは、通常は内容証明郵便で通知します。

3■書類で確認する。
動産に関する情報が記載された書類がある場合には、まず書類を確認します。
記載されている可能性がある書類には、次のようなものがあります。
- 遺言書
- 相続税申告書(遺言者を被相続人とするもの、遺言者の配偶者を被相続人とするもの)
- 遺言者の通帳(貸金庫の利用料が引き落とされている場合)
- 遺言者の住所の変遷(転居前の建物が遺言者名義のままの場合には、旧住所の建物内にも動産が残っている可能性があります。)

4■聴取を開始する。
協力的な相続人から以下のような情報を事前に聴取します。
- 重要な動産の種類、数(遺言者が遺言書作成後に高価なものを購入していないか?)
- 重要な動産が保管されている場所
- 保管されている場所の「見取図」
- 重要な動産がどこにあるか
- 他の相続人から「遺産ではなく、相続人の固有財産である」旨の主張がなされる可能性
- 遺言執行者が動産を保管した後、遺産分割を要する場合には、取得を希望する動産

5■現地で記入用にあらかじめ見取図や相続財産目録を作成する。
単なる白紙を持参しても、聴取漏れなどが発生します。そこで、現地では記入だけすれば良いように白紙の「(建物)見取図」や「相続財産目録」をあらかじめ作成して、準備しておきます。

6■現地調査の日程調整をする。
遺言執行者から相続人全員に対して、現地立会の日程調整を依頼する文書を送ります。
遺言執行者の都合の良い日を複数挙げて、都合の良い日時に○印をつけてもらうようにすると良いでしょう。
<相続人の立会か、公証人による作成か>
遺言執行者は、相続人の請求があるときは、相続人の立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければなりません(民1011)。
二つの方法、すなわち①相続人の立会のもと遺言執行者が相続財産目録を作成する方法、または②公証人が相続財産目録を作成する方法の選択権が、相続人又は遺言執行者いずれにあるかについては、「相続人が立会を求めた場合には,必ず相続人立会のもとに財産目録を調製しなければならず,また,相続人が公証人による調製を請求した場合には,公証人をして調製させなければならない(本条2項)。公証人が財産目録を調製する場合には,相続人を立ち会わせ(明32・7・10民刑局長回答〔法曹記事93号40〕)(ただし,その署名・押印を要しない),目録の1通を公証人役場に保存し,他の1通を遺言執行者に交付する取扱いになっている。目録には、立ち会った相続人、遺言執行者の署名押印は必要ありません(明32・3・2民刑局長回答〔法曹記事89号67〕)。(『新版 注釈民法(28) 相続(3) 補訂版』329頁)」。

7■現地調査を準備する。
次のようなものを準備します。
- 専門業者(搬出業者、骨董品屋など)の手配。大きいトラックで乗り付けると警戒されて入れてもらえない可能性がありますので、トラックは少し離れた場所で待機してもらいましょう。
- (専門業者を手配した場合)日当、作業料
- (相続人の求めがあるときは)公証人への相続財産目録作成の手配(通常、目録作成後に請求されると思いますが、事前に公証人に確認しておきましょう。)
- 遺言書(写し)
- ICレコーダー(充電の確認も)
- ビデオカメラ、カメラ(充電の確認も)
- 建物の見取図(現地で記入用)
- 相続財産目録(現地で記入用)
- 動産引渡証:①遺言執行者が相続人にそのまま保管してもらうとき、②遺言執行者が現場で相続人に動産を交付するとき→遺言執行者が相続人に受取のサインをもらう必要があります。
- 動産受領書:遺言執行者が相続人から動産を預かったときに→遺言執行者が相続人に交付する。遺言執行者は動産受領書の控えを保管する。
- 筆記道具
- クリップボード(現場で文字を書くため)
- 貴重品用の白手袋
- スリッパ
- (真夏は)着替え

<当日>
8■現地調査を開始する。
遺言者の遺品である「鞄の中身」も確認する必要があります。
協力的ではない相続人に対しても、質問し聴取する必要があります。
トラブルになりそうなときは、公証人に「事実実験公正証書」の作成を依頼することも検討します。

9■(現地調査を認めない相続人に対する対応をする。)
被相続人の最後の住所地が、相続人の住所地でもある場合には、被相続人の所有する動産が相続人の住居内に存在している可能性が高いです。しかしながら、遺言執行者といえども、当該相続人の承諾なく住居内に入ることはできません。
遺言執行者は、そのために相当かつ適切と認める行為をすることができます(最判昭和44年6月26日民集23巻7号1175頁)ので、遺言の執行において紛争が生じた場合には、裁判上、裁判外を問わず、必要な行為をすることができます。なお、これらの行為を行うために、裁判所の許可は不要と解されています(『遺言執行の手引』134頁など)。

10■個々の動産を「特定」し、相続財産目録を作成する。
<動産の特定について>
遺産の中に、同種の動産が複数ある場合には、個々の動産をしっかり特定する必要があります。個別の動産について、遺産分割協議を行い、承継するためには、動産が特定されている必要があるからです(民400.401参照)。
「不特定物の場合は、特定して初めて特定物として引渡の対象となるから、遺言執行者は特定をする作業を要する。 そのうえでの受益相続人に対する引渡となる。 この特定作業では、例えば、金の延棒で品質や重量が異なるような場合は、その品物を鑑定評価して、その価値を把握し、後日、紛争にならないように工夫するところが出てくるものと思われる。 不特定物を特定した場合は、そのことを相続人全員に対して通知をしておくべきである。 不特定物の場合は、上記のように不特定物の中から受益相続人のために特定をし、その引渡をすることが遺言執行者としての行うべき任務となる(後掲『遺言執行の手引〔第2版〕』72頁)。」
「特定の方法としては、①1個1個の動産をその形状等により個別に特定する方法と、②複数の動産類を包括して保管場所により特定する方法があります。個性が乏しい多数の動産を特定する場合は、②の方法によることを検討すべきです。(例えば「母屋桐箪笥内の着物類」等)ただし。保管場所内で対象物が変動しないように留意する必要があります。(山本真太朗/ブログ『遺産分割で動産の管理をするにあたってどのような点に注意すべきでしょうか。』2021.12.03)」
「『遺贈の目的物として宝石2点と記載されているが、宝石は全部で5点あった』というケースで5点の宝石は種類・大きさがバラバラである・・・場合、5点のうちどれを目的物すればよいのだろうか。この場合は、遺言者がこのような遺言書を作成した動機、遺言者と宝石との関係(入手経過など)、遺言者と受遺者の関係等を関係者に聴取し、また、宝石そのものに関する情報(誕生石など)も加味して、遺言者の真意を推定し、目的物を特定することになる。どうやっても特定できない場合は、不特定物の処理に準じて中等の品質を有する物(民401Ⅰ)を給付することが許されるべきであろう。『改訂 実務解説 遺言執行』139頁」
「その後、受遺者に対して、動画を引き取るよう通知することになります。なお、この際に、今後のトラブルを避ける等の意味で、特定の経緯等を併せて通知することも有用でしょう『新版 遺言執行の法律と実務』172頁」

11■(所在不明な動産がある場合の対応をする。)
遺言書には記載があるものの、所在不明な動産がある場合「現実の執行においては、目的とされた動産の所在が不明な場合も少なくありませんが、善良な管理者の注意義務をもって調査した結果なお所在が不明であればその責任を免れると解されます。(後掲『遺言執行実務マニュアル』141頁)」

12■動産の保管場所、保管方法を決定する。
個々の動産の種類、数量、形状、性質等に応じた適切な保管場所を選択し、必要に応じて搬出保管します。搬出、保管等の費用は、相続財産の負担とされています(民1021)ので、相続人がその固有財産から支払う必要はありませんが、後日揉めないために、相続人に通知をしておくのが無難です。
「大変なのは引渡までの間の動産の管理である。 管理を要するものは、遺言執行者に善管注意義務があるので、管理の期間中はその保管方法等の管理について細心の注意を払う必要がある。 絵画や骨董品等については、場合によっては専門の業者に保管を委託し、金の延棒等については銀行の貸金庫での保管などを考える必要があると思われる(後掲『遺言執行の手引〔第2版〕』72頁)。」
- 家財家具、衣類等は、滅失・毀損のおそれがない限り、それらの動産がもともと保管されていた場所にて保管する方法を選択することが多くあります。その場合、管理する相続人または遺言執行者は、建物について施錠等の防犯対策をとるように留意し、また、日照、雨漏り、湿度、乾燥、虫害等により動産が滅失・毀損しないように十分留意します。
- パソコン等の電子機器については所在場所、種類、機種名、型式、保証書の有無等を確認した上で、付属品、説明書等と一緒に保管します。また、パスワードを設定するなどのセキュリティ措置を講じます。
- 書画骨とう、茶道具、高級ワイン等の温湿度管理を必要とするものは、専用の貸金庫、トランクルーム等の活用を検討します。保証書、鑑定書、箱書き等の付属品も含めて保管します。絵画、古書については、鑑定書、説明書等を確認し、または専門家に依頼して、作家名や作品名を調査します。保管方法についても専門家に相談します。滅失毀損のおそれがない限り、もともと保管されていた場所で保管する方法を選択することが多くあります。
- 株式等の有価証券は、「保管者から証書、証券、株券あるいは配当金通知書などの株式情報が記載された書類、保護預り証、印鑑等の引渡しを受け」ます。
- 借用証は、「保管者から契約書等の引渡しを受け、債務者に就職した旨を通知します。」
- 貴金属、宝石等の高価品は「現物、保証書、鑑定書等の引渡しを受けます。」「保証書や鑑定書が添付されているものは、これら保証書等があってはじめて高い価値を維持し得る場合もあるので、紛失しないよう現物と一緒に保管しておくよう注意が必要である。」
- 自動車は、「遺言執行者は自賠法上の運行供用者責任を負う危険性があるため、可及的速やかに、鍵、車検証、保険証券、ローン契約書等関係書類を保管者から預かり、とりあえず使用できないようにすることが重要である。また、車両の所在、種類、型式等を角煮にし、車両の盗難、破損等防止のため車庫を用意する等の適切な保管方法を直ちに取る必要がある。なお、損害保険(任意保険)の加入の有無、保険期間も確認しておく・・・この点、被相続人の家族らが生活の必需品として使用している場合、直ちに使用を禁止することが難しいと思われるので、損害賠償保険への加入の有無、十分な補償内容であるかを確認した上で、必要性に応じて、使用を許可しつつ、速やかに執行に移る場合もあろう。ただし、任意保険に入っていない場合や保険期間が切れてしまった場合には、使用を許可すべきではない。」「保管者から車検証、ローン契約書等の引渡しを受け、運輸支局または自動車検査登録事務所に申請して登録事項等証明書を取得します。また、自動車の存在と保管場所を確認します。」
- 不特定物・金銭(現金)は「不特定物(種類物(民401))が特定遺贈の目的とされた場合、遺言執行者は、相続財産の中から特定し、又は他から調達して受遺者に引き渡します。金銭が遺贈の目的とされた場合、古銭のように貨幣の個性に着目しているような例外的な場合を除き、相続財産の中から受遺者に引き渡します。もし相続財産中の現金が遺言に記載された額に不足する場合、他の財産を処分して調達する必要があるかどうかは、遺言の解釈によります。受遺者への引渡しまでの間金銭を管理する場合には、遺言執行者固有の財産との混同を避けるため、遺言執行のため新たに保管金管理口座を作成し、そこに保管することが適切です。」
- 現金は、法律的には動産ですが、遺言の解釈において、現金が金融資産なのか動産なのかは、遺言書の具体的な記載と、その遺言を作成した人の意思(遺言者の真意)を解釈して決めることになります(前掲・東京地判平成24年1月20日(平成20(ワ)32286)参照。)。
- ペット類も「そのまま現状で世話をしてもらえる人がいるのであれば、飼育環境をできるだけ変えないほうがよいので、その者に世話を委ねたほうがよいが、適当な者がいない場合は、専門業者に委託するのもよいであろう。いずれにしても、ペット類の維持管理は難しいので、速やかに執行に移るべきである」
以上、いずれも後掲、『改訂 実務解説 遺言執行』94頁以下138頁以下、ブログ『遺産分割で動産の管理をするにあたってどのような点に注意すべきでしょうか。』、『遺産相続事件処理マニュアル』201頁、『遺産相続事件処理マニュアル』142頁、
不特定物(種類物(民401))が特定遺贈の目的とされた場合、遺言執行者は、相続財産の中から特定し、又は他から調達して受遺者に引き渡します。金銭が遺贈の目的とされた場合、古銭のように貨幣の個性に着目しているような例外的な場合を除き、相続財産の中から受遺者に引き渡します。もし相続財産中の現金が遺言に記載された額に不足する場合、他の財産を処分して調達する必要があるかどうかは、遺言の解釈によります。受遺者への引渡しまでの間金銭を管理する場合には、遺言執行者固有の財産との混同を避けるため、遺言執行のため新たに保管金管理口座を作成し、そこに保管することが適切です。

13■動産を搬出する。
共同相続人の一人が被相続人の動産を自宅に保管している状況で、遺言でその動産を別の相続人に遺贈している場合、売却処分が指示されている場合は、適切な執行のために搬出が必要です。
また、現地保管では後日トラブルが生じそうな場合や、高額な動産の場合にも、搬出し、然るべき保管措置を講じます。

14■(動産を引き渡さない者に対して対応する。)
- 動産を相続人が占有しているとき:遺言執行者は、遺言執行上必要があるときは、動産を占有している第三者に対して、その引渡しを求めることができます(民1013)。
- 動産を非相続人が占有しているとき:遺言執行者は、遺言執行上必要があるときは、動産を占有している第三者に対して、その引渡しを求めることができます(大審院判昭和15年12月20日大民集19巻2283頁、WestlawJapan)。

<後日>
15■動産を評価する。
「相続財産目録は、相続財産の状態を具体的に明らかにすればよく、遺言執行者には特に個々の財産の価額を調査するまでの義務はありません(この点、相続人らからの請求がある場合には、委任に基づく報告義務として(民1012Ⅲ・645)個々の相続財産の評価額を調査・報告する必要が出てきますが、これは、ここでいう相続財産目録調製の義務の問題ではありません。)。(後掲『遺言書作成・遺言執行実務マニュアル』915頁)」
「財産目録の内容は法定されていないが,遺言執行者の管理に付される相続財産の状態を具体的に明らかにすればよく,特に個々の財産の価額を調査する義務はない(もっとも,相続人の要求がある場合には,報告義務にもとづいて〔1012II・645〕,個々の相続財産の価額を調査する必要があるが,それは本条の財産目録調製義務にもとづくことではない)。また,家財道具などは一括して合計価額の概数をもって表示してもよく(大判昭6・12・14法学1上518は,限定承認のさいの財産目録について「相続動産ヲ表示スルニ評価格金79円也トノミ記載シ其ノ種類品目ノ記載ナキ〔モ〕......其ノ評価額ヨリシテ之ガ範囲ヲ想度シ得」るとしているが,この理はここでも生かされてよい),少額の有価証券なども一括記載して差し支えない。かくして遺言執行者による財産目録は,限定承認に必要とされる財産目録とその内容を異にする(限定承認のための財産目録は,相続債権者の利益を守る趣旨のものであるから,原則として,相続財産を個別的に,しかもその価額を表示して作製しなければならない)。財産目録に記載されることによって裁判上相続財産と推定されることはもちろんないし,遺脱に対する格別の制裁もない。『新版注釈民法(28)』328頁)」
財産的価値のあるものと財産価値のないものを選別するために、財産の種類に応じて、貴金属買取業者、着物買取業者、家具・家電リサイクル業者、書画骨とう業者、画商、古美術商等に、評価額の査定を依頼します。対象となる動産にもよりますが、複数の業者に評価してもらうことが望ましいと考えられます。査定の結果、値段がつかず財産的価値がないことが判明した動産で、かつ遺言または遺贈の対象となっていないものについては、遺産分割、遺言執行の対象とせず、廃棄処分または形見分け行なうことを検討することになります。
(山本 真太朗/ブログ『遺産分割で動産の管理をするにあたってどのような点に注意すべきでしょうか。』2021.12.03)

16■相続人に対して相続財産目録を交付する。
遺留分が認められていない相続人に対しても、遅滞なく被相続人に関する相続財産の目録を作成してこれを交付する必要があります(民1011)。
「できる限り速やかに作成します。形式は自由であり、相続財産の内容を特定し、現在の状態が把握できるような内容であれば足ります。具体的な評価額まで記載する必要はありません。(後掲『遺言書作成・遺言執行実務マニュアル』915頁)」

17■(遺産分割協議を促す。)
遺言書に「個々の動産を特定し、一つ一つについて、誰に承継させるか」まで記載されている場合は、ほとんどありません【1】。
遺言書に「動産は相続人○○と相続人□□に相続させる。取得させる割合は2分の1ずつとし、具体的な分割方法については、相続人○○と相続人□□が話し合いのうえ決めること」と記載されている場合には、遺言執行者は、相続人間で遺産分割協議を行うよう促します。
【1】遺言書に「個々の動産が具体的に特定され、個々の動産一つ一つについて、誰に承継させるか」まで記載されている場合、遺言執行者は、特定された動産を、承継するとされた相続人に引渡しをすれば完了です。

18■(相続人が動産を勝手に第三者に譲渡した場合、対応する。)
遺言執行者がある場合、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができず(民法1013Ⅰ)、違反してした行為は、無効となりますが、善意【1】の第三者には対抗することができません(民法1013Ⅱ)。
この結果、相続人から財産を譲り受けた第三者が「善意」である場合、受遺者と善意の第三者との関係は、二重譲渡のような対抗関係となります。そして、先に動産の引渡し(対抗要件)を受けた方が、その権利取得を主張できることになります(民法899条の2)。
【1】「善意」とは、遺言執行者がおり、その財産の管理処分権が遺言執行者にあることを知らないことを意味し、無過失を要しないとされています。

19■相続人に対抗要件を具備させる。
民法が改正され、法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないこととなりました(民899の2Ⅰ)ので、遺言執行者は、動産を承継した相続人に、対抗要件を備えさせます(民1014Ⅱ)。
<対抗要件を具備する方法>
動産の種類によって異なり、登記、登録がある場合には登記、登録を行います。
- 自動車の場合には、遺言執行者は、陸運局で、相続人名義に自動車の名義変更をします。
- 船舶の場合には、遺言執行者は、法務局で船舶登記の変更を、地方運輸局等で船舶登録の変更をします。
- 登記、登録がない動産の場合には、遺言執行者は、相続人に対して、当該動産を引渡します(民178)。引渡しには、①現実の引渡し、②簡易の引渡、③占有改定、④指図による占有移転がありますが、いずれの方法であっても、対抗要件として認められます。
|
現実の引渡し (民182Ⅰ) |
物理的に目的物の占有を移転する方法。譲渡人が譲受人に現物を手渡す場合など。 |
|
簡易の引渡し (民182Ⅱ) |
譲受人が既に占有している場合、譲渡人の意思表示のみで占有移転とする方法。 |
|
占有改定 (民183) |
譲渡人が目的物を引き続き占有するが、譲受人のために占有する旨の意思表示をする方法。 |
|
指図による占有移転 (民184) |
第三者が目的物を占有している場合に、譲渡人の第三者への指図と、譲受人の承諾で成立する方法。 |

20■(動産を売却換価する。/動産を処分する。)
遺言で動産の売却処分が指示されている場合には、適正な価格で売却します。

21■相続人に報告する。
遺言執行者は、遺言執行完了後、遅滞なく、相続人全員に対して、遺言執行の経過及び結果を報告します(民1012→民645)。

22■遺言執行報酬を請求し、受領する。
委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない(民1018Ⅱ→民648Ⅱ)。
「遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とされています(民1021本文)。遺言の執行に関する費用には、遺言執行者の報酬も含まれますので、報酬は、相続財産から支払われることになります。遺言執行者が相続財産を管理している場合は、普通は、遺言執行者は、報酬等の遺言執行費用を控除してその残額を相続人に引き渡すことになります。(後掲『遺言書作成・遺言執行実務マニュアル』953頁)」
貸金庫内の動産に関する遺言執行の流れ
貸金庫があることが判明した場合には、次のような手続きを進めます。
(貸金庫の開扉は、特殊です。)
就任直後
遺言執行者は、その就任直後に、金融機関に対して、内容証明郵便で①遺言執行者就任通知とともに②相続人による預金解約や貸金庫開扉を禁止する通知を送ります。

貸金庫の開扉の時期
貸金庫が存在していることが明らかであるときには、開扉を急いで行います。別の遺言執行者を指名している遺言書が、貸金庫内に保管されている可能性もあるからです。

銀行との打合せ
相続人から立会を要求されることがありますが、貸金庫室には、物理的に相続人全員が入れないときもあります。
また、銀行によっては、遺言執行者以外の立会を認めない場合もあるようです。
銀行に事前相談する必要があります。

(公証人の予約)
次のような場合には、公証人に「事実実験公正証書」の作成を依頼するのが無難です。
- 相続人から立会を要求されたが、相続人全員の立会は無理などと、銀行に言われた場合
- トラブルが生じそうな場合
遺言執行の参照条文
民法第648条(受任者の報酬)
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。
3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき。
民法第899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
民法第909条(遺産の分割の効力)
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
民法第1007条(遺言執行者の任務の開始)
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
民法第1011条(相続財産の目録の作成)
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
民法第1012条(遺言執行者の権利義務)
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 第644条〔善管注意義務〕、第645条〔報告義務、第646条〔受取物の引渡義務〕〕から第647条〔金銭消費の責任〕まで及び第650条〔受任者による費用等の償還請求等〕の規定は、遺言執行者について準用する。
民法第1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
民法第1014条(特定財産に関する遺言の執行)
前三条〔1011=相続財産の目録の作成、1012=遺言執行者の権利義務、1013=遺言の執行の妨害行為の禁止〕の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
3 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
4 前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
民法第1015条(遺言執行者の行為の効果)
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
民法第1016条(遺言執行者の復任権)
遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
民法第1018条(遺言執行者の報酬)
家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
2 第648条第2項及び第3項並びに第648条の2の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
民法第1020条(委任の規定の準用)
第654条〔委任の終了後の処分〕及び第655条〔委任の終了の対抗要件〕の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。
参考文献等
- 第一東京弁護士会司法研究委員会(編)『新版 遺言執行の法律と実務』ぎょうせい/2004年
- 東京弁護士会法友全期会(編集)『遺言書作成・遺言執行実務マニュアル』新日本法規/2008年
- 中川善之助、加藤永一(編集)『新版 注釈民法(28) 相続(3) 補訂版』有斐閣/2011年
- NPO法人 遺言・相続リーガルネットワーク(編著)『改訂 実務解説 遺言執行』日本加除出版/2013年
- 〔共編〕仲隆弁護士、浦岡由美子弁護士〔執筆者〕浦岡由美子弁護士、遠藤幸子弁護士・税理士、佐々木好一弁護士、菅沼真弁護士、鈴木茂弁護士、瀬川千鶴弁護士、仲隆弁護士、藤﨑太郎弁護士、三ツ村英一弁護士、村松聡一郎弁護士『遺産相続事件処理マニュアル』新日本法規出版/2019年
- 中根秀樹弁護士(著)『遺言執行実務マニュアル』新日本法規/2020年
- 山本 真太朗司法書士・行政書士/ブログ『遺産分割で動産の管理をするにあたってどのような点に注意すべきでしょうか。』2021.12.03/最終アクセス250929
- 山本 真太朗司法書士・行政書士/ブログ『遺産分割で動産の承継をするにあたってどのような点に注意すべきでしょうか。』2022.01.04/最終アクセス250929
- 山崎巳義(著)『遺言執行の手引〔第2版〕』商事法務/2022年
 企業・事業者向けサービス
企業・事業者向けサービス
 トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)
トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)



















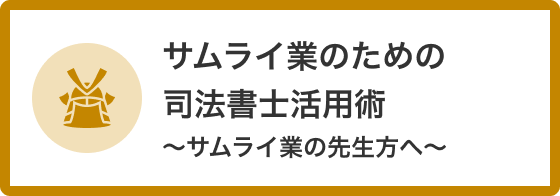
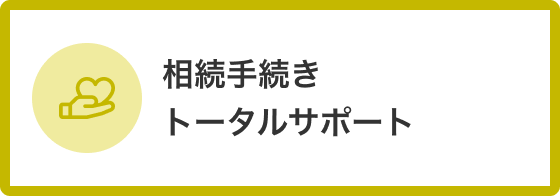
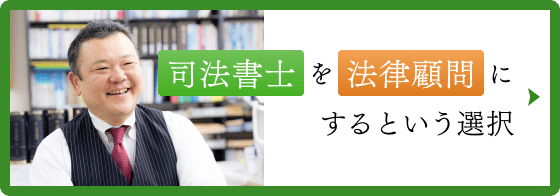

 個人向けサービス
個人向けサービス